特集/地域リハビリテーション 大都市の地域に根ざした(コミュニティ・ベイスド)リハビリテーション
特集/地域リハビリテーション
大都市の地域に根ざした(コミュニティ・ベイスド)リハビリテーション
―都市の福祉対応能力の強化のためのCBRの視点と戦略―
小島蓉子 *
地域社会が住民のニーズに答え切れない貧しい社会の中で障害をもつ人々の生存と福祉を守るために、家族、本人の周囲の援助者のギリギリの努力の中で地域に根ざした(コミュニティ・ベイスド)リハビリテーション(以下CBRと略す)という方策が出現した。だが援助能力の貧しい社会とは、果してGNPで評価される発展途上国だけのことだろうか。社会福祉そのものの貧しさは、GNPでは豊かなはずのわが国のような高度産業社会の中でも見ることができる。とりわけ住民の他者の問題に対する関心の希薄な大都市では、自然発生的な相互援助はひとりでは生きられない障害者や老人の生活をおびやかしている。本論文は現代の都市生活の危機と回復の方向性を模索するものである。
1.CBRの発展経過と特質
CBRと称されるリハビリテーションの実践方策は、臨床的な実践の手法というよりは、リハビリテーションという人間サービスを、地域の中に生活する全障害者に供給していく社会リハビリテーションの戦略であると見る。1970年代頃より、発展途上国の少数の心ある医師が限られた人材と資源を最大限に生かして、広い地域の中に埋れて苦しんでいる障害児童や障害者をひとりでも多く援助して行こうと、地域の住民の中に潜在している協力者たちの力を組織化し、教育しながら、実践したお金のかからない、その土地の文化に密着した援助供給システムである。これは発展途上国での児童福祉・健康対策であるプライマリー・ヘルス・ケアとは双子のような関係にある人間サービスの地域実践方式とも考えられる。
発展途上国での障害児・者に対する環境はきびしく、次のような構造を持っている。
(1)近代的な意味での医療・福祉・リハビリテーションの社会資源そのものは不在であるか、場所だけあっても人、金、物の不足から人的サービスは実施されていない。
(2)医師や援助者が少数いても、住民は山間地や離島に分散して住み、情報が届かないために障害者援助としてのリハビリテーションを知らない。
(3)人間に不自由をもたらす障害そのものに迷信や偏見がつきまとい、障害者の能力を客観的に認識することがなされないため、家族や本人自身も可能性を見ることなく、あきらめを感じ、障害者は無視されている。
(4)障害者が社会的な役割を担ったり、働いたりは出来ないだろうと思い込み、何の機会も与えることなく消極的な保護を与え、障害者の主体性は圧殺されたままでいる。
かような現実認識に基づいて、この現状を引き上るために練られた方策がCBRである。
フィリピンやインドネシアで実践されたCBRは、地元の価値や文化をありのまま受容し、住民の時間や空間の概念にマッチする方策でなくてはならないと、1980年にそれを指導した国際連合や、WHO(国際保健機関)は考えたのである。
たしかに発展途上国の主産業は農業で、水道や電気のない生活をしている。住民にとっては近代医学よりも、その土地に伝わる薬草やまじないの方が安心だし、効果があると信じられることは確かだ。発展途上国の社会はそれでは他者の問題に冷めたいか、というとむしろ、自然発生的な援助関係は緊密である。そして、フィリピンの「はだしのヘルスワーカー:カティワラ」のように、占い師、薬草についての知識の豊かな人、助産婦などのような人をめぐる信頼関係のネットワークも出来ている。そのような自然発生的なシステムと資源を生かしながら、地域住民をまき込んで医療とリハビリテーションの必要な人々に最大限の回復と発達の機会を与え、その地域生活への統合を援助していこうというのがCBRの輪郭である。
図1 地域の人々を動員してのCBR活動システム
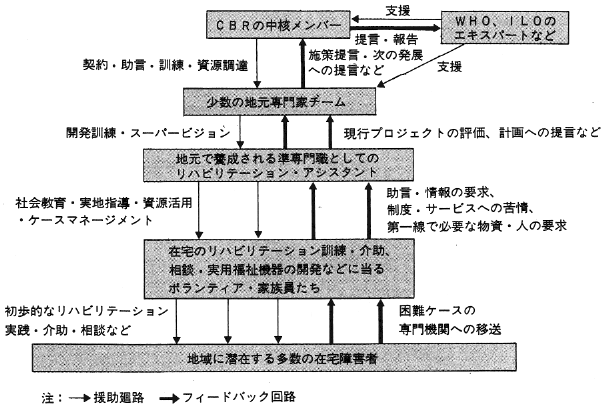
インドネシアにおけるCBRの実践報告の中からとらえることの出来るCBRの原則を要約すると次のようなことになる。
(1)地域の人々や組織を運動に巻込んで行う。
(2)障害者個人をリハビリテーションの対象としながらも、リハビリテーション・サービスをも実践することの利益を、障害者をめぐる地域住民全体に広く還元する(例えば地域センターの機能を開放しての保健教育や、プライマリー・ヘルスケアなどと共に行う)。
(3)地域の文化・生活水準に合致した方法と人材を通して行うこと。
(4)地域の既存の計画や資源を活用し、それを実施することのために特別な経済負担を住民や地域行政にかけるものではなく、自主的な労働奉仕などを歓迎すること。
(5)医療、保健、家族計画、教育、福祉などに関するあらゆる活動や社会資源を動員、調整して実施すること。
(6)CBRの目的を達成するためにキーパーソン(中心人物)の意図を地域の第一線で実践する人々。即ちはだしのヘルスワーカーあるいはリハビリテーションワーカーに伝えて、実践の第一線に立たせる。そのためキーパーソンである少数の専門家は地元人の信望が厚く、潜在的な能力のある人々を見出し、それらの人々を訓練して実践者に登用するなど、社会人教育をCBRの付随計画とすること。
以上のようにCBRは、少数の専門家が多数のクライエントに、地元で育成した準専門家を通してリハビリテーションの機会を提供することである。そのプログラムは①家庭で出来る機能訓練、②その土地で調達出来る素材を使った自助具の開発と利用、③その地域の児童と同等の教育を、住民手づくりの塾のようなものを作って提供すること、④働くことの出来る障害者には、地場産業について働くことができるよう訓練し、雇用、準雇用が可能となる保護職場を運営させること、⑤障害者の自助グループを組織化させ、教養向上、スポーツ、音楽、演劇、絵画、などを通しての社会活動を活発化させる、などのプログラムが含まれる。
以上に述べて来たようにCBRは、少数の専門家が、障害者にクリニックで対面するというようなものでなく、障害者の問題に地域住民のすべてをかかわらせて、システムとして、コミュニティ全体が障害者の回復と自己実現にかかわっていかせる地域運動である。西欧医学からすれば専門的とは言えないかもしれないが初期介入に、リハビリテーションの技術を加味したものである。
このような性格をもつCBRは、発展途上国だけが求めているものであろうか。今日人間の心の壁が人間同士の絆を引裂き、障害者ならずとも人間個人を孤独にしている先進国にあっても、CBRの考え方と実践モデルこそは、「地域社会の人間化をめざす運動」として、また「人間的な地域の復権」へのきっかけとして必要とされるのではあるまいか。
そこで次に人間性を失ってしまった大都市の衰弱、先進工業国の都会の生活サポートのもろさについて考察してみよう。
2.大都市の変動と生活基盤の弱体化
わが国の社会変動は今や、都市と農村をまき込んで進行しつつある。すでに始まっている農業社会から工業社会への変動過程で核家族化した労働者人口が大都市に流入し、若者世代が老人を残して農村は過疎化している。とりわけ若者の機動力と援助能力を失った農村では老人が一度病気になると食事も、排泄もままならず、ついに孤独死が訪れるといった不幸に見舞われる。かような孤立した人間の問題は都市生活にも拡大しつつあるのである。
1) ゆとりのない大都市の生活空間
人口が急増する大都市では、地価の急騰から住宅は無秩序に密集する。都市人口の大部分を占めるサラリーマンたちは職場に近い住いを見つけようとすれば小さなアパートにしか入れないので、子供の勉強や生活に必要なスペースを確保することが出来ない。一方、生活空間にゆとりを求めると長時間通勤で肉体的過労に耐えなければならないという苦しい二者選択にせまられるのである。
2) 社会資源の欠乏
たとえ大都市の只中に適当な住居が見つかったとしても、住宅地の中での公共施設は、計画的に配置されているわけではない。健康な人ならば地下鉄やバスなど段差だらけの複雑な公共交通機関を利用して、目的地に到達するわけであるが、それがきわめて困難な身体障害者や老人などにとっては、至難の業である。大都市ですべての人々が安易に利用できる病院、市役所、福祉事務所、各種リハビリテーションセンター、福祉会館などは、どれだけ適所に配置されていることであろうか。たとえノーマライゼーションが口で説かれたとしても、身体障害者や老人達が利用出来ないところに、それらがあったのでは、福祉の社会資源としては用を足さないことになる。
一方、精神薄弱者や精神障害者が一人の地域住民として、普通の社会に生活しようとしても、都市のスペースは金持ちの有力者から買い占められていく。不動産業者からも偏見の目でみられる身体障害者などのアパート探しは至難の業とされる。精神薄弱者の場合、しっかりした法人や行政の建てる施設でさえ住民の反対にあう今日、グループホームを町中につくることは、親の遺産の運用という形で入り込まない限り、容易に開所することは出来ないであろう。そこで勢い便利でなくてはならないはずの障害者の生活は、逆に不便で人々が近づきにくい場所で我慢しなければならないという矛盾に耐えしのばなければならないということになるものである。
3) 希薄化する大都市の人間関係
大都市の住民は、従来から居住していた住民(旧住居)とさまざまな出身地から移住して来た住民(新住民)との混合である。新住民の殆どはサラリーマンで職場を通しての人間関係は作りやすいが、妻や子ども達とは違って、地域の人々とふれる時間も機会もないために、近隣関係のネットワークに参加していない人々が多い。そうした新住民は、土地柄や地元文化との一体化の強い旧住民とは全く別の生活感情で生活するということになる。
わが国の大都市にはアメリカやヨーロッパのように階級、人種、職場の別を越えて人々を結びつける教会という連帯組織が必ずしも、どこにでもあるわけにはいかない。わが国の、大都市住民にとっての他者の援助を期待しうるものは税金と、納税者への見返り責任でつながる地方行政による福祉サービスが最後の頼りとなろう。それ以前に機能する援助が地域自助のネットワークといえば、わが国の冠婚葬祭時に見る勤労者の職場のつながりが唯一のものであろう。それは、欧米では見られないほど、個人の事柄に直線的に職場での身分関係が持ち込まれるので、気がねを前提にしたインフォーマルな援助の授受を覚悟しなければならない。
とりわけ、身辺介助や、食事や移動など個人生活の援助にかかわる、重度障害者の社会リハビリテーションの援助においては、インフォーマルな援助に欠ける都市生活は幾重もの困難に直面している。それらを列記すれば次の通りとなる。
①リハビリテーションに関する社会資源は大都市の地価高騰の余波を受けて、住民の近づきやすい所に配置されていない。②国の援助制度のメニューは多元的に分化し、ボランティアによる援助は乱立している割に、情報が少なく、その利用を助けてくれるサービスのコーディネーター及びその機関はない。③障害者の地域自立の基盤となる住宅問題は健康な市民にさえも解決されておらず、障害者がグループホームや、ケアハウスで自立しようとしてもその資源は無いか、全く不足している。④在宅介助を受けて大都市の中で自立生活をしていきたい身体障害者は多くても、介護手当で購入できる介護、介助サービスのマーケットが量・質共に成り立っていない。⑤これらの問題を地域レベルでトータルに解決すべき責任の所在は地方公共団体であっても、その地方行政の中に社会福祉計画とアドミニストレーションのノウハウを知る専門的人材と、彼らを生かすべき中心人物としてのキーパーソンが欠けている。その場合、たとえ福祉予算がついたとしても、地域の福祉実践に欠けるかまたは、質的に低下してしまう。
公的福祉が地域住民の急速に多元化していくニーズに追いついていけない間に、現実は別のルートを作り出す。契約社会の中で住民が止むをえず、お金と引きかえにサービスを確実に得る道として見出したものは、有料在宅介護、高額のケア付マンション、ベビーホテル、有償家事サービスなどである。これらは住民のニーズの高まりの中で止むなく現れた民間営利事業は、サービスの買手が無防備な弱者であるならば、非人間的な営利が先立つ危険性が伴うものである。この時こそ、専門社会福祉の倫理は、それを手放しで傍観せずに新しいニーズに応える権利擁護をせねばならない。また地域住民の税で支えられている地方自治体は、古い福祉システムを整理統合してでも、今日的な住民のニーズに、住民を二重、三重の経済的負担に苦しめることなく応えていく必要にせまられているのではないかと考えられる。
3.住民福祉に向けての大都市計画、再編成の課題
他人とかかわらない方がかえって気軽だと思い、地域の人々とのつながりから遠ざかって暮らしている人々が、病気や高齢になったら、断絶の社会の中で全く孤立してしまう。
かつての社会福祉の対象者は、一般中産階級の生活からかけ離れて見られる少数者に限定されていたが、今日の福祉社会の中では、その対象者の概念も全く様変りしている。我々一般社会の中産階級の勤労者生活の只中に障害者問題も、母子問題も老人問題も、単なる所得の不足という経済的貧困の故だけでなく派生してきて、家族員の普段の生活の仕組みに歪みを与え、生活ストレスをもたらすのである。
今日のリハビリテーション問題について云えば、戦後以来1970年代までのわが国の障害者福祉は生存権の限界を辛うじて守る生活保護の考え方に基づき、施設収容による救済を主軸として来た。しかし国際障害者年以降わが国も、欧米に20年遅れのレベルで、障害者福祉の本質を障害者が対等な市民として一般社会に生きる「社会的権利の追求」と、普通の人と対等な「生活の質の保障」に求める視点に転換し始めるようになった。
だが高度成長期の1960年代から1970年代にかけては、福祉財政のパイの拡大のまま、無方針といっても過言でないほど圧力集団各々からの要求に押し切られた形で、行政はバラバラなメニューとして諸制度を乱立させるに至った。それは一見総花式で、いかにも豊かな国の豊かな社会福祉プログラムに見える。しかしそれでいて、最重度の身体障害者を地域に自立させるための介助を徹底的に保障するとか、ひとりでは自立生活を営めない精神薄弱者に地域生活を保障するケアハウスを制度化することとか、自立援助のための資源を発動させるための援助のシステム化をする人を地域に配属してのケースマネージメントを徹底させるとか、基本的な課題についての地域リハビリテーションの政策を欠落させたままでいる。
事実、1980年代の行政改革、即ち、老人在宅福祉への重点移動、民間活力の強調、老人保健法の改正に伴う費用の本人一部負担制の導入、身体障害者授産施設利用料の本人一部負担制の導入、いわゆる中間施設やグループホームの新設、国と地方公共団体の措置費負担率の改訂、機関委任から団体委任への移行、社会福祉士及び介護福祉士法の制定によるマンパワーの強化などを内容とする。そしてこれらの一連の動きは施設から地域中心へ、中央集権から地方責任の強化への新しい福祉社会への脱皮過程の文脈でとらえることができる。
しかしその中で見えにくいのは、各種障害を持つ人々の社会生活権に対応する地域リハビリテーション政策の視点である。
わが国の大都市の福祉実践能力は、機関や行政プログラムがあったとしても、障害者が地域に生きる上での有効性について考えると、発展途上国のそれに劣るとも、それ以上とは云えない状態である。この現実に立って今や必要とされることは、障害者の生活権を保障するための仕組みを住民ぐるみで創り上げていくCBRの視点を明確化し、社会のネットワークを再編成するという課題に公・私あげて取り組むことであろう。
4.大都市のCBRの諸条件とその実践例
先発工業国においてのCBRは、援助を求める地域住民をけっして見過したり、無視したりしないケア・ネットワークを形成していくことである。大都市で自然発生的な援助網が存在しない場合は、それを形成するよう、行政も、社会福祉協議会も住民も協力しなければならない。
イギリスでは、1982年に発表されたバークレーリポートを契機として、地域におけるケアのネットワーク作りが一段と活発化した。障害者が地域で安心して住み、その地域生活の中で様々なリハビリテーションの課題を果していくためには、M.バルマーの云う次のような社会資源が大都市生活の中でも必要とされよう。それらは-
(1)親族、友人、近所などインフォーマルな個人的援助関係
(2)自然発生的な援助関係がない場合のボランティア援助組織
(3)当事者自身によるセルフ・ヘルプ(自助)団体を通しての権利擁護のための組織
(4)援助や適切な専門機関への橋渡し(リフアーラル)をしてくれる近隣援助ネットワーク作り(自助組織の援助は地域で孤立している人々の援助に適切である)
(5)地域ニーズに出発して、未だ充足されていない援助を形成したり、新しい対応づくりへの関心を行政に訴え、草の根の声を政策決定過程に反映させる民間の推進団体、及びそれのソーシアル・アクションの実施
以上のような地域のサブ組織が充分に発達し、一方それらの活用を個人の実情に合わせて行わしめる専門職者のケースマネージメントを障害をもつ住民に対して徹底して行うことによって先進工業国型のCBRが緒につくものであろう。
ところでわが国では、まだCBRの概念の定着もなく、地域に根ざしたリハビリテーションの実践も未だCBRとして自覚されておらず、先駆者の実験的段階と考えられるところから、CBR概念に近いと判断される大都市での実践活動を紹介してみたい。
第一のインフォーマルな援助については、障害者をめぐる大学生の介助グループや、父母の会が行う個人的なしかも信頼性のある援助である。
第二のボランティア組織として、最近活発な働きを見せているわが国の団体には盛岡市の「地域リハビリテーション協力会」や損なわれやすい精神障害者の社会的結びつきと食生活の維持を余暇と栄養指導で同時的に行う調布の「クッキングハウス」の活動がある。
第三の当事者自身による自助を基調とした地域に根ざしたリハビリテーションの実践は、八王子の「ヒューマン・ケア協会」や、「新宿ライフ・ケア・センター」などに見られる。
第四の近隣援助ネットワークでは、生活協同組合の地盤を生かし、生活物資のみならず、介助や介護をも会員同士で供給し合う「灘神戸生活協同組合コープくらしの助け合い会」は傑出した代表例である。一方、行政と社会福祉協議会の支援を背景に地域ベースの介助やケアを組織的に行う事例としては「世田谷ふれあい公社」などがあげられよう。
第五は、入所する障害者のニーズに応えるばかりでなく、地域に在住する障害者のニーズへのアウトリーチを施設を中核として繰り広げている事例には「藤沢湘南希望の家」及び「内潟療護園」を基地として行うコミュニティ・ケア実践がある。
以上のいずれの福祉実践も、今日のわが国の大都市の人間疎外への挑戦である。障害者のリハビリテーションの実践を地元社会の組織化、統合化から着手するこれらの動きはわが国の都市型CBRの先駆としてこれからも見守り育てられなければならない実践である。
参考文献と資料 略
*日本女子大学教授
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1990年6月(第64号)2頁~7頁


