第3節 福祉的就労分野での労働法適用拡大に向けた3つの選択肢
岩田 克彦(職業能力開発総合大学校 専門基礎学科)
はじめに
誰もが就労ないし社会に参加できる「排除しない社会」、「包摂する社会」の実現に向け、障害者の社会への統合促進が国際的潮流になっている。障害者でも就労可能な者は、一般労働市場ないし保護的就労環境で「ディーセントワーク」(働きがいのある人間らしい仕事)が保障されなくてはならない。日本においても、福祉的就労から一般就労への移行策267の積極的推進とともに、福祉的就労分野の障害者に労働法の適用を広げていく必要がある。そのためには、長期的賃金補填制度の適用を長期的課題として真剣に検討しつつ、当面は最低賃金の減額特例措置の拡大により、福祉的就労分野での労働法適用者の拡大を図ることが適切であると筆者は考える268。なお、こうした手段によっても労働法適用が難しい者に対しては、労働法各領域の特殊性に配慮した「福祉労働法」的な法律制定による労働法の部分適用ということになる。以下、それぞれ検討する269。
1.労働法の「ほぼ」全面的適用270(その1)-長期的な賃金補填制度の実施-
障害者と非障害者との間の「衡平」を重視し、労働能力の低い障害者にも減額特例なしの最低賃金を適用すべきだとの議論がある。障害は本人の責任で生じたものではなく、それを理由に「労働する権利」が損なわれるのはおかしい、障害者にも「ディーセントワーク」を保障すべきである、というものである。もっともな主張であるが、「合理的配慮」がなされた上で当人の労働能力、労働(価値)生産性が「適正に」評価され、その上で、労働(価値)生産性が最低賃金を下回った場合、その差額を「個別」事業主に負担させることは無理であろう271。したがって、その差額は公的制度による「賃金補填」(事業主への助成)で対応する必要がある。このような「期間を限定しない賃金補填」は、スウェーデン、オランダ、デンマーク、フランスなど多くのEU諸国で採用272されており、日本でも十分検討対象になろう。
(1)3つの課題
筆者は10年ほど前の論文273で、「長期的な賃金補填制度」の新設を提案した。すなわち、最低賃金の5-8割274程度の職業能力を有する者を、職業能力から算定される額を超える賃金(最低賃金かつ障害者加算を加えた生活保護水準以上)で雇い入れた事業主に対して、賃金補填を永続的ないし5~10年程度の長期間にわたって実施する制度275である。上記論文では以下の3つの課題を指摘した。第1に、障害者の職業能力評価が正確に行われる必要がある。第2に、福祉施策との調整が必要である。地域に生活できる場所がないと企業就業も進まないし、一定水準以上の賃金が保障されるのであるから、障害年金受給額を減少させる方向での検討も必要となる。第3に、障害者及び雇用事業主が既存の能力認定に甘んずることなく、職業能力の向上に努めるインセンティブを持ちうる仕組みの設定が必要である。この3点の課題への対処がポイントであるとの認識は今でも変わらない。
(2)障害者の就労能力評価システムの構築
特に、障害者の就労能力を評価する何らかの仕組みの構築が重要であろう。賃金補填制度や障害者年金・手当の支給に当たり、就労能力の評価判定を踏まえている国が多い276。フランスでは、多分野の専門家チームの活動を統括するMDPH(県障害者センター)内に設置されたCDAPH(県障害者権利自立委員会)が、就労を含めた障害者の置かれた様々な側面での能力低下率を判定し、障害者にいろいろな助成金、サービスを受ける権利が与えられる。
オランダでは、2006年1月策定の「就労能力に応じた労働及び所得に関する法律」に基づき、残存する就労能力判定に応じ、障害保険年金の支給額が変化する。「保険医師」の評価の後、労働市場専門家が「受給者に障害がない」時の所得と残存就労能力による所得を比較し、受給者が残存機能を使ってできる仕事を3種類決定する(3種類以上見つかった場合は、所得額の多い3つが選ばれる。)という。そして2番目の仕事の賃金額と前職の賃金の差が「就労能力の差」と判断される。イギリスでは、2007年成立の福祉改革法により従来の就労不能給付(Incapacity Benefit)が雇用及び生活補助手当(Employment and Support Allowance)に移行し、従来の「個人能力評価」から「就労能力評価」(Work Capability Assessment)と呼ばれる評価方式に変わった。世界の福祉改革の大きな流れ-「できないこと」から「できること」を重視(from disability to ability)-に沿い、就労能力の制約評価、就労関連活動の制約評価、就労に焦点を置いた健康関連評価が行われている277。
アメリカの障害保険給付における障害認定も5つの段階を経て行われる。第1段階は給付申請者の就労状況に関する判断で、一定額以上の収入がある者はどのような医学的状態にあっても障害者と認められない。第2段階は機能障害の認定であるが、機能障害が労働に関する基本的活動を妨げる深刻なものでなければならない。第3段階で、申請者の機能障害と、社会保障庁(Social Security Administration)の定めたリストにある機能障害の種類及び程度とを照合する。第4段階は申請者が過去に従事していた仕事の遂行が可能かどうかを、身体的残存能力と精神的残存能力で判断する。第5段階は他の種類の仕事ができるかどうかの検討である。
このように、障害者の就労能力評価システムが多くの国で構築されている。長期的人材育成システムが普及し、同一労働同一賃金原則が浸透しづらいとされる日本ではあるが、近年、労働市場の流動化が進んでいる。医療専門家と労働市場専門家との協力による障害者の就労能力評価システムの構築278や就労と各種給付との連動そして就労・所得保障制度全体の総合調整を真剣に考える時期であろう。
(3)他の課題と今後の検討の方向
第2の課題-就労移行支援や所得保障に関する福祉政策と労働政策の連携については、第1章の拙稿を参照されたい。第3の課題-障害者及び雇用事業主が既存の能力認定に甘んずることなく、就労能力向上に努めるインセンティブを持ちうる仕組み-については、賃金補填制度と併行して給付付き税制控除等の導入が必要であろう。
さて、出縄氏が言うように、「高福祉高負担」社会になっていない日本において、長期的ないし永続的な賃金補填制度の導入は、財政的にも限界があり、かつ国民のコンセンサスを形成することは難しい。また、脱施設化の流れを阻害しないよう制度設計を慎重に行う必要があるし279、事業主に対する給付方法も簡略な方法280を工夫する必要がある。当面は次に述べるように、最低賃金の減額特例の適用対象者を拡大し、長期的賃金補填については、西欧諸国での制度適用の実態や幅広い視点からのコストベネフィット分析を踏まえた検討をすべきであろう281。
なお、公的な経済的補てんは、必ずしも賃金補填措置だけではない。「労働・雇用分野における障害者権利条約の対応の在り方に関する研究会」では、現行の障害者雇用納付金の額を最低賃金とリンクさせるべく大幅アップを図るべきである、との意見があったようだ。就労能力の低い障害者を雇う経済的コストを事業主全体で広く分け合おうというものだが、企業サイドからの大きな抵抗で、実行はかなり難しいと筆者は考えている。
2.労働法の「ほぼ」全面的適用(その2)-最低賃金の減額特例の適用拡大-
2008年7月に施行された改正最低賃金法により、都道府県労働局長の許可を受けた障害者を最低賃金制度から適用除外する規定が削除され、その代りに、都道府県労働局長の許可を要件として、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」には、「最低賃金額から最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額」を適用することになった(最低賃金の減額特例、最賃法第7条1号)。同法施行規則第5条では、最低賃金の減額率は、当該障害者の「職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定める」とされている。この減額特例が授産施設等の利用者に広まれば、こうした障害者にも労働者性が認められ、労働法の保護が受けられることになる。障害者の権利条約でも、「適切な措置」(appropriate steps)の中に、「適当な政策及び措置(積極的差別是正措置【affirmative action programmes】、奨励措置その他の措置を含めることができる。)を通じて、民間企業における障害者の雇用を促進すること」(第27条1(h))とある。最低賃金の減額特例の適用が、積極的差別是正措置”(アファーマティブ・アクション)とみなすことができれば、条約批准上は何ら問題ないことになる282。
(1)最低賃金減額特例の適用拡大に対する5つの異論
最低賃金の減額特例を「積極的雇用差別是正措置」とすることに対しては、主として5つの異論がありうると筆者は考える283。第1の異論は、賃金補填を主張する立場であり、そもそも障害は本人の責任ではないので、賃金で差をつけるのはおかしい、したがって、職業能力が低い障害者が最低賃金相当分を賃金として受理できるよう、賃金補填をすべきだというものである(本稿の前節参照)。第2の異論は、労働者と認められる形態で就労をしていることを前提とするならば、そうした障害者について最賃の減額特例措置を適用すること自体が正当な理由のない差別にあたるのではないかというものである。第3の異論は、安易に最低賃金の減額特例を認めると、障害者も事業主(ないし福祉施設運営者)も安易に福祉的就労環境に甘んじることになりがちで、一般労働市場賃金での就労が進まなくなるというものである284。第4の異論は、最低賃金の減額特例の実態は、低コストで障害者を安易ないし「あこぎに」使用している場合が多く、「積極的雇用差別是正措置」になっていないのではないか、との批判である。第5の異論は、様々な手段(雇用率制度の強化、合理的配慮措置、職業リハビリテーション、ジョブコーチ等)を用いて減額特例措置なしに一般就労を積極的に進めるべきであって、こうした手段によっても一般就労が難しい障害者に労働法を適用すること非常に難しい、というものである。
(2)5つの異論に対する筆者の考え
第1の異論に対する筆者の考えは前節を参照されたい。第2の異論は、トートロジー的な議論、すなわち、「厳密に労働者と認められる形態での就労ではないので労働者ではない」との議論になりかねない。すなわち、長期的に労働(価値)生産性が最低賃金を少しでも下回る者は労働法の保護を全くないしほとんど受けられなくなる可能性が高く、結果として障害者雇用の抑制につながる議論だと思う。最賃額の弾力的な引上げも難しくなろう。最賃の減額特例は、障害者ないし「障害により著しく労働能力の低い者」に対して即減額を認めるというのではなく、地方労働局長が、「個々人の労働能力等を勘案し能力に応じた賃金」を認定する仕組みであり、障害者差別とは言えないと筆者は考える。労働能力が低いと認定された「労働者」が、労働法規制で保護されながら最低賃金を下回る賃金の低さを他の公的支援で補い労働する(こう考えると、長期的賃金補填とも類似する。)という選択肢を活用すべきであろう。第3の異論に対しては、福祉的就労から最賃額以上を稼ぐ一般市場での本格的就労へ向けた方策も同時に積極的に実施するのであり、最賃減額特例はそうした対応が取れない者への対応策であり、また、障害者や事業主が保護雇用に甘んじないような取り組みも重要である、と応答したい。第4の異論は厳しい指摘であり、最低賃金の減額特例措置が、実際、「積極的差別是正措置」となっていると、より説得的に主張できる運用を目指すべきである。現時点で最賃減額特例が適用されている者の実態把握に努めるとともに、①減額幅の改善努力(就労能力向上方策等)と一定期間ごとにおける「能力に応じた賃金」の再評価、②監督署による就労能力判定技能の向上、③悪質な事業主の取り締まり285、④都道府県労働局間の減額認定幅の差異解消、⑤発注奨励(障害者雇用率換算)や雇用改善コンサルタントの活用拡大による就労継続支援B型施設からA型施設への移行推進、等が重要であろう。第5の異論は、一般就労化方策の効果に楽観的すぎるし、一般就労(就労継続支援A型を含む)ができない者には労働法のほとんどの領域を適用できないというのは、障害者権利条約の趣旨(社会への包摂)に沿う方向ではないのではないか、と筆者は考える。
(3)最低賃金減額特例の適用拡大後の所得保障
さて、最低賃金減額特例が適用拡大された状況で、障害者の生活保障はどのようになるのであろうか。障害者雇用率を達成している企業を前提にすれば、減額特例が適用されれば、障害者納付金制度の「報奨金」相当額(障害者雇用率を超過した1人当たり月額2.1万円)を企業は賃金に充当できる286ので、「障害基礎年金」(2級は月額6.6万円287)を合わせ、
障害者の獲得総収入=障害者が労働で稼ぎ出す賃金+報奨金相当額を賃金として支給+障害年金>(一番水準の高い東京都での)生活保護の18歳単身者基準
が一つの目安になるのではないだろうか。
具体額の目安として、生活保護の18歳単身者基準を考えると、一番水準の高い東京都では、13.9万円である(無職・無収入)。最低賃金を目安にするならば、東京都の地域最低賃金は約13万円である。最低限の所得保障の目安は全国一律に揃えた方がいいと筆者は考えるので、結局、少なくとも4~5万円の賃金原資を自前で確保することができる事業所に減額特例を適用することになる。松井氏(第3章第1節)は、減額特例で許容される限度額を全国最低賃金(加重平均713円)の50%(労働能力が50%低い)とすると、時間当たり工賃は365.5円となり、この障害者が仮に1日6時間、月20日間就労すると月当たり工賃は4万2780円となると言うが、ほぼ見合う水準であろう。年金受給権を有しない者(無年金障害者)には、現在「特別障害者給付金」(障害基礎年金2級相当に該当する者は、月額約4万円、1級相当に該当する者は月額約5万円)が支給されているが、その増額ないし基礎年金相当額の支給が望まれる(図1参照)。
図1 最低賃金減額特例の適用拡大後の所得保障(概念図)
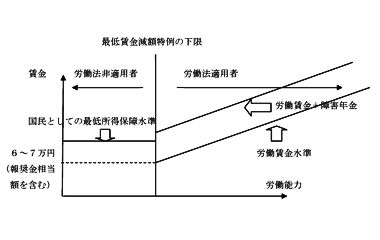
さて、松井氏(第3章第1節)が言うよう、授産施設の平均工賃が政府目標通り倍増されたとしても、4-5万円の賃金原資を自前で確保できない授産施設も多く残り、こうした施設には最低賃金の減額特例が適用されないことになる。経営改善コンサルタントの一層の活用、「ハート購入法」の制定、授産施設等への発注を障害者雇用率に換算する等の取り組みが求められる。この取組結果を踏まえて障害基礎年金自体の引き上げも検討すべきであろう288。
なお、労働法適用者が増えることにより、同一施設内の労働法適用者、非適用者の混在化が進めば289、現在の福祉工場(ないし移行先としての就労継続支援A型事業所),授産施設(ないし移行先としての就労継続支援B型事業所)を一本化すべきであろう。
3.労働法、社会保険法の部分適用
福祉的就労分野での就労者を労働法上の「労働者」ないし「労働者に類する者」とみなし、労働諸法を改正ないし法解釈を変更することは難しいとする意見も根強くある。また、長期的賃金補填や最低賃金減額特例の適用拡大によっても、就労能力が相当低く労働法の適用を受けることができない障害者は残り、こうした者向けに生きがいと就労が表裏一体となった「就労」施設の役割は今後も残るであろう。欧米諸国においても、生産年齢世代の日中の活動場所は、基本的には、一般雇用、保護雇用就業(国によっては一部非雇用形態を含む。)、デイセンターの3つに分かれる。「デイセンター」(日中に介護やレクリエーション的作業を提供する施設)利用者等労働法の適用拡大が難しい者に対しては、作業中の安全衛生などの労働法及び被用者を対象とした社会保険法の部分適用を考える必要がある290。
筆者は、アラン・シュピオの「4つの同心円モデル」が大変参考になると考える。アラン・シュピオを中心に学際的専門家からなる「労働法の未来」グループが、欧州委員会により1996年に組織され、1999年に「雇用を超えて」と題する報告書を取りまとめた。その中で、労働・社会保障にまたがる社会的権利を4つの同心円に整理した(英語版p54-55)。社会保障上のリスクと雇用関係での依存性を同一視せず、雇用労働者、自営業者、無償労働とどのような就業形態を選択した場合でも極端な不利益を受けず、離職・転職等があっても、職業人としての地位(statute professional, membership of the labourforce)が維持できることを狙った大変刺激的な問題提起であり、その後労働法研究者等の多くの論文で取り上げられている(各円に当てはめる具体的権利内容については、論者によって微妙に異なる。以下は、筆者の考えである)(図2)。
一番外側の円、すなわち、「仕事の有無を問わない普遍的な社会的権利」には、基礎的な医療・年金・生涯教育・生活保護等が挙げられる。これらは、国民一人一人が生きていくためのいわば「ナショナル・ミニマム(ないしシビル・ミニマム)」である。
外側から2番目の円、すなわち、「有給・無給に関わらずワーカー(島田陽一早大教授の表現では労務供給者)に共通する課題」としては、健康安全の確保、雇用・就業面での差別禁止、個別労働関係の紛争処理が挙げられる。健康安全の確保は、シュピオは第3の円に含めているが、人命の尊重に関わることであり、有給・無給に関わらず、仕事の管理責任者に、従来の労働法での使用者に類似する責任を課することを検討すべきである。雇用・就業面での男女間等の差別禁止も、就労環境の整備の観点からは、ワーカーに共通する課題であろう291。個別労働関係の紛争処理手続きルールを規定しておくことは、有給・無給労働に関わらず有用であろう。
外側から3番目の円、すなわち、「雇用・自営を問わず、有給ワーカーに共通した適用を検討すべき課題」としては、職業単位ごとの協会組織の育成、団体交渉制度の導入、積極的労働政策などが挙げられる。
一番真ん中の円は、雇用労働であるが、使用従属関係でいくつかの層(一番内側がフルタイムの正規社員)に分けることができる。なお、第3の円と第4の円の間に、「雇用的自営(経済的従属ワーカー)に適用すべき法規制」として、最低賃金(収入)制の適用、未払い賃金の立替払い制度の適用など報酬の支払いの確保、労災保険、労働基準法の解雇関係規定の適用など契約解除に関する規制、等を挙げる論者も多い。
一番外側の円、すなわち、「ナショナル・ミニマム(ないしシビル・ミニマム)」に相当する領域は、「労働法が適用されない」福祉的就労従事者に対しても当然適用されるべきである。筆者は、家事労働やNPO等でのボランティア労働を念頭にした第2の円も、基本的には適用すべき法領域と考えている。第3の円は、雇用労働者だけでなく「自営」等にも適用すべき領域であるが、「福祉的就労従事者」にも適用可能な事項が多いと思われる。但し、「福祉的就労従事者」という新たなカテゴリーを、労働・社会保障関係の各法律に共通なものとして創設することは、線引きが難しい。どの同心円のどのあたりの位置にくるか大雑把な位置関係を踏まえつつ、立法の趣旨・目的に照らして法律ごとに適用範囲を定めることが適切ではないだろうか292。
図2 労働・社会保障法の4つの同心円(アラン・シュピオ『雇用を超えて』(1999)を筆者一部修正)
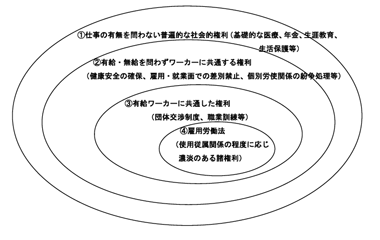
おわりに
福祉的就労従事者への労働法適用については、長期的賃金補填制度の適用を視野に入れつつ、当面は最低賃金の減額特例の適用拡大による労働法の「ほぼ」全面適用者の拡大が適切である。もちろん、悪用防止、さらなる雇用改善に向けた不断の努力が不可欠である。これが筆者の結論であるが、こうした障害者への就労・生活支援策を積極的に進めるためには、そもそも、国民の理解とバックアップが不可欠である。確かに、近年、社会保障問題への国民の関心は大変高まっている。しかし、年金、医療、児童福祉等に比べ、障害者問題については、残念ながら関心は低いと言わざるをえない。昨年から今年にかけて、「社会保障国民会議」や「厚生労働行政のあり方検討会 」、「安心社会実現会議」等、社会保障に関し重要報告書が多く出されたが、障害者問題についてはほとんど言及がなかった。
筆者は、研究者、障害者団体、障害者関連施設関係者の共同プロジェクトとして、障害者を巡る全体状況の、分かりやすい実態と対策を提示することが肝要だと考えるが、今回の研究プロジェクトが、その方向に向かう第一歩となれば幸甚である。
(※)拙稿執筆にあたり多くの方から頂いた丁寧なご助言に厚く感謝したい。但し、拙稿の内容はすべて筆者個人の責任で執筆したものである。
【参考文献】
- 岩田克彦「雇用と自営、ボランティア-その中間領域での多様な就業実態と問題の所在-」(2004)『就業形態の多様化と社会労働政策』第1章、労働政策研究報告書No12、労働政策研究・研修機構
- 樋口美雄・宇野裕・岩田克彦「労働・社会保障政策の総合的展開をめざして」(1998)、『季刊年金と雇用』第17巻第2号
- Supoi.Alan(1999),”Beyond Employment”
- Employment & Social affairs,European Commmission(2002),“Definition of Disability in Europe.A Comparative Analysis”,Appendix1(The assessment of incapacity of or inability to work.)
- EASPD(European Association of Service Providers for Persons with Disabilities)(2007),“An international comparison of methods of financing employment for Disadvantaged people”
