III. 1.避難訓練
今年度は、津波による被害の可能性がある標高10メートル以下に立地する、べてるの活動拠点と住居すべてにて避難訓練を行った。
活動拠点:ニューべてる、べてるセミナーハウス、4丁目ぶらぶらざ
GH:べてる、潮見ハイツ、フラワーハイツ、ぴあ
共同住居:みかん、ひかり、おざき荘、レインボーハウス、駅前ハウス
一般住宅:しおさい荘、きれい荘、武田ハウス
※べてるにはこの他にリカウスというGHがあるが、十分な標高があり、津波による被災の可能性はほぼないことから、本年度の避難訓練の対象からははずした。
活動事例 その1 日中活動拠点/住居からの避難訓練
4丁目ぶらぶらざ・共同住居レインボーハウスからの合同避難訓練(通常期避難訓練)
4丁目ぶらぶらざは浦河町内の大きな商店街、大通り4丁目の3階建ての1階にあり、べてるの商品や町内の他店の商品を売っている。誰でも気楽に立ち寄ってぶらぶらしてもらう場所という意味で「ぶらぶらざ」と名づけられた。店舗としての性格上、メンバー以外にお客様がいる可能性が高いので、非常時には安全に避難場所までお客様を誘導する必要がある。
4丁目ぶらぶらざの2階、3階は女性だけの共同住居(レインボーハウス)となっており、現在8名のメンバーが暮らしている。平成18年度には共同住居に住むメンバーで避難訓練を行っている。今年度は4丁目ぶらぶらざ、レインボーハウスともに冬期・夏期両方の避難訓練を実施した。特にレインボーハウスでは冬期夜間の訓練を実施した。


さあ避難訓練開始!
a)事前準備
・レインボーハウス:住居ミーティングにて、12時間避難先に滞在することを想定して、どんな避難グッズが必要か話し合い、準備した。
・4丁目ぶらぶらざ:8月7日の「4ぶらミーティング」において、かつて経験した災害について話し合った。十勝沖地震や阪神大震災での体験や、「寝るときにはいつもスリッパと眠剤はいつも用意している。ガラスが落ちたら歩けないし、眠剤なしでは避難してもバテてしまうから」という知恵などが出された。
b)避難訓練
8月28日(火) 13:30~
十勝沖地震発生による津波警報が発令されたという状況を想定し、この日の店番担当者の誘導での避難訓練を実施した。
まず、メンバースタッフの司会による「4ぶらミーティング」を開き、みんなで避難訓練の意義について話し合った。次にDAISY版避難マニュアルを見て避難経路を確認し、参加者の役割(先導する人、後方確認する人、車椅子を押す人、車椅子に乗る人、歩行に困難がある人の手を引く人)を決めた。入り口近くにいたメンバーが自動ドアのスイッチを切り替え、手動で開ける作業を担当した。全員が一斉に避難体制へ入るために、地震発生にはカウントダウンを行った。
本訓練では、最後尾の人が目標地点(標高10mの高さ)に到着するまで4分35秒だった。訓練を繰り返すともう少し早くなると推測される。
参加人数約50名:べてるメンバー25名 見学者10名 学生・スタッフなど関係者10名 他福祉施設スタッフ5名
c)避難の様子と振り返り
①歩行に困難のあるメンバーの避難に関して
あるメンバーは、日常生活では一人で対応できる一方、スピードが求められる津波や火災など避難時についての不安を感じており、どのように支援するか皆の課題となっていた。今回は仲間に手を引いてもらいながら避難場所まで自分で歩いた。実際にやってみると、仲間の助けがあれば避難先に行けるので、支援の重要さを実感したという。また汗で手が滑ってしまうので、ハンカチを握るなど手のつなぎ方の工夫が生まれた。
【本人のコメント】
当日は体調も悪く、本当に不安だったのですが、仲間の力を借りることが出来て本当に助かった。私は地域で一人暮らしをしているので、これらはいざという時、誰かに応援をお願いしようかなと思った。

②車椅子に乗ったメンバーの援助に関して
災害時に車椅子で移動することが適切と思われるメンバーが、避難用車椅子に乗り、仲間の協力で全行程を避難することができた。ホームヘルパーの経験を持つメンバーが車椅子の押し方を指導した。ただ車椅子のタイヤの空気が抜けていたため車椅子で坂道を上るのがとても大変で、4人体制でやっと押していった。
【よかった点】
大勢での訓練だがスムーズにできてよかった。
住居の仲間がたくさん参加できてよかった。
レインボーハウスに住む人で、なかなか住居の人もスタッフも日常的には会っていないメンバーが参加し、話すことができた。
【さらによくする点】
車椅子の日常的な点検が必要だと実感した。
4ぶらは店舗なので、体格の違うお客さんのために車椅子を3台用意してはどうか。
車椅子だけでなく、杖などを検討してはどうか。
寝ているときとか、靴をはいてから出るというのをやってみたかった。
今後周りの商店とも合同で避難訓練を行いたい。

レインボーハウスからの冬期避難訓練
a)事前準備
夏の避難訓練前に防災グッズの準備は完了していた。夏期の訓練以降、新しく入居したメンバーがおり、冬期の夜間訓練も初めてだったので、当日、避難訓練直前に住居のメンバー(2人)と国リハスタッフで避難経路を下見した。DAISYの避難経路マニュアルの写真をその日の写真に入れ替え、避難訓練直前に全員で確認した。その際、最終目的地であるファミリースポーツセンターまでの道のりでは風が冷たいので、避難先は標高10m以上にある測候所とすることに決め、また積雪のため滑りやすいなど冬期の注意点も確認した。

雪道の中、上りきった清水さんと泉さん。
b)避難訓練
1月18日(火)17時30分~
住居からの火災発生及び津波警報発令を想定し、各居室から避難場所(測候所)へ避難した。地震発生のカウントダウンの後、それぞれの居室に声を掛け合いながら1階までおり、屋外に出た。冬期夜間で雪が凍って非常に歩きにくい状況だったが、全員が約5分で目標とする標高10mの地点に到達することができた。
参加人数10名:共同住居レインボーハウス入居者6名、べてるスタッフ1名、国リハスタッフ3名
c)振り返り
【よかった点】
外は寒かったが、防寒シートは暖かかった。避難グッズを背負って行ってみて、反射板が光るのがよかった。
雪が積もったところの方がかえって歩きやすかった、それがわかってよかった。
避難マニュアルの音声が同じ住居のメンバーの声で、なじみがあって安心した。
測候所まで意外と近く、スポーツセンターまで上がると大変だけど、安全な所までであればそれほど慌てなくても大丈夫だとわかった。
【さらによくする点】
凍っていて滑りやすいことで苦労したが、両手を使えるようにしておくことが大事だと思う。玄関のライトを抜いて持っていくことを忘れたので、そのことがずっと「お客さん」となって頭に残っていた。
今回は十分に防寒対策ができたが、必ずしもいつもその状態で避難できるとは限らないが、靴下を準備しておくなど、いろいろ工夫ができそうだと思った。アルミの防寒シートは上手に使うことはできるのではないか。
津波への対応ではないが、避難梯子の使い方も練習したいと思った。

レインボーハウスでの振り返り。
4丁目ぶらぶらざからの冬期避難訓練
a)事前準備
DAISY作成チームのメンバーが国リハスタッフとともに避難経路を確認し、冬期版DAISY避難マニュアルを仕上げ、事前のミーティングにてこの避難マニュアルを見て、避難経路を確認した。また転倒や怪我をしないよう、防災みなみ体操を行った。レインボーハウスから防災グッズを借り、担当のメンバーを決めて避難所まで運ぶ体験をした。また坂道を登りやすいように、車椅子に防災グッズで購入した紐をつけた。そのほかトランシーバーの使い方を学び、避難誘導者、中間、最後尾を担当するメンバーが実際に通信しあい、全体の状況を確認しつつ避難した。
なお、冬期避難訓練には消防署の方に監督をお願いした。
b)避難訓練
2月27日(火)14時00分~
参加人数39名:消防署2名、べてるメンバー30名、べてる家族1名、べてるスタッフ1名、そのほか2名、国リハスタッフ3名

活動事例 その2 その他の日中活動拠点からの避難訓練
ニューべてるからの冬期避難訓練:築地地区
ニューべてるは現在のべてるの家の中心的な活動拠点であり、法人本部および二つの作業所の事務所もここに置かれている。毎朝行われる「朝ミーティング」をはじめ、「SST」、「金曜ミーティング」、「グッズミーティング」など様々なプログラムが行われる。また昆布詰めやTシャツ作成などの作業の場所でもある。平成18年度にも夏期の避難訓練を行った。

a)事前準備
前日、DAISY作成チームメンバー1名、ニューべてるを利用しているメンバー1名が、国リハスタッフ(2名)とともに避難路の確認、写真を撮影した後、冬期の避難マニュアルを準備した。
b)避難訓練
1月18日(金)13時30分~
冬の昼間、作業中に、十勝沖地震による作業所の火災発生及び津波警報が発令されたという想定で、作業場(1階)から避難場所への避難訓練を行った。
避難訓練開始直前に徳島県美浜町作成の「防災みなみ体操」で準備運動をし、避難マニュアルにて避難経路を確認した。訓練後、全員で振り返りを行い、災害時非常食を試食した。

ニューべてるから車椅子を引いて避難した。
参加人数44名:べてるメンバー27名、べてるスタッフ7名、浦河赤十字病院スタッフ・家族会・ボランティア4名、国リハスタッフ3名、来客者3名
c)振り返り
避難経路を冬雪の少ない道路にしてよかった。
体操をして体があったまった。
雪道の坂で車椅子が大変だった。
セミナーハウスからの冬期避難訓練:築地地区
セミナーハウスは、小規模授産所浦河べてるの活動拠点として製麺作業をしたり、大人数の研修施設としてお客さんを迎えたオリエンテーションをお恐なったりする施設と、2つの共同住居(みかん・潮見ハイツ)のある複合施設である。平成18年度には昼・夜2回の避難訓練を行った。

セミナーハウス

DAISY版避難マニュアルをみんなで見る。
a)事前準備
昨年3月に行った避難訓練の写真でDAISY避難マニュアルを作成した。
b)避難訓練
2月22日(金)16:00~
今回は消防署の方から指導を受け、消火器の使用訓練を行った。その後、セミナーハウス内の1室に集まりトランシーバー利用方法についDAISYで確認し、ニューべてるのスタッフと通信練習をした。避難訓練直前に、役割分担を決めた(先頭(1名)、最後尾(2名)、車椅子を押す係(2名))。雪道での転倒防止を防ぐため、防災みなみ体操で準備運動をした。
スタートの合図(スタッフ)で、一斉に避難開始した。最後尾が10メートルに達するには約8分かかったが、道路横断時の信号待ち、踏切遮断機があがるまでの待ち時間を差し引くと、もう少し短かったと思われる。
参加人数22名:べてるメンバー10名、スタッフ3名(うち1名は留守番)そのほか(国リハ・防災フォーラムシンポジストを含む)9名
c)振り返り
【よかった点】
事前に経路を確認してから避難できたので、以前よりスムーズにできてよかった。
DAISYのマニュアルに自分たちの顔がでてきて、自分たちのための避難マニュアルだなと実感できて、やっぱりDAISYはいいなと思った。
消防、警察、支庁など、地域の資源となる人たちにべてるの避難訓練を知ってもらうことができてよかった。
みんなまとまって避難できてよかった。
今、ホテルのフロントで働いているが、べてるでの避難訓練の体験を自分の仕事に活かせると思う。べてる以外の場所でも人が集まりやすい場所に応用できるといいと思う。
最後尾の人がきちんと確認できていてよかった。
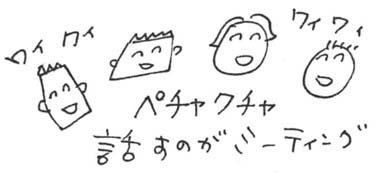

セミナーハウスからの避難経路

避難先からトランシーバーで連絡
【さらによくする点】
避難マニュアルを流れとして見られるようなものがもう一つあるといいと思った。
これまで大きな地震を浦河で経験したが、いざという時にはパニックになるので、どんなことが起こるか、またどうしたらよいかについて日々伝えていくことが重要だと思う。
スタッフがいない夜間にどうやって避難できるかがいつも気になっている。住居のメンバーでまたやってみたい。
<お客さんから>
「楽しく」避難訓練をしている要素があったのがよかった。災害が怖いのはみんな知っているが、楽しくないと続かないので、こんなことをやろう、あんなことをやろうというアイディアが出てくるような楽しい訓練が大事だと思う。近所の建物などの防災資源をもっと活用する方法は工夫できるのではないか。
地震の研究者として予知が実現していないことは申し訳ないが、今後も一緒に考えていきたい。
活動事例 その3 共同住居からの避難訓練
しおさい荘、フラワーハイツ・ひかり、きれい荘からの冬期合同避難訓練:東町うしお地区
浦河高校を避難場所としている共同住居(3カ所)のメンバーが協力し、合同冬期避難訓練を実施した。
参加した共同住居とGH
1.しおさい荘
しおさい荘には11名のメンバーが暮らしているが、海岸線近くに立地し、地震発生後、迅速に避難する必要がある。
2.フラワーハイツ
フラワーハイツには合計6名のメンバーが暮らしている。幻覚、妄想が強いメンバーもおり、避難訓練では彼らと一緒に避難するための工夫が必要だった。

フラワーハイツ
3.きれい荘
きれい荘は4名のメンバーが暮らしている。浦河高校に最も近い共同住居の1つだが、避難訓練は今回が初めてであり、避難経路での注意点、危険箇所を確認した。

a)事前準備
浦河高校と避難訓練実施の連絡をし、前日までにしおさい荘、フラワーハイツから避難経路を踏査し、冬場の留意点を確認した。
b)避難訓練
2月26日16時半~
各住居にて最新のDAISY版避難マニュアルによる経路の確認、防災みなみ体操、先頭・最後の担当、防災リュックや懐中電灯を持つ人の確認をした後、トランシーバーを使って3地点から同時にスタートした。しおさい荘からは、これまで他のメンバーとともに行動する機会のなかったメンバーが参加し、総勢10名となった。いずれの住居からも、雪道の中でも整然と避難することができた。避難訓練後は消防署の方から総評をいただき、全員フラワーハイツに戻り、合同で振り返りを行った。
参加人数20名:①しおさい荘・武田ハウス:入居者8名、スタッフ1名、ATDO1名、②フラワーハイツ・ひかり:入居者4名、スタッフ2名、国リハ1名、③きれい荘:入居者2名、国リハ1名


フラワーハイツでの合同振り返りMT
c)振り返り
【よかった点】
防災グッズを持っていったがあまり重くなかった。(しおさい荘)
きれい荘からは2名参加でき、雪道も経験できてよかった。4分以内に間に合うことがわかってよかった。避難グッズの用意をしていないので困ったなと思った。(きれい荘)
今日は幻聴さんが静かだった。黙ってついてきてくれた。(フラワーハイツ)
トランシーバーがどこまで届くかを確認できてよかった。
【さらによくする点】
しおさい荘では、きれい荘・フラワーハイツからの音がよく聞こえなかった。きれい荘・フラワーハイツ間は聞こえた。今後、中継に携帯電話を使うなどの対策を含め、連絡の取り方も考えていけるといいと思う。
しおさい荘では、2階の人は靴を上においているので、下でミーティングをしているときに靴をどうするか困った。1階に普段はかない靴またはスリッパなどおいておくとよいかも知れない。
引きこもっている人のところの部屋は鍵を開けてもいいのか分からないので、いざというときにどうやったら出てくることができるか、今後、対応を考えていきたい。
今後、高校の中に入る練習もしてみたい。中に入ってからどこに行けばよいか、知っておく必要がある。
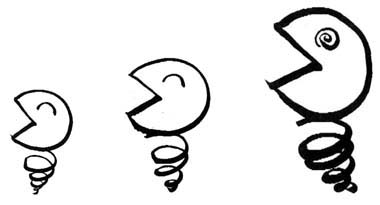
各共同住居からの避難訓練
GHぴあ・おざき荘からの通常期避難訓練:東町地区
GHぴあ・おざき荘は浦河赤十字病院に近く、しばしば退院にむけて外泊訓練が行われている住居である。退院促進支援事業において地域生活の活動拠点となり、入居者であるピアサポーターが彼らの応援に活躍している。
今年度は通常期、冬期ともに避難訓練を実施したが、いずれも退院準備のため外泊中のメンバーがピアサポーターとともに参加した。

a)事前準備
平成15年の地震では浦河赤十字病院へ避難しようとしたメンバーもいたため、おざき荘では、津波浸水による孤立を避け、安全に過ごす場所として、東町第5自治会が管理する「ふれあい会館」が避難先であることを確認した。そして4分以内に10m以上の高さまで避難すること、おざき荘の位置、高さ、避難先・ふれあい会館の位置と安全な避難経路を確認し、自治会から許可をいただいて避難訓練を実施した。
事前ミーティングでは、4丁目ぶらぶらざからの通常期避難訓練に参加したメンバーから、日中活動の場所からの避難経路がわかったので、今度は住居からの避難経路を知りたいという発言があった。
b)避難訓練
9月26日(水)16:00~
参加人数11名:おざき荘入居者7名、べてるスタッフ3名、国リハ1名
住居ミーティング中に、十勝沖地震発生に伴う津波浸水警報が発令されたという想定で避難訓練を開始した。避難訓練では、居間の扉を開ける人など役割を決め、カウントダウンにより地震発生とした。
c)振り返り
ドアを開けること、玄関を出たらどの方向に逃げるのか分からず戸惑った。
一度やってみると、どこに避難すればよいか分かる。何度も繰り返しやるといい。
GHピア・おざき荘からの冬期避難訓練
a)事前準備
雪が残っているため事前にメンバーと国リハスタッフが避難経路を確認し、DAISY版避難マニュアルを作成した。舗道には氷が張っていて滑りやすいので注意する旨、メンバーから報告された。
b)避難訓練
1月30日(水)15:30~
冬期避難訓練では各居室に在室中に地震発生という想定で訓練を行った。避難には、レインボーハウスの防災リュックとアルミシートを試用した。すでに防災グッズを準備していたメンバーもおり、その防災グッズを用いて避難した。避難訓練後には、非常食を参加者で試食しながら振り返りを行った。
参加人数10名:ピア・おざき荘入居者7名、べてるスタッフ2名、国リハ1名

c)振り返り
通りに出る際、逆方向へ曲がってしまったメンバーがいたので声をかけた。けれども帰り道に自分が歩道凍結のため転びそうになり、スタッフに助けられた。気をつけたい。
避難訓練に参加できてよかった。
夜の避難訓練ができてよかった。
しおさい荘からの通常期避難訓練:東町うしお地区
しおさい荘から浦河高校まで避難するためには、川を渡らなければならならず、津波や鉄砲水に襲われる非常に危険なルートを進まなければならない。そのため、夏期避難訓練では土地を所有されている方の許可を得て、山側に逃げる避難経路による避難訓練を行った。
a)事前準備
8月27日、山道を登るため、通り道を確保すべく、土地の所有者の方と一緒に草刈をしながら経路を確認した。個人の所有地であるが、いざというときにはしおさい荘のメンバーが上がってもよいという許可をいただいた。
b)避難訓練
9月28日14時00分~
10月4日14時00分~
再び所有者の方の許可を得て、所有者の方とともに避難訓練を行った。直前までの降雨のため、足下が滑りやすいことに注意すると確認しあった。避難訓練に参加できなかったメンバーは、翌週、参加メンバーとともに自主的に避難訓練を行った。これには、通常の住居ミーティングよりはるかに多いメンバーが参加した。いずれの避難訓練でも全員が3分30秒で標高10mの高さまで登ることができた。
参加人数のべ12名:しおさい荘入居者9名、国リハ2名
c)振り返り
【よかった点】
山道を通って逃げられるとわかってよかった。
【さらによくする点】
眠っている人と一緒に全員安全に避難するにはどうしたらよいか。鐘を鳴らしたり、大声を出したりするなど、考えなくてはならない。
夜の避難は道や雨のとき滑るのかもしれないので、気をつけたい。
フラワーハイツ・ひかりからの通常期避難訓練:東町うしお地区
a)事前準備
DAISYチームのメンバーが、ATDOスタッフの指導を受けながらフラワーハイツから浦河高校までの避難マニュアルを作成した。避難経路には車道脇を進む道と住宅の間を抜ける近道があったが、事前確認により、住宅の間にある近道は、雨上がりにはぬかるんでいて歩きにくく狭いことが分かり、地震直後は危険だろうと推測した。
b)避難訓練
10月30日(火)17時00分~
住居ミーティング中に、浦河沖等を震源とする地震により津波警報が発令されたという設定で、住居から避難場所(浦河高校)への避難訓練を行った。前日雨が降ったため、避難場所へ向かう往路は道路を通り、復路にわき道(泥道)を通った。話しながら、笑いながらだが、信号待ちの時間を除いて正味4分30秒で浦河高校校門前に到着した。
参加人数11名:フラワーハイツ入居者4名、ひかり入居者3名 応援団1名、スタッフ3名、国リハ3名
c)振り返り
【よかった点】
幻聴さんの声がうるさくてもしっかりDAISYを見ることができてよかった。
どこに行けばみんなに会えることがわかってよかった。
【さらに良くする点】
住居にいたけれども参加できなかった人が3名いた。幻聴で途中で避難するのをやめてしまった人もいた。(Tシャツの上にジャンバーを着た後にも「マメ幻聴」のために部屋に入ってしまった人、人が多いから行けないという人、直前でやめてしまった人)。避難場所に着いてからも大勢の人がいるわけなので、幻聴に対しての対応、避難先で病気とどうやって付き合っていくか考えたい。
浦河高校の2階/3階への上がり方を知りたい。
浦河高校への依頼を準備していければいいと思う。
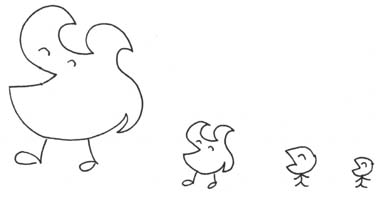
グループホームべてるの家、駅前ハイツからの通常期避難訓練:昌平町地区
グループホームべてるの家
べてるの家は標高10m付近に位置する。そこで津波警報発令を受けて避難するとき、より海側から避難して来る高齢者・障害者の手助けをしようという案が出され、地震発生後1分間は周囲の状況を確かめたり、手助けする時間とし、その後避難することを、もっとも理想的な目標とした。

駅前ハウス
駅前ハウスは津波浸水予想区域には入ってないが、避難先に行く途中で地崩れ危険区域を通ることになる。このため測候所のデータの読み方や地盤が緩んでいる兆候の見つけ方、避難するときに留意すべき点を考えていこうと話し合った。また大判地図を玄関前の廊下に貼り、いつでも見られるようにした。
9月15日、2つの住居からメンバーが築地地区の図上訓練へ参加し、避難経路と危険区域についての確認を行った。今後は火災、土砂災害をも想定した避難計画を立て、住居からの避難訓練を行うことがの課題である。


