IV. この取り組みからみえてきたこと
1.メンバーが参加する避難訓練のステップ
各住居、活動拠点の防災隊長を決め、その人を中心に避難訓練の時期や場所、防災グッズについて日常のミーティングで繰り返し相談すると、避難訓練もSSTや当事者研究のように、メンバーが自分達の身体で学習し、避難訓練をより良く工夫しやすいことがわかった。DAISY版避難マニュアルの作成でも、DAISYチームと一緒に避難経路の下見に行き、マニュアルをつくってもらうと、より避難するときの注意事項が分かりやすい。避難訓練の日と時間をミーティングで決めたら、以下の順番で避難訓練を進めると良い。
【避難訓練当日の進め方】
①その日の設定・テーマを確認する(SST方式)
②防災みなみ体操で体をほぐす
③地図で避難経路を確認する
④先頭・最後・車椅子を押す人・防災グッズを運ぶ人・懐中電灯やトランシーバーをもつ人など役割を確認する
⑤合図と共に避難開始
⑥避難中はできるだけ記録をとる(ビデオ・写真)
⑦10メートルの高さに達する時間を計る
⑧避難場所で集合し、集合写真をとる
⑨戻って振り返りをする:よかった点、苦労した点、もっとよくする点
2.防災を通じて強まった、協力合う雰囲気
本年度の防災事業を通じて、防災グッズを皆で考える、一緒に避難するといった体験を重ねて、メンバーやスタッフの間で絆がさらに深まったり確認できたりした。べてるの住居では、働いているメンバー、デイケアに通っているメンバー、引きこもっているメンバーなどさまざまな人が暮らしており、一人一人がそれぞれのリズムで生活している。時には協力し合うことがなかなか出来ないこともある。防災事業は避難方法などを住居ミーティングで考え、振り返りをするので、今まで以上に、一人ひとりの苦労を伝える機会となった。
特に共通の課題として、防災への取り組みを通じて、地震や津波災害に関連した漠然と気になっていた不安(「いざという時幻聴さんがやってきてパニックになってしまうかもしれない」、「眠剤がないと眠れないけど、災害時に起きられなかったらどうしよう」など)を、みんなで考える共通のテーマとして再確認することができた。
3.町内の人たちとのきずなを深められた
浦河町民にとって防災対策は思った以上に共通の関心事となっており、自治会/町役場と一緒に避難訓練に参加したときは思った以所に共通の課題を持っていることに気づいた。そして、当たり前のことだが、地元の方は、具体的な建物の建て方や町内の地盤の特性をよく把握していて、べてるも今後学習していく必要があると思った。
同じように、防災をキーワードに、はまなす学園・浦河向陽園とのつながりをはじめることができた。
4.町外の人との防災対策ノウハウの交換
浜中町、美波町との交流がはじめられ、お互い防災対策の良さを学びあうことで、自分たちの防災対策が充実していくことを実感した。


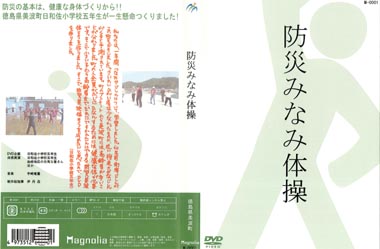 (
(