第2章 「活動の経過・参考資料」
(3)ピアサポーターからの報告
ピアサポーター感想(かんそう) (知的障(ちてきしょう)がい者(しゃ)入所施設訪問(にゅうしょしせつほうもん))
今回(こんかい)、施設(しせつ)にいって よかったと思(おも)う。いろんな人(ひと)に であえたのが よかった。
入所施設(にゅうしょしせつ)にいる人(ひと)は、グループホーム(ぐるーぷほーむ)や地域(ちいき)で生活(せいかつ) したらいいと思(おも)う。ひるまは、ちいきでしごとして、しごとおわって、家(いえ)やグループホーム(ぐるーぷほーむ)にかえって、じぶんのすきな時間(じかん)をすごせたらいいと思(おも)います。
僕(ぼく)も、昔(むかし) 入所施設(にゅうしょしせつ) にいたことがありました。入所施設(にゅうしょしせつ)にはいるときに、親(おや)とはなれるのはさびしかった。なんで、ぼくは施設(しせつ)に はいらなあかんのかわからなかった。でも、しょうがないと思(おも)って入所施設(にゅうしょしせつ)に行(い)った。お兄(にい)さんが探(さが)してくれたから、行(い)くしかなかった。
施設(しせつ)にいる時(とき)、職員(しょくいん)さんに「グループホーム(ぐるーぷほーむ)があるよ。1回(いっかい)体験 (たいけん) してみない。」と誘(さそ)われた。はじめは、どんなところか分(わ)からなかったので不安(ふあん)でした。でも、体験(たいけん)してみると自由(じゆう)に過(すご)せたり、テレビ(てれび)も見(み)れたりしたので、グループホーム(ぐるーぷほーむ)がいいなと思(おも)って、グループホーム(ぐるーぷほーむ)に行(い)く事(こと)に決(き)めました。
グループホーム(ぐるーぷほーむ)に行(い)ってすぐは、不安(ふあん)がいっぱいでした。分(わ)からないこともたくさんありました。寝(ね)る時間(じかん)も自分(じぶん)で決(き)めていいと言(い)われて、何時(いつ)に寝(ね)たらいいのか困(こま)りました。でも、だんだんなれてきました。いまは、グループホーム(ぐるーぷほーむ)がさいこうとおもっています。
ぼくは、今(いま)結婚(けっこん)して奥(おく)さんと2人で暮(く)らしています。
施設(しせつ)では、結婚(けっこん)のはなしをたくさんきかれました。結婚(けっこん)はかんたんにできるものではないです。おたがい、好(す)き同士( どうし)になって、つきあって、デートしたりして、やっと出来(でき)ます。そのことも話(はな )しました。みんなすごくきょうみを持(も)っていたなと思(おも)います。
障(しょう)がいが重(おも)くても地域(ちいき)でくらせるとおもいます。むかし、僕(ぼく)が施設(しせつ)にいた時(とき)に同(おな)じ部屋(へや)だった障(しょう)がいの重(おも)い人(ひと)が、いまパンジー(ぱんじー)の グループホーム(ぐるーぷほーむ)で暮(く)らしています。そのひとは、自分(じぶん)で思(おも)っていることは伝(つた)えられないけど、いまは楽(たの)しそうにしています。
好(す)きな事(こと) ができたり、自由(じゆう)にできたほうがいいとおもいます。
施設(しせつ)の人(ひと)たちも、ちいきで生活(せいかつ)できたらいいと思(おも)います。最初(さいしょ)は不安(ふあん)やけど、なれたら大丈夫(だいじょうぶ)とおもいます。ぼくも、これからも応援(おうえん)していきたいと思(おも)います。
(4) 派遣調整事業所からの報告
モデル施設へのピアサポーター派遣について
知的障がい者入所施設派遣事業所 担当者
<取組みの概要>
知的障がい者入所施設に、既に入所施設からグループホーム・ケアホーム(以下ホームとする)を利用した地域生活に移行した経験をもつピアサポーター2名を、計4回派遣し、施設利用者に地域での生活の様子について紹介したり、ホームや日中活動の場所を見学する取組みを行い、施設利用者が地域での生活を知る機会とした。また、参加した施設利用者が自らの施設での生活についてあらためて振り返り、一人ひとりが将来どのような生活をしたいか、それを実現するにはどのようなことが難しいと感じているかを考える機会をつくり、同じ立場の仲間たちと、自らの気持ちを話し合い、気持ちを共有し合うことにより、今後の自らの生活を考えるきっかけとした。
<取組みの内容>
| 内容 | |
| 1回目 | ・入所施設での生活を振り返る(施設で楽しかったこと、いやだったこと) ・ホームの生活紹介(スライド) ・日中活動の紹介(スライド) ・質疑応答 |
|---|---|
| 2回目 | ・ホームの見学と説明 |
| 3回目 | ・日中活動場所(生活介護事業所)見学と説明。 ・活動体験 |
| 4回目 | ・感想 ・将来の自分の暮らしについて |
<経過>
◇スライド等を活用した説明
派遣されたピアサポーターは2名とも、以前にこの施設に入所していた方であったため、参加した施設利用者には馴染みが深く、リラックスした雰囲気であった。
1 回目、ピアサポーターから、以前の施設に入所していたときの経験を思い出して話し、そこから参加者自身の現在の施設内での生活で「楽しいこと」「ちょっといやなこと」について話す機会をつくった。自分の生活をあらためて振り返って、その思いを遠慮なく話す機会はとても新鮮だったようで、日々の生活で楽しみに思っている活動や、大人数で生活する施設内の騒々しさ、気が合わない人との人間関係や、外出の機会が少ないことなど、それぞれの思いを一生懸命に語る様子があった。
その後、ピアサポーターが暮らすホームの様子や、日中活動の場の様子など、写真をまじえたスライドを活用して紹介をし、参加者は興味をもってスライドを見る様子がみられた。ホームには一人部屋があることや、世話人さんが美味しいごはんを作ってくれることなど、「うらやましい」との声がある一方で、「病気になったらどうするのか」「夜が心細い」など、不安に思う言葉もきかれた。また、ホームで暮らしたいと思うが、きょうだい(家族)が反対しているなど、現実に目を向けた発言もあった。
◇見学(ホーム、生活介護事業所)
ピアサポーターが生活しているホームと、日中利用している生活介護事業所の見学を行った。
施設職員が送迎に協力してくれて、移動もスムーズに行えた。
2回目のホームの見学では、ピアサポーターは、ホームの毎日の生活で気に入っていることなど、実際に生活している人の視点で案内してくれて、施設利用者も興味を持った様子だった。ホームは、鳥のさえずりが聞こえるほどにとても静かで、参加者も「すごく静か」と口々に話し、実際に見学してみて初めて入所施設との違いを実感したようだった。ホームの個室に、好きな雑誌の付録の人形をとてもたくさん並べている人もおり、「ホームは一人部屋だから怒られないんやなあ」と話す人もいた。また、歩行が不自由で玄関で躊躇する人もいたが、「手すりがあったらいけると思う」など話し、具体的に「自分が生活するとしたら・・」ということをイメージする様子もあった。また、「こんなところに住みたいなあ」と自分の生活としてホームを考えるような様子もみられた。
3回目の日中活動の場である生活介護事業所の見学では、この施設から徒歩10 分ほどの近さだが、実際に見るのは初めてとのことだった。生活介護事業所の利用者は、この施設からホームに移行した方がほとんどで、懐かしい人と久しぶりに対面して喜び合う様子がみられた。ピアサ ポーターから事業所内を案内してもらい、その後、和紙で作った封筒に絵を描いたりシールを貼ったりして、オリジナル封筒を作る活動を、説明してもらいながら一緒に体験した。建物を見るだけではなく、活動を一緒に体験することで事業所の楽しい雰囲気を味わうことができ、「またここに来たい」と話す人もいた。
参加者の感想とまとめ(思ったことを自由に話す)
最終回に、見学してみた感想をきくと「よかった」「また行きたい」など、今回の取組みがよい きっかけとなり、今後につながっていきそうな感じをうけた。また、「夜一人で寝るのが心配」など、具体的に生活をイメージして不安な気持ちを話す人もおり、ピアサポーターから「わたしも最初は不安でした」と同じような気持ちだったことを話していた。
そして、実際にホームで暮らしてみたいですか?と問いかけると、ホームに暮らしたいが、きょうだいなどの家族が反対しているという話がでてきた。これまでに「ホームで暮らしたい」と話して反対されたことのある人もいれば、聞いたことはなくても「このままこの施設にいてほしいと思っていると思う」と家族の思いを敏感に感じている人もいた。ピアサポーターの2人は、ホームへ移行したときに特に家族の反対はなかったが、ホームに引っ越す前に、家族にホームの建物をみてもらったり世話人に会ってもらったりして、安心したのではないかと経験を話した。家族が反対しているのはなぜだと思いますか?と問いかけると「私が何もできないと思っている」「ホームのことをよく知らないと思う」という言葉があり、家族にもホームを見学する機会があればよいのに、と話す人もいた。ピアサポーターも「家族の意見もきかないとだめなんやなあ」と新たな課題を感じたようだった。
<まとめと今後の課題>
◇今回の取り組みでよかったこと
| ・ | 写真を多く用いたスライドを活用した説明で、興味を持って説明をきいてもらうことができ、地域の生活をもっと知りたい(見学に参加したい)という目的意識をもつことができた。 |
| ・ | 1回目の説明があったため、見学が単なる「外出の機会」ではなく、「地域生活を知る」という目的を持って参加することができた。 |
| ・ | 見学をすることにより、実際に地域で生活するイメージをもつことができた。 |
| ・ | 「自分の生活」という視点をもち、入所施設での生活もふまえながら今後の自分の生活について考えるきっかけとなった。 |
| ・ | ピアサポーターや、入所施設の仲間と一緒に参加することにより、周りの人と一緒に気持ちを共有しながら、自分の思いを確認することができた。 |
| ・ | 家族の理解など、希望する地域生活を実現するためにどんなことが必要であるかを、施設利用者自身も考える機会とすることができた。 |
| ・ | 施設職員にとっても、施設でのいやなことや、地域移行についての思いを施設利用者が予想以上に具体的に考えていることや、家族の思いを非常に敏感に感じ取っていることに気づくよい機会となった。 |
◇今後の課題
| ・ | 見学の人数の都合などから、限られた人数の参加者となった。今回のような取組みをさらに多くの方が参加できるように回数を重ねるなど、広める必要がある。 |
| ・ | 今回参加した施設利用者の中には、実際にホームへの移行を希望し、家族への説明や体験利用など、移行のための支援を必要としている人もいる。今回の取組みをきっかけに、次は個別に取組みを深めていく必要のあるケースもあると考えられ、そのための支援策を検討していく必要がある。 |
| ・ | 今回の取組みで、特に家族の反対によって、地域移行がすすまないケースが多くあることが実感された。家族に対しても、地域生活について知ってもらう取組みが今後必要であると考えられる。 |
モデル施設へのピアサポーター派遣について
身体障がい者入所施設派遣事業所 担当者
今回の事業は、昨年度に出た「大阪府地域移行推進指針」にも見られるように、地域移行の意思形成・意向確認の部分で、地域で生活している障がい者が体験をもとに相談を行うことが有効であり、ピアカウンセラーを活用した入所者への働きかけと派遣の取り組みが今後の課題とされた部分を、実践・検証するために行った。
身体障がい者については、身体障がい者入所施設(療護施設)3施設にそれぞれ5回(内1施設については3回)の派遣を行った。1回あたりの実施時間は約2時間。なお今回は「ピアカウンセラー」に限定せず、地域移行の実体験をもった者などにまで枠を広げる意味あいもあり、「ピアサポーター」として障がい当事者が施設におもむくこととした。
実際の派遣は、概ねどの施設も、1~2回目にビデオ・スライドなどを利用した地域生活の紹介、および実際に地域生活をしている障がい当事者からの説明、3~4回目に実際に地域生活の様子をみるための見学会、最後に見学を含め、まとめの意見交換、という流れで行った。
地域生活の紹介については、自らの体験を話すことによって、関心・興味を引くことができた。またビデオなどの映像や画像を使うことにより、さらに分かりやすく説得力のあるものになった。しかし体験談や映像等によるアプローチは、入所者にとって「受け身」的な素材でもあり、実際に自分のこととしてイメージをする場合、それではまだ弱い面もあったように見受けられる。
見学会については、今回の目的に即して言うと、非常に大きな効果をあげたと言える。
実際に施設から出て、障がい当事者の集まる日中活動の場を見ること、生活している住宅を見ること、何よりもその場の空気・雰囲気に触れることで、自分のこととしてイメージできる部分が大きくなった。施設の空気の中で行うのではなく、実際に地域を感じる効果だと思われる。結果、見学会によって施設入所者から出される感想は、施設で行った体験談・映像の時よりも、生々しいものとなる。
それは「やってみたい」という肯定的なものから、「自分の障がいでは難しい」などのネガティブなものもあるが、いずれにせよ、自分の希望・期待や不安・懸念が大きくなって、自らの言葉で語り始めたということであると思われる。
今回の事業で確認できたこととして、
・ピアサポーターによる入所者への働きかけは、地域移行の動機付けの際に非常に効果的であった。
・実際に入所者が地域生活の様子を見学することで、イメージがふくらみ、また課題についても具体的に意識できる(地域への見学では、送迎体制等で希望者を制限せざるを得なく、事業終了後に見学を実施した施設もあった)。
1点目であるが、もし地域移行の説明が、経験者でもない健常者の職員等からの一般的な話に終始した場合、より他人事としての情報でしかなかったであろう。ピアサポーターの体験をもとにした説明であるからこそ、入所者にも伝わるものがあったと考えられる。
2点目は当初から一定予想されたことではあったが、予想以上に大きな効果があった。地域移行について、積極的・消極的いずれの意見も、それだけ自分の中にある意識をゆさぶったということである。
本事業を通して施設と地域(団体)との恒常的なつながりを持っていく契機となった。また、地域移行を支援する施設職員の認識がより深まったのではないかと思われる。
今回はここまでの取り組みであったが、見学会での意見・感想について、フォローする場が必要であったと感じる。自分には難しいという意見の中には、医療的ケアの問題や、住宅の構造の問題なども見受けられたが、本来地域の生活は、そのような環境を調整して行っていくものである。決して環境に自分を合わせて生活をするのではない。
その辺りをピアの立場で相談し(ここでもまたピアの威力が発揮されるところである)、不安を一つずつ取り除いていく必要がある。今回の見学は日中活動・住宅と、ともに1カ所だけになっているので、複数の場の見学をすることや、また、入所施設の生活は自分を環境に合わせる部分も大きいと考えられ、そうではなく、自分に合わせた環境を、創っていくという方向に意識を向けていくことを、伝えていく必要がある。
今回の5回という中での課題として、細かなことをあげれば、ピアサポーターによる体験談の伝え方、映像・画像の使い方を更に研究していくこと、また素材となる映像等について充実させていくこと。また今回は短期間の実施であったため、調整が非常に難しく結果的に3回の派遣となった施設については、5回のイメージのプログラムのまま進めたために、充分に伝えきることができなかったことなどから、実施期間と回数・内容の更なる研究も必要と思われる。
さらに、大きな課題としては、今回の結果を活かし次に何を作っていくかということである。基本的にこの取り組みを充実させていくこと、また次のステップとして、施設・地域の支援センター・自治体が連係して、地域移行が進んでいくような枠組みやパターンを作っていくことなどがあげられる。
障害者権利条約の批准が間近であると言われている。第 19 条には「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域生活で生活する平等の権利を認めるもの」とある。施設入所者に、平等の選択の機会がある、ということは、単なる情報提供で終わるものではない。今回、入所者の中から「本当は地域で生活したいのだが・・」という思いがいくつか出たが、それを実現させていく仕組みが必要である。この試行事業が、障がい者の権利を護っていくための、大きなきっかけになることを期待している。
(5)受け入れ施設からの報告
ピアサポーター派遣モデル事業を終えて~受け入れ施設から~
身体障がい者療護施設 相談支援専門員
今回「地域生活移行支援ピアカウンセリング検討委員会」の一員として、この事業の受け入れ施設側で参加させて頂き、当園の方々と一緒に「施設入所者の地域移行」という問題を正面から考える機会に恵まれた。
「ピアサポーター」を派遣して頂き、4 回(今回の事業以外に、別途今回事業同様の地域移行研修を受けた)に亘っての勉強会や、「ピアサポーター」が関係する事業所等のご協力でグループホーム見学会を実施した。
当園入所者の中から、この研修会に10 名(延べ19 名)の方々が参加され1,2回目のピアサポーターによる体験談では、「聞いてみよう!見てみよう!たずねて見よう!」と入所者達の前向きな姿勢を当初から感じて、「今までの研修と違うな!!」と話し合い、講演形式とはかなり違いがある事に気づいた。それは、同じ障がい者の目線で具体的に「地域で暮らす」メリット(良いところ)だけではなく、デメリット(困難なところ)を重点的に聞きたいとひとり一人の、「地域で暮らす」イメージがある程度できて来た事である。
3 回目のグループホームへ出向いた見学会では、5 人の参加者から更にかなり具体的な意見も出された。以下はその時の意見を集約したものである。(3ヶ所共通)
1.アットホームな雰囲気で個室である事が最大の魅力だが、全て自己責任で一からのスタートなので人脈のない者にとっては困難なように感じた。
2. 個人の意思は充分反映できるものの、「生活保護」を受給しない限り経済的な負担が大幅に増える可能性があるように思った。(家賃、食費、ヘルパー利用料、医療費等)
3. 障がい者として必要不可欠な介護(支援)体制の不安感は否めない。
4. 各ホームを訪問した結果、ホーム毎の介護体制にバラつきが見られた
(ア) 建物内の単独移動に危険な箇所あり。(EV 横の階段等)
(イ) 廊下が全体的に狭く、電動車椅子では動きにくい。
(ウ) キッチン、風呂等の居住スペースが狭く、自分でする調理や機械浴が困難。
(エ) グループホームを立てる場合に「バリアフリー」の視点がないと、入居者が不便に思う部分が多くなる。
(オ) 最重度の身体障がい者が自立するには、ハード面の充実も必要だと思う。
さらに、今回の取り組み全体を通して以下の意見があった。
①「本来の地域生活(自立)とはどういう事か」をかなり前向きに考えることができた。
② 基本的には、みんな地域(自立)生活をして暮らしたい。今後もこの様な取り組みを継続してほしい。(新しい地域の情報をほしい)
③ 全ての障がい者の地域移行を達成するには、法的な整備を行政にお願いしたい。
(6)知的障がい者入所施設A ピアサポーターと支援者との打ち合わせ資料
ホームのくらしを、施設(しせつ)の人(ひと)につたえよう!
| ◆ 打(う)ち合(あ)わせ◆ ・ 1月(がつ)15月(がつ)(木もく)10:00~ 施設(しせつ)と日中活動(にっちゅうかつどう)の場所(ばしょ)で ・ 1月(がつ)29日(にち)( 木 ) 日中活動(にっちゅうかつどう)の場所(ばしょ)で (支援者(しえんしゃ)がうかがいます) |
| ◆1回目(かいめ) ◆ 1月(がつ)29日(にち) ( 木 ) 1:00~2:30 ・ 施設(しせつ)のくらしをふりかえろう(楽(たの)しかったこと ちょっといやだったこと) →参加者(さんかしゃ)みんなで話(はな)してみよう ・ グループホームのくらしを紹介(しょうかい)しよう(スライドなんかを使(つか)って) ○参加者(さんかしゃ)へアンケート |
| ◆2回目(かいめ)◆ 2月(がつ)12日(にち)( 火 ) 1:00~2:30 ・ グループホームを見学(けんがく)しよう(みんなでおじゃまします) ・ ホームのくらしについて、質問(しつもん)にもこたえてね ○参加者(さんかしゃ)へアンケート |
| ◆3回目(かいめ) ◆ 2月(がつ)26日(にち)( 木 ) 1:00~2:30 ・ 日中活動(にっちゅうかつどう)の場所(ばしょ)を見学(けんがく)しよう ・ 日中活動(にっちゅうかつどう)の場所(ばしょ)やホームのくらしについて知(し)りたいこと(質問(しつもん)に答(こた)えてね) |
| ◆4回目(かいめ)◆3月(がつ)2日(にち) ( 月 ) 1:00~2:30 ・ わたしの今(いま)の気持(きも)ちはどうかな? ☆やってみたいこと<ホームでくらしてみたい?> ☆ちょっと心配(しんぱい)なこと<わたしもホームでくらせるかな?> ・ ☆○○さん、△△さんは、ホームで生活(せいかつ)をはじめるとき、どうでしたか? ○参加者(さんかしゃ)へアンケート |
(7)知的障がい者入所施設A 参加者への配布資料(日程表)
地域(ちいき)での生活(せいかつ)について、いっしょに考(かんが)えてみませんか!

どこで住(す)むか・・・ 誰(だれ)と住(す)むか・・・
日中(にっちゅう)何(なに)をするか・・・ どのような手伝(てつだ)いが必要(ひつよう)か・・・。
実際(じっさい)に、ホームで生活(せいかつ)している皆(みな)さん(ピアサポーター(ぴあさぽーたー)さん)の話(はなし)を聞(き)いたり、住(す) んでいる場所(ばしょ)などを見学(けんがく)してみませんか。
○1回目(かいめ) 1月(がつ)29日(にち)(木(もく))1:00~2:30
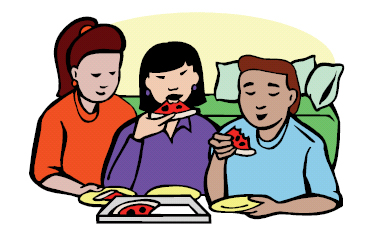
地域(ちいき)での生活(せいかつ)って何(なん)だろう?
園(えん)での生活(せいかつ)を考(かんが)えたり、ピアサポーター(ぴあさぽーたー) さんの話(はなし)を聞(き)いたりしてみましょう。
○2回目(かいめ) 2月(がつ)12日(にち)(火(か))1:00~2:30
ピアサポーター(ぴあさぽーたー) さんが、生活(せいかつ)しているホームを見学(けんがく)してみましょう。
わからないことを、いろいろ聞(き)いてみましょう。
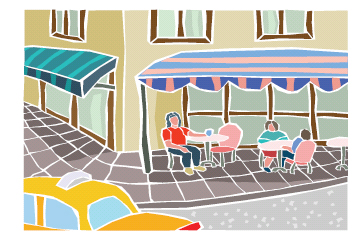
○3回目(かいめ) 2月(がつ)26日(にち)(木(もく))1:00~2:30
ピアサポーター(ぴあさぽーたー)さんが、通(かよ)っているところを見学(けんがく)してみましょう。
○4回目(かいめ) 3月 (がつ)2日(にち) (火(か))1:00~2:30
思(おも)ったことや感(かん)じたことを、いっしょに話(はな)してみましょう。


