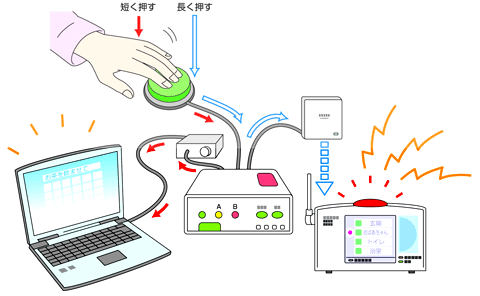A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等
指針にある、意思伝達装置の購入基準や修理基準は以下の通りになっています。
<購入基準>
| 重度障害者用意思伝達装置 | 金額 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| ソフトウェアが組み込まれた専用機器およびプリンタで構成されたもの、もしくは生体現象(脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。 | 450,000円 | 5年 |
<修理基準>
| 金額 | |
|---|---|
| 本体修理 | 50,000円 |
| 固定台(アーム式またはテーブル置き式)交換 |
30,000円 |
| 入力装置固定具交換 | 30,000円 |
| 呼び鈴交換 | 20,000円 |
| 呼び鈴分岐装置交換 | 20,000円 |
| 接点式入力装置(スイッチ)交換 | 10,000円 |
| 帯電式入力装置(スイッチ)交換 |
40,000円 |
| タッチ式加算 |
(10,000円) |
| ピンタッチ式先端部加算 | ( 6,300円) |
| 筋電式入力装置(スイッチ)交換 |
80,000円 |
| 光電式入力装置(スイッチ)交換 |
50,000円 |
| 呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換 |
35,000円 |
| 圧電素子式入力装置(スイッチ)交換 | 38,000円 |
(出展:平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号 最終改正:平成20年3月31日)
【参考:修理基準の解説】
重度障害者用意思伝達装置の修理基準には、6種類の異なるスイッチと、本体及びスイッチの付属品が定められています。それぞれの項目について簡単に説明します。
スイッチは利用者の身体機能に合わせて選ぶことができます。また、特に進行性の疾患の場合、身体機能の変化に合わせて、その時々にもっとも使いやすいものに換えていくことが可能です。同じスイッチでも,色々な身体部位で操作することが可能です。
⇒ 具体的な使用例は、「操作スイッチの適合事例(別冊、ホームページ)」をご覧下さい。
(1)接点式入力装置
接点式は、押しボタンスイッチのように、荷重をかけて機械的な接点を閉じる操作をする入力装置で、種類も形状も豊富に市販されています。操作が分りやすく、クリック音やクリック感などの操作感があるので入力したことを確認できます(図1)。手だけでなく足や頬など色々な身体部位で操作することができます。小さな力、小さな動きで操作できるものもありますが、意図しない誤入力も入りやすく、スイッチの反発力が少ないため、押しっぱなしになることがあるので注意します。一般的に進行性の神経筋疾患等ではその初期段階に用いられます。
最も多く使われている種類の入力装置です。
図1 接点式入力装置
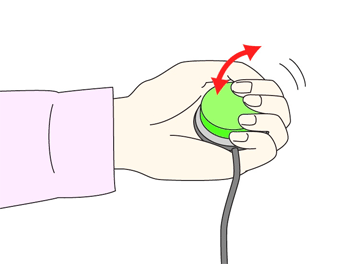
(2)帯電式入力装置
帯電式は、一部のエレベータのスイッチにも使われている、いわゆるタッチセンサです。身体の静電気に反応する(静電容量の変化を検知する)入力装置なので、荷重をかける必要がなく、操作部位に力がなくても操作できます(図2)。神経筋疾患等のかなり進行した段階でも使用可能です。ただし、触った感覚だけでクリック感がないので、正しく操作していることを確認するため、表示ランプ、音や画面で操作している本人に知らせる(フィードバックする)必要があります。
図2 帯電式入力装置

(3)筋電式入力装置
筋電式は腕やあごなどの大きな筋肉が収縮するときに発生する筋電(EMG)の強弱を、皮膚表面に貼り付けた電極で検知する入力装置です(図3)。あごをかみ締める、肩に力を入れるなど、必ずしも巧緻性の高い動作は必要ないことが長所です。しかし、有線のセンサを身体に装着することが必要なので、鬱陶しさや煩わしさ、ベッドや車いすに引っかかって断線する、線が動くと雑音が入るので誤動作する、などのリスクがあります。電極の貼り付け部分のかぶれにも注意が必要です。
図3 筋電式入力装置
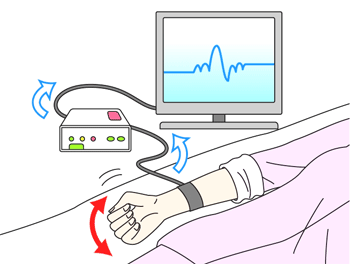
(4)光電式入力装置
光電式は、対象物に光を当てて、その反射の強さを検知する入力装置です。スイッチにタッチしなくても設定した距離まで近づけば反応するので、額やまぶたなど、接触が煩わしい操作部位でも使用できます(図4)。感度が高く、操作部位のわずかな動きを検知することができます。ただし、接触の感覚がないので、操作感もありません。(2)の帯電式と同様のフィードバックが必要です。また、目の周りで使用する際には、直接光が目に入ると眩しいので、設置位置に注意します。
図4 光電式入力装置
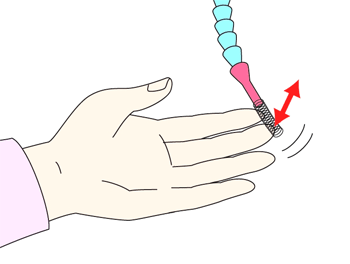
(5)呼気式(吸気式)入力装置
呼気(吸気)式は、主に高位の頸髄損傷者がよく使用する、チューブやストローを通して呼気圧(吸気圧)を検知する入力装置で、同じスイッチで「吹く」と「吸う」の2つの入力まで可能です(図5)。操作がわかりやすく、圧をかけることによって自分の口元にも圧がかかり、操作感として伝わります。先端のチューブやストローを一度離しても、くわえ直せるように設置位置を調整します。チューブにたまる唾液や水滴は、放置すると不衛生で、かつ入力装置の寿命を縮めることになるので、定期的な洗浄と乾燥が必要です。
図5 呼気式(吸気式)入力装置
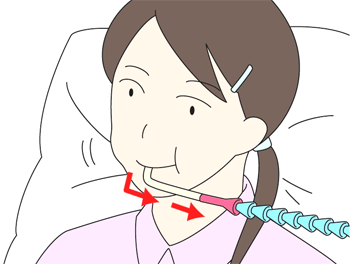
(6)圧電式入力装置
圧電素子式は、身体の動きによってピエゾ素子と呼ばれる薄板がたわみ、発生した電圧を検知する装置です。わずかな力でもたわみが生じるため、操作部位のわずかな動きを捉えることができます(図6)。手、足、顔など様々な部位で使用できますが、有線のセンサを身体に貼り付けるため、筋電式と同様の注意が必要です。この入力装置は、ピエゾ素子がたわんだ瞬間のみスイッチが入るので、(10)で後述する呼び鈴分岐装置の動作に必要な長押しができないので、設定時間内に決められた回数の短い入力を行うなど他の方法が必要です。
図6 圧電式入力装置
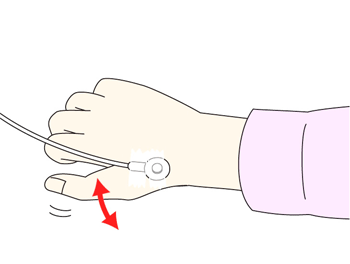
(7)固定台:アーム式・テーブル置き式
固定台は、意思伝達装置の本体(画面)を使用場所に、本人が見やすいように固定するための台です。車いす上で使用する場合には、画面の高さを目の高さに合わせ、ベッド上での使用では、ベッドの高さや角度に合わせて、画面を傾斜させて支える必要があります。テーブル置き式は主にノートパソコンをベースにした意思伝達装置を一定の画面角度に固定する台です(図7-1)。構造が簡単で取り扱いやすい反面、アーム式に比べて固定位置の自由度が少ない特徴があります。一方、アーム式はオーバーテーブルやサイドレールにクランプで締め付けたアームに意思伝達装置の本体を固定します(図7-2)。体位交換で身体の向きが変わる場合はアーム式の方が画面を見やすい位置に固定できます。自立式でキャスター移動が可能なスタンド型の固定台もあります(図7-3)。クランプなどの固定部分は徐々に緩んでくるので、時々締めなおさないと位置がずれてきます。
図7-1 固定台:テーブル置き式
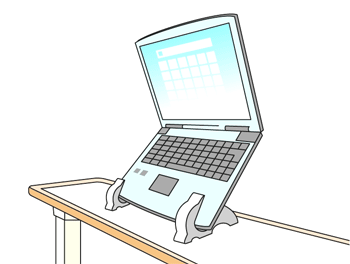
図7-2 固定台:アーム式
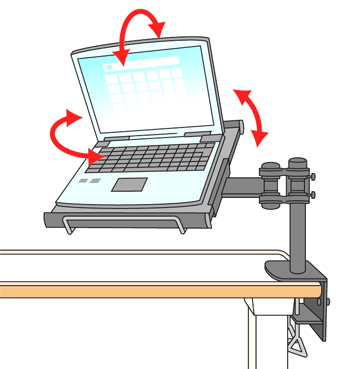
図7-3 固定台:自立式
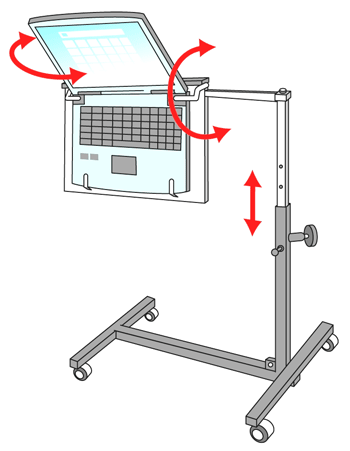
図8 入力装置固定具
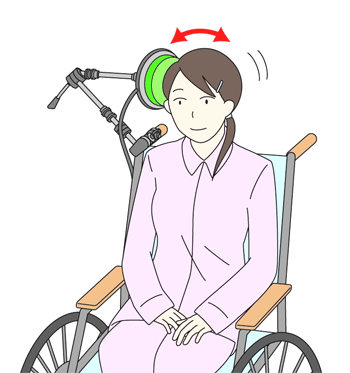
(8)入力装置固定具
入力装置固定具は、入力装置を本人の操作しやすい位置に固定するための道具です。(7)のアーム式固定台のように、車いすやベッド周りに固定して、入力装置の位置を手・足・頭などの操作部位の近くに固定できます(図8)。ノブボルトを回してアームの位置を固定するものや、蛇腹を曲げて位置決めするものなどがあります。入力装置は固定具の先端にねじ止めするか、両面テープや面ファスナー(ベルクロ、マジックテープ等)で固定します。クランプやノブボルトは(7)と同様に時々締めなおす必要があります。
(9)呼び鈴
呼び鈴は、病院病棟のナースコールのようなもので、家庭や施設で人を呼ぶためのベルです。同じ部屋にいても、意思伝達装置を使う方は、声を出して人を呼べないため、コミュニケーションをはじめる前に、相手の注意を引きつける必要があります。また、離れたところにいる家族や介護スタッフを呼ぶときにも呼び鈴が必要になります(図9)。呼び鈴には有線・無線、電池式・充電池式・AC電源式などの種類があります。一般に無線で、充電池式のものは設置場所を選ばないなどの点で使い勝手が優れています。ただし、無線は、建物の構造によって電波が届きにくく、うまく動作しない場合があるので注意が必要です。
(10) 呼び鈴分岐装置
呼び鈴分岐装置は、意思伝達装置を操作する入力装置で呼び鈴も操作できるようにするための切替装置です。入力装置を通常よりかなり長く押す、あるいは短い時間に何回も入力すると意思伝達装置から呼び鈴に操作が切り替わります(図10)。入力装置の種類によっては、連続した長い入力が得られないもの(例えば(6)の圧電式入力装置)があるので注意します。その場合は、本人の身体機能的に可能であれば、設定時間内に決められた回数の短い入力を行って操作します。
図9 呼び鈴
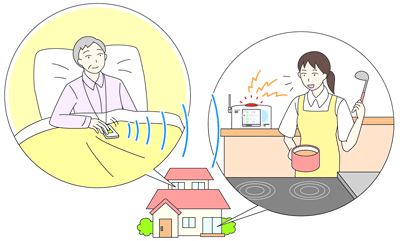
図10 呼び鈴分岐装置