⑧聴覚障害学生の在籍調査
東京手話通訳等派遣センターはI大学医学部に1年6ヶ月にわたり手話通訳の派遣を行った。調査者は平成21年2月に東京手話通訳等派遣センターを訪問し、担当職員3名に聞き取り調査を行った。東京手話通訳等派遣センターよりI大学への手話通訳派遣についての報告資料を提出していただいた(報告資料⑧-1)
医学部の臨床実習における情報保障は、東京手話通訳等派遣センターとして初めてのことであり、これまでのような大学の講義における情報保障と同様な体制では対応することが困難であったが、さまざまな問題に直面しながらも、それらの問題を学生、大学、派遣センター、通訳者が連携して解決していったことを知ることができた。
まず、医学という非常に専門的な分野の通訳を担える人材の確保という問題があった。これに対しては、医療関係の有資格者の通訳者を4名確保し、派遣センター職員2名と合わせて対応したとのことだが、当然のことながら、医療関係の有資格者の手話通訳者はその資格関係の仕事に就いている人が多く、仕事との調整が難しかったとの報告があった。今後増えるであろう、医療系高等教育機関での情報保障のニーズに対応するためには、医療関係の有資格者に手話通訳の資格を持ってもらうのも1つの方法であるが、仕事の関係上柔軟な対応が困難なことが多いので、手話通訳者に専門知識を習得してもらう取り組みも必要ではないかと感じた。
ただし、報告によると、臨床実習の現場で看護師資格を有していない手話通訳者が通訳する場合は、患者の承諾書が必要になるなど、制度上の支障があるとのことであった。このままでは、専門知識を有した手話通訳者を養成したとしても、臨床実習の現場の通訳には派遣ができないということも予想される。これについては、手話通訳者の業務の意味に対する理解を求め、ある一定の研修を受けた手話通訳者は承諾書なしでも臨床実習の現場で通訳を行うことができるようにする取り組みが必要ではないかと思われる。
また、この報告を聞いて疑問に思ったことであるが、聴覚障害者が実際に医師となって診療を行う時に、看護師有資格者の手話通訳者でないと、患者の承諾がない限り診療行為ができないということはないのだろうか。もし、そうだとすると、この条件を有する手話通訳者は少ないため、結果的に聴覚障害者は診療行為ができなくなるという事態が生じる恐れがある。そのようなことはないのかどうか、確認が必要であろう。
次に、臨床実習は普段の医療の場面と同じように、患者と医師や看護師とのコミュニケーションがあるのだが、通常のように診療を受ける側の聴覚障害者の患者に対して通訳をするのではなく、診療する側の医師が聴覚障害者であり、彼に対して通訳をするため、通常の時の通訳とはまた異なる通訳の方法が必要になってくるという報告があった。これも、初めて気がついたことであり、このような場面での通訳の方法なども含めた、聴覚障害者が診療する側にいる場合の医療現場での通訳方法の整理が今後の課題として出されたと思う。
今回のケースは、聴覚障害学生本人の意欲、大学の理解と協力がうまくいったという面では良かったと思う。ただ、情報保障に要した経費の負担については、少し問題を残したのではないかと思われる。今回は学生側も負担したようであるが、他の学生より聴覚障害学生の負担が重くなることはあってはならないことであり、情報保障に要する経費の負担についても解決していかなければならない課題である。
調査者:河原 雅浩、大杉 豊
【報告資料⑧-1】I大学医学部における手話通訳派遣について
東京手話通訳等派遣センター
■概略
2005年12月から約1年6ヶ月にわたり、東京手話通訳等派遣センター(以下「当センター」という。)では、東京都内にあるI大学医学部へ手話通訳者を派遣した。
これまで当センターでは、高等教育機関や学生からの依頼に応じて、手話通訳者を派遣してきた実績がある。しかし、医学部へ手話通訳者を派遣するのは初めてのことであり、先行事例がないながらも、手話通訳派遣事業所として組織的にこの依頼に応じることになった。
特に病院内の臨床実習では、通常の高等教育場面での講義保障と異なり、手話通訳者の技術・能力を発揮するだけでなく、さらに医学・医療領域の知識が求められた。
この特殊性のある領域での手話通訳派遣の取り組みを振り返り、課題を整理することで、医学部へ手話通訳者を派遣するためのシステム構築や、手話通訳派遣のあり方を考察したい。
今後は、医者になるために「医師免許」の取得を目指し、医学部で学ぶ聴覚障害学生が増え、手話通訳の依頼や、手話通訳ニーズが高まることが予想される。今回のレポートが、医学部で学ぶ聴覚障害学生の教育を受ける権利が等しく保障されるために、全国各地で奮闘する手話通訳派遣事業所や、手話通訳者をはじめとする関係者の一助になれば幸いである。
1.手話通訳派遣の実施期間
2005年度12月~2007年度5月(約1年6ヶ月)
2.手話通訳派遣の依頼機関(派遣先)
東京都内I大学(医学部)
3.手話通訳派遣の実施機関
社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 東京手話通訳等派遣センター
4.手話通訳の内容
| 区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 講義 | 臨床医学、社会医学等 |
| 臨床実習(BSL) | 実際の医療場面での患者との接し方(コミュニケーション)、診断や治療方法等。教授回診、カンファレンス(治療方針等を検討する会議)、クルズス(臨床の講義)、手術見学等 |
| 試験 | 各試験等。習得した能力の評価、進級のための査定等 |
| その他 | 修学するにあたって必要なもの |
■手話通訳派遣のコーディネートと実施
1.準備過程
2005年12月に、依頼機関の大学で、聴覚障害学生(当時4年次)・教授・大学学生課・当センター職員が集まり、手話通訳者を派遣するにあたっての確認のため、打ち合わせを行った。
【確認事項】
- ①依頼までの経過
- ②修学の概要・・・5年次になると病院での臨床実習(ポリクリ・BST)が中心となり、病棟や外来で一定期間決められた診療科で実践的に学ぶ。
- ③臨床実習・・・実習として、患者とのコミュニケーションや、教授回診、カンファレンス(治療方針等を検討する会議)、クルズス(臨床の講義)、手術見学等がある。
- ④講義保障・・・a.板書、b.音声字幕装置、c.手話通訳の3つの方法を中心に、聴覚障害学生本人の希望や、内容に合わせて使い分けをする。
- ⑤手話通訳の依頼・・・聴覚障害学生⇒大学学生課⇒派遣センターの流れで行う。(原則的に、変更・キャンセル・確認事項等が生じた場合も大学学生課が集約窓口となる。)
2.手話通訳の依頼・変更・キャンセル等の連絡
当センター職員2名を担当窓口とした。連絡は、電話やメールでのやり取りが中心となった。円滑なコーディネート業務を遂行するため、I大学医学部専用の情報ファイルを作成し、依頼・変更・キャンセル等の管理と、履修要項・カリキュラムの概要等の資料を整理し保管した。そのファイルを見れば、部内スタッフでも一定程度の対応は可能な状態にした。
【依頼】
- 手話通訳依頼の基本的な流れは、「聴覚障害学生⇒大学学生課⇒派遣センター」とした。当センターから確認等のため連絡を取る場合も、大学学生課に連絡をするようにした。大学学生課に双方からの手話通訳派遣の情報が集約され、それが明確になることで当センターからの問い合わせもスムーズに行うことができた。
- 緊急の場合を除き、大学学生課からの手話通訳依頼は、大枠のカリキュラムごとに1ヶ月から3ヶ月間のクールでの連絡が多かった。
【変更・キャンセル】
- 臨床実習を行う診療科によっても異なるが、前日や当日の変更等も生じ、その都度大学学生課から連絡をもらった。
- 緊急時(急患等で当日、翌日午前中の依頼がキャンセルになる等)への対応として、窓口担当職員1名の個人が所持する携帯電話のメールアドレスを聴覚障害学生に伝え、夜9時まで、その職員とメールで連絡が取れるように急な変更やキャンセルにも対応できる体制を整えた。
【手話通訳者への依頼】
- 固定した登録手話通訳者と職員で担当することにした。
- 大学学生課が作成した「スケジュール表」を当センターでも使用し、それを担当手話通訳者にも所持してもらい、依頼漏れや派遣のミスを防ぎ、聴覚障害学生との確認も取れるようにした。
3.期別手話通訳者別可動状況〔可動があった期に「○」〕
| 年度(学年)/手話通訳者 | 登録手話通訳者 | 職員(手話通訳者) | 可動 人数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 看護師 | 臨床検査技師 | |||||||||
| 05年度後期 (4学年) |
○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ? | 6名 |
| 06年度前期 (5学年) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ○ | ○ | 7名 |
| 06年度後期 (5学年) |
○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | ○ | 6名 |
| 07年度前期 (6学年) |
○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | ○ | 6名 |
- 職員F→05年度窓口担当職員
- 職員H、I→06年度~07年度窓口担当職員
4.年度別手話通訳者別可動状況〔回数、(%)〕
| 年度(学年)/手話通訳者 | 登録手話通訳者 | 職員(手話通訳者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 看護師 | 臨床検査技師 | ||||||||
| 05年度 (4学年) |
7 (24%) |
7 (24%) |
6 (21%) |
2 (7%) |
- - |
5 (17%) |
2 (7%) |
- - |
- - |
| 06年度 (5学年) |
3 (3%) |
6 (5%) |
40 (36%) |
2 (2%) |
14 (13%) |
- - |
- - |
18 (16%) |
28 (25%) |
| 07年度 (6学年) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
- - |
- - |
- - |
1 (20%) |
1 (20%) |
- 05年度TTL=29回
- 06年度TTL=111回
- 07年度TTL=5回
- 講義では、教授から学生への一方向での話が多く、専門用語が多用されるので、専門用語を理解している登録手話通訳者を中心に派遣することが妥当であると判断した。そのため、登録手話通訳者で医療関係有資格者に依頼した。
- 医療関係有資格者は、病院等の医療関係施設で働いている者が多い。そのため、医療関係有資格者に手話通訳を担当してもらう際は、仕事の調整をお願いするなどの大きな協力があった。そのような協力があり、上記の派遣体制が実現できた。
- 臨床実習では患者との接し方やコミュニケーションが手話通訳の中心となるため、講義と比較し、専門用語は少なくなると判断し、医療関係資格を有していない登録通訳者にもお願いした。
- しかし、臨床実習の内容が急きょ変更等となり、カンファレンス(治療方針などを検討する会議)やクルズス(臨床の講義)で専門用語を多用する内容となることがたびたびあった。そのような状況を踏まえ、専門領域・継続性・緊急性が求められる手話通訳場面にできるだけ対応できる体制にするため、当初の登録通訳者(医療関係有資格者)4名と、当センター職員2名で対応することにした。
- 看護師有資格者でないと支障がある場合(臨床実習で、看護師有資格者以外が手話通訳を担当する場合は、患者の「承諾書」が必要になる等)は、大学学生課から通常より早めに(3ヶ月~6ヶ月前頃)に日程を知らせてもらい、看護師資格を有する登録手話通訳者にお願いし、仕事の調整をしながら担当してもらった。
5.大学や聴覚障害学生と手話通訳者、手話通訳者間の情報共有
- 大学学生課と密なやり取りを行い、手話通訳を行うために必要な情報や資料収集をできる限り行った。
- 「通訳連絡ノート」を作成し、大学学生課に保管してもらい、手話通訳者間の引継ぎ事項や、聴覚障害学生と確認した手話表現等を記入し、担当手話通訳者が通訳開始前に引き継ぎ事項等を閲覧・確認できるようにすることで、担当手話通訳者同士の情報共有を図った。
- 手話表現については、聴覚障害学生が創造した手話や、(財)全日本ろうあ連盟が出版した「医療の手話シリーズ」を活用した。
- 大学学生課が入手した様々な情報を当センターに連絡してもらい、ノートの中身においても、改めて担当手話通訳者に周知した方が良い内容は、その都度担当手話通訳者に連絡をした。
- 職員2名で、医療知識を深めるために医療に関する専門用語のリストを作成した。
- 聴覚障害学生から学生課を通してI大学独自の医療関係用語のリストをもらった。それを基に聴覚障害学生と手話表現について確認し、担当手話通訳者間で情報を共有した。
6.守秘義務、個人情報保護等
- 臨床実習が始まった当初は、担当手話通訳者個人が大学側で用意した守秘義務に関する確認書に署名をした。このような手話通訳者個々の署名は経過処置として取られたもので、その後は大学と当センターとで包括的な契約書を交わし、個々で署名をすることはなくなった。
- I大学医学部付属J病院では、上記の内容で対応可能だったが、I大学の他の付属病院では、手話通訳者(医療関係有資格者でない者)が診察場面に同席する場合には、患者個々に「承諾書」をもらうことになるとのことだった。そのため、看護師資格を持つ登録手話通訳者に限定して派遣することになった。
7.臨床実習における通訳場面
床の講義)、手術等の場面での手話通訳が必要となる。下記は、それぞれの場面における一例を示したものである。
◎聴覚障害学生 ●通訳 ○教授(医師) □健聴学生・医師
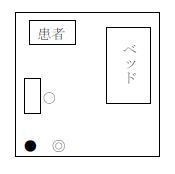
①診察
- 教授(医者)と患者とのやり取りや様子等を手話通訳する。
- 診察室は多くの学生が入室できるスペースがないため、その日毎に学生1名が診察室での診察を観察するための手話通訳が多かった。
- 言葉をそのまま伝えるように意識しながら手話通訳した。
- 患者への配慮が求められ、手話通訳者として日本語が聞こえやすく、手話が見やすい位置を選びにくい。
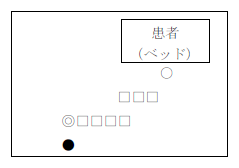
②教授回診
- 教授(医者)と患者とのやり取りや様子、学生への説明等を手話通訳する。
- 言葉をそのまま伝えるように意識しながら手話通訳した。
- 患者への配慮が求められ、手話通訳者として日本語が聞こえやすく、手話が見やすい位置を選びにくい。
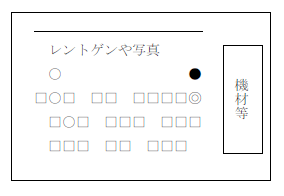
③カンファレンス・クルズス
- 教授(医者)と医者間で、症例検証や治療方針の検討・確認などを行うため、専門用語が多用され、やり取りや様子等を手話通訳する。
- 医者同士の会議や打ち合わせとなるため、瞬時に専門用語が多用される会話を手話通訳しなければならず、手話通訳者が情報保障をしていることの配慮をお願いした。
- 医学的な知識や、病院内のシステム、患者の様態等の共通した情報や認識を持つ医者が集まり、慌ただしく話が進むことが多い。
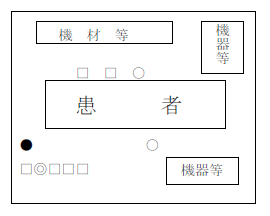
④オペ室
- 教授(医者)と医者、看護師等のやり取りや様子等を手話通訳する。
- 手話通訳者もオペ着に着替え、マスク着用で手話通訳に当たる。
- 患者の配慮や医療行為の優先が求められ、手話通訳者として日本語が聞こえやすく、手話が見やすい位置を選びくい。
8.その他
- 大学内では、白衣とネームプレート(「手話通訳」)を着用、また場合によってはマスク着用が義務づけられた。
- 医療の知識の学習や確認するため、大学内の図書館の利用(医療関係図書の閲覧と貸し出し可能)を認めてもらった。(図書館利用カードを貸与され所持)
■日常における医療場面通訳との違い
手話通訳派遣件数の報告を見ると、どこも共通して「医療・保健・健康」に関わる手話通訳派遣が多い。そういった公的派遣(コミュニケーション支援事業)では、聴覚障害者が患者である。従って、手話通訳の目的は、患者が自分自身の病気や怪我の状況を知ることや、治療していくための医師や看護師などとのコミュニケーション保障である。しかし、医学部における手話通訳では、患者である聴覚障害者への手話通訳とは目的が異なる。
医学部の講義や臨床実習等では、通常の医療場面の手話通訳とは異なる知識や技術が求められる。必然的に手話通訳者へのニーズや手話通訳の方法が異なってくる。聴覚障害学生には、医師の患者に対する接し方やコミュニケーションの取り方、患者の様子をリアルタイムで伝えることや、どのような日本語を選択しているのか等、教育・研究的なものとして伝えるよう心がけた。
■聴覚障害学生のエンパワメント
今の社会では、聴覚障害によるコミュニケーション障害は避けられない。聴覚障害者が、医療行為を行う場合、健聴者の患者がコミュニケーションに不安を持つことも予想される。
その反面、コミュニケーションが取りにくく、相手とのコミュニケーションを常に意識する環境で生活する聴覚障害者だからこそ、患者の目を見て、表情や行動等の細かな様子を観察し、患者の訴えを理解する努力をし、患者に理解して欲しいことを伝えていくことができるとも言える。病院経営の効率化により、電子カルテが表示されるディスプレイのみを見て、診察室内の会話が進む等、患者と医者等とのコミュニケーションの希薄さが問題となっている現在、コミュニケーション障害をプラスにしえるものだと考える。
■今後の課題
(1)コーディネート担当者としての課題
コーディネートを行う上で、授業内容の変更など緊急の対応ができる体制や関係機関との連絡、相談、提案ができる体制を整えることが課題であると考える。そのために、コーディネート担当者を固定することが望ましい。
- コーディネート体制(専任担当者の固定と共有化)
- 急な変更への対応(直前の授業内容の変更により、臨床実習から講義に変更になり、手話通訳者を追加派遣しなければならない時の対応等)
- 大学や聴覚障害学生との関係調整(連絡、相談、提案、手話通訳や手話通訳者への理解等、情報共有、共同作業)
- 事後処理、分析、評価(関係調整・情報提供・通訳条件整備)
- スーパーバイズ機能
- 専門領域の知識・継続性・緊急性のある手話通訳依頼に対応できる手話通訳者の養成と確保
(2)手話通訳者としての課題
通訳を行う上で、医療知識を深めることは言うまでも無いが、通訳環境をよりよくするための現場での対応も必要となってくる。
- 通訳条件(場面環境)の整備
- 聴覚障害学生へのエンパワメントアプローチや、潜在的なニーズの掘り起こし
- 特殊な場面での支援方法の創造(バリアの予測、回避、場面や対象者、患者や関係者も合意のできる支援)
- 高等教育場面や医学部での手話通訳のあり方の整理、研究
- 学習・研修機会の保障(費用、時間)
- 担当者会議の開催(費用、時間)
- ストレスケア
- 評価、評価システム
(3)手話通訳派遣事業所の手話通訳派遣の対応と、大学の直接雇用の対応
手話通訳で聴覚障害学生の情報保障を考えた際、今回のような手話通訳派遣事業所が手話通訳派遣をする場合と、大学が手話通訳者を直接雇用する場合と2つの方法が考えられる。その場合の考えられるポイントを挙げてみた。
*当センターが手話通訳者を派遣する場合
- 通訳課題を組織として受け止め、役割を分担し解決へとつないでいくため、個人の負担が軽減できる。
- スーパーバイザーの存在。
- 大学側と組織的な対応ができ、整理した確認作業がしやすい。
- 手話通訳者と大学内の関係者との関係作りがしにくい。
- 医療知識を深める手立てに制限がある。
- 担当手話通訳者を固定できない場合もあり、経験の積み上げがしにくい。
*高等教育機関が手話通訳者を雇用する場合
- 医療知識を深める手段が豊富にある。(積み上げができる)
- 関係者とのコミュニケーションが取りやすい。
- 通訳課題を解決する手立てが少ない。
- スーパーバイザーの不在。
- 大学側と通訳者が労使関係にあるため、改善のための手立てがとりにくい。
- 聴覚障害学生がいなくなれば、雇用の継続ができず、不安定な身分である。
(4)その他の課題
- 話通訳依頼の費用(日本私立学校振興・共済事業団の経常費助成金等)聴覚障害学生や、コーディネーターが手話通訳者の人数を増やすように要望すれば、その人数分費用が加算される。教授や病院の都合により、緊急な変更により待ち時間なども発生する。卒業するまでの6年間、手話通訳を利用すれば費用はかなり高額となる。参考までに、今回のケースでは、約150万円の手話通訳費用となり、聴覚障害学生も費用の一部を負担したと聞いている。
- 相談体制と手話通訳者の受入れ態勢(期間内の連携、他の学生との連携)
- 大学関係者への理解啓発
- 他のサポート機関や関係機関との調整(学生ボラ、他機関、支援ネットワーク)
- 手話の習得(インフォーマルなサポート)
- 手話単語の創造、整理、習得
- 臨床実習と手話通訳とのジレンマ(患者優先、個人情報保護、手術室でのマスク、先生の声が聞き取りにくい等)
- 経験の蓄積と整理(コーディネート、共同、手話通訳技術、手話通訳実践技術)
- 主体的にコミュニケーションが取れる環境づくり
■まとめに代えて
わずか約1年半の期間ではあったが、私たち手話通訳派遣事業所としては貴重な経験を得ることができた。その中で感じたことを振り返りまとめに代えたい。
まず、今回の手話通訳派遣に結びついたのは、聴覚障害学生の要望や努力も然ることながら、担当教授や大学学生課の理解が根底にあったからだと考える。また、情報保障のため、事前の情報や資料提供などの努力をしてくださったことで、一歩ずつ手話通訳環境の改善を見ることができた。また、聴覚障害学生と同じグループの学生の理解や協力も得られたことが、私たちの大きなサポートになり、励みにもになった。
やはり聴覚障害学生本人や関係者が一体となった協同的な関係や動きが、より良い情報保障に結びつくと改めて認識を強めた。
また、当センターには職員・登録手話通訳者を合わせると約120 名の手話通訳者がいる。また、その中に医療関係の資格を持つものが4 名おり、全面的な協力を得ることができた。このように、通常の手話通訳派遣件数に対応しながらも、専門領域・継続性・緊急性のある医学部の手話通訳派遣に応じることができたのは、手話通訳者とコーディネーターの力、これまでのノウハウの蓄積等、当センターとしての組織の力ではないかと思う。
さらに、大学の交通の便も良く、当センターからの距離も近いことなどの立地条件にも助けられた。しかし、今後も医学部等の高等教育場面への手話通訳を受けていくためには、社会システムや制度、財源の確保や改善と合わせて、専門領域の知識のある手話通訳者の確保、養成、人数の確保、コーディネート力が大きな鍵となると考える。


