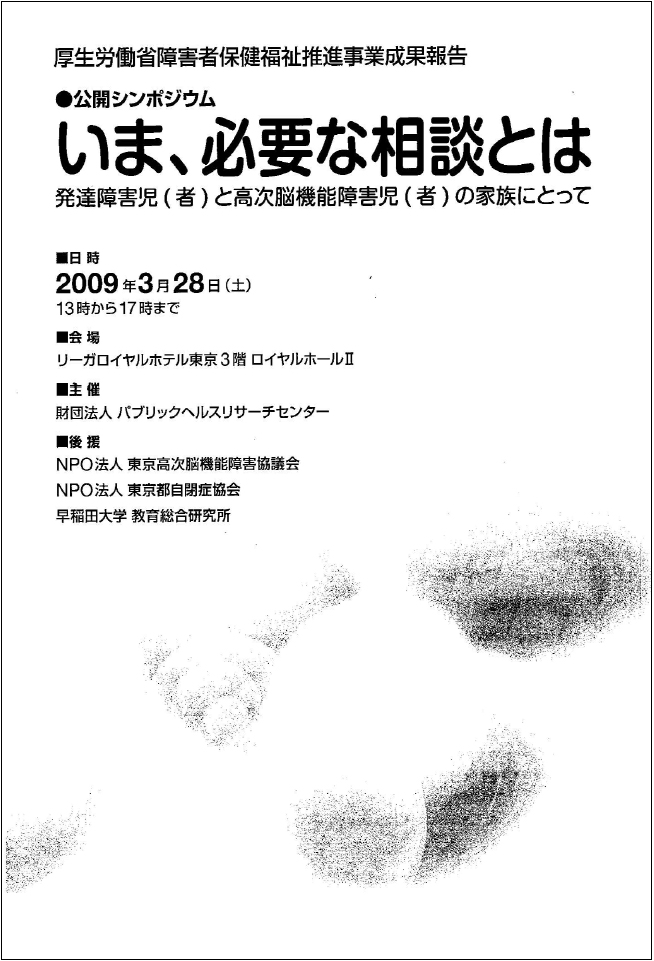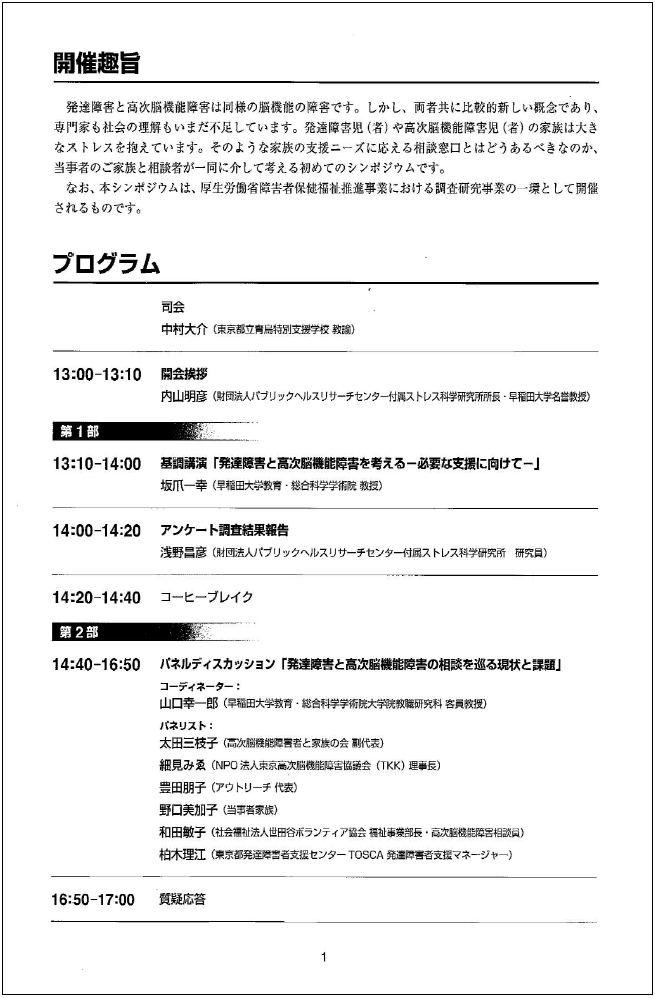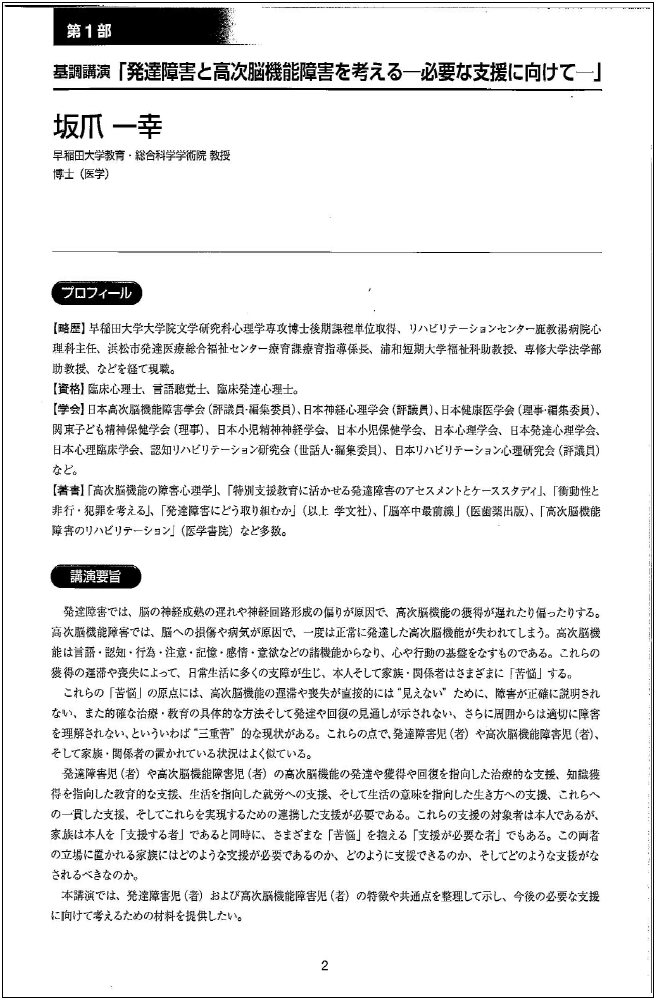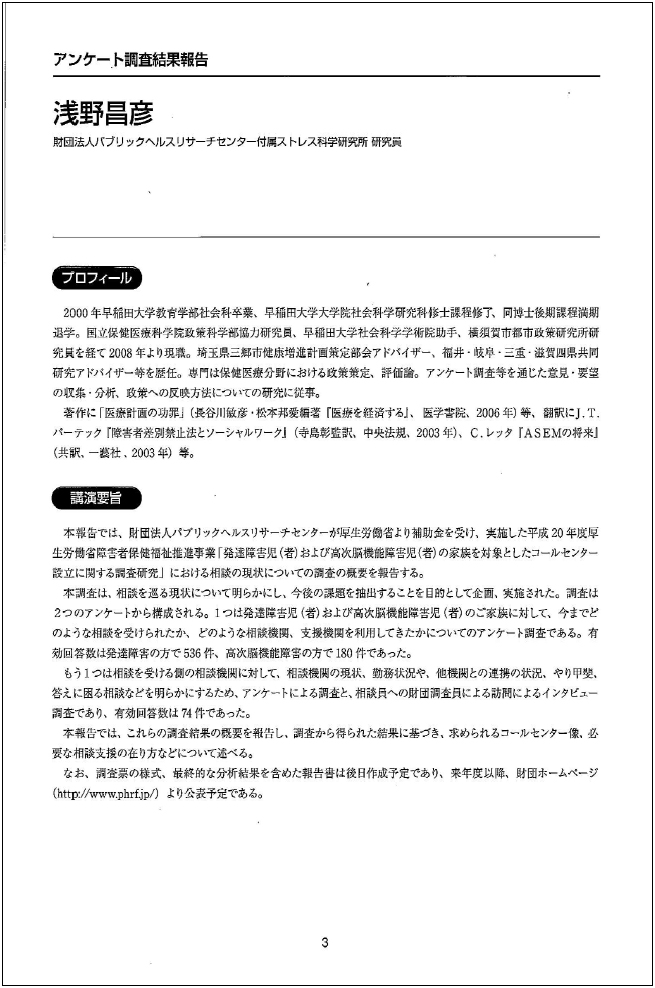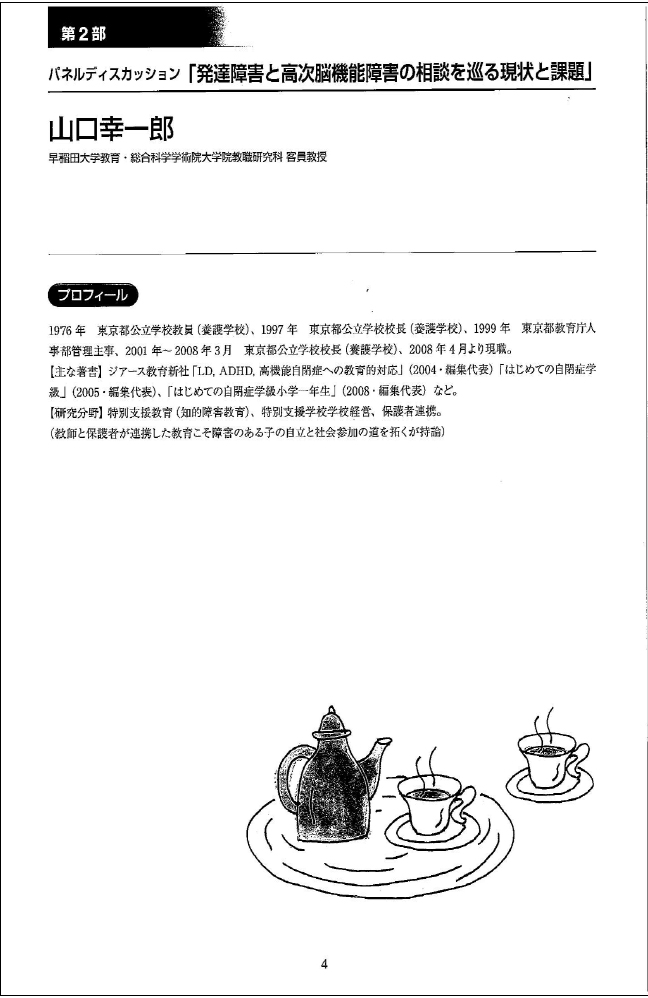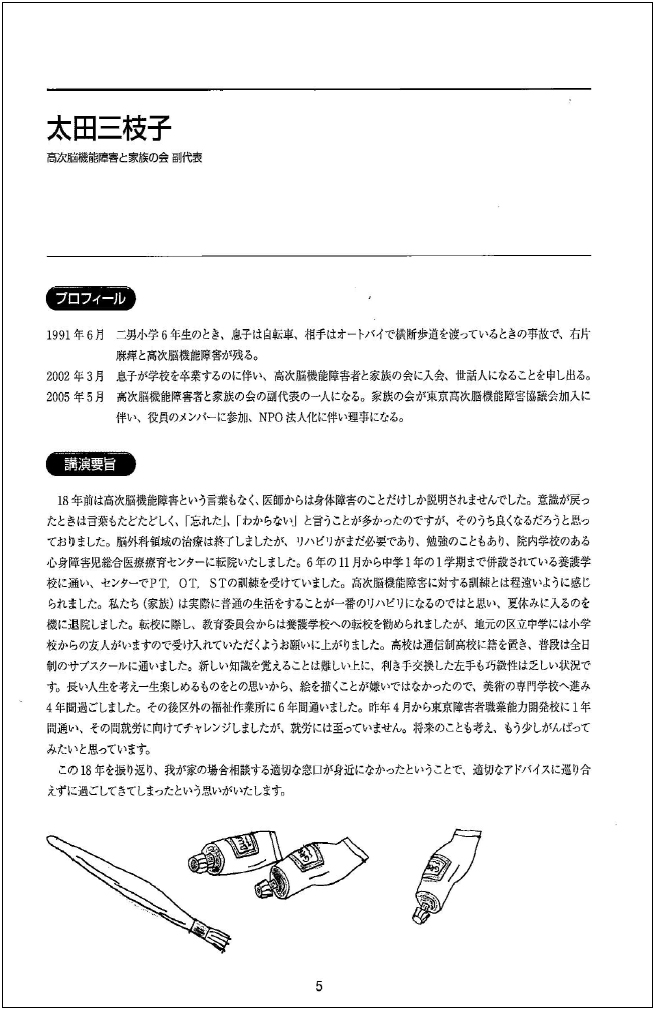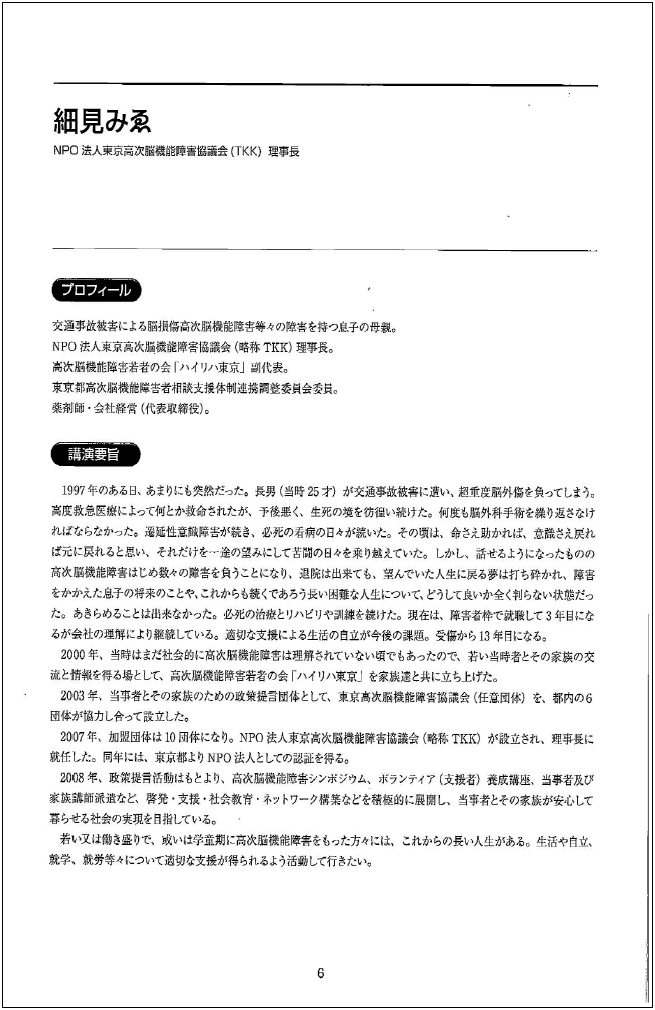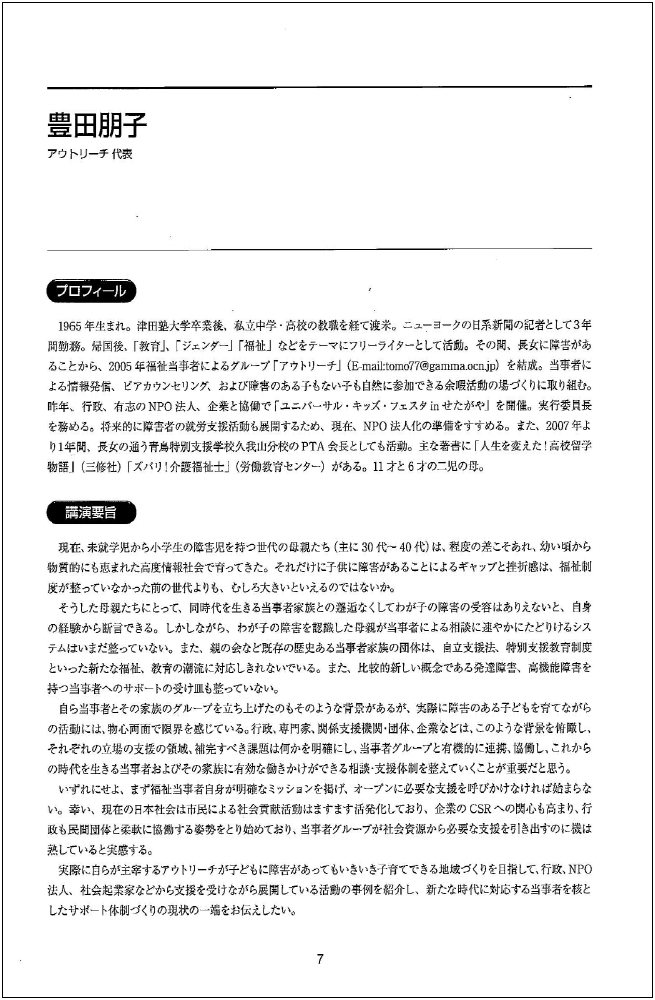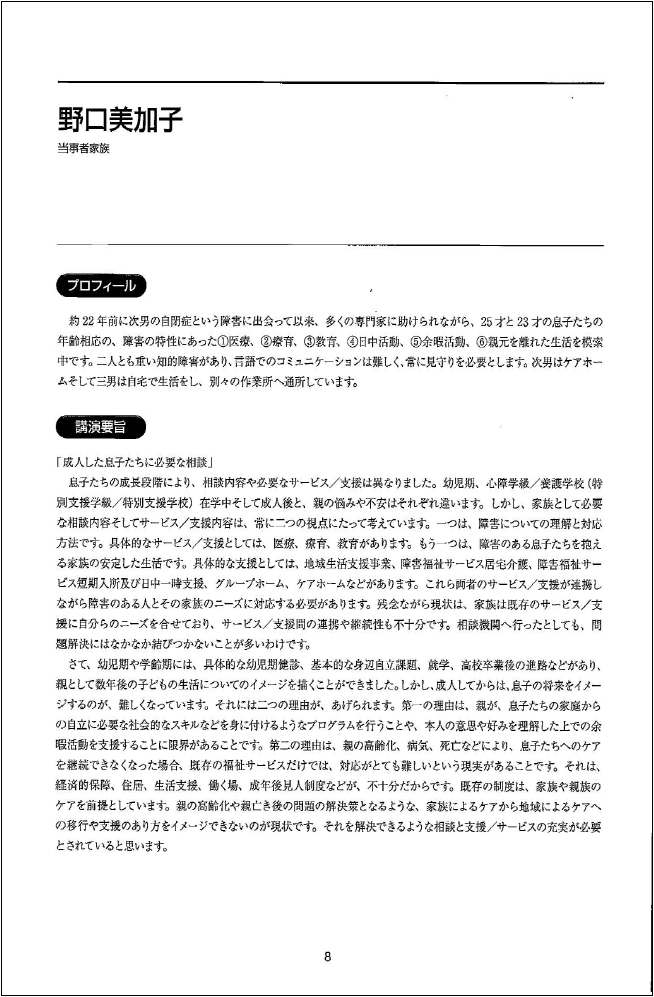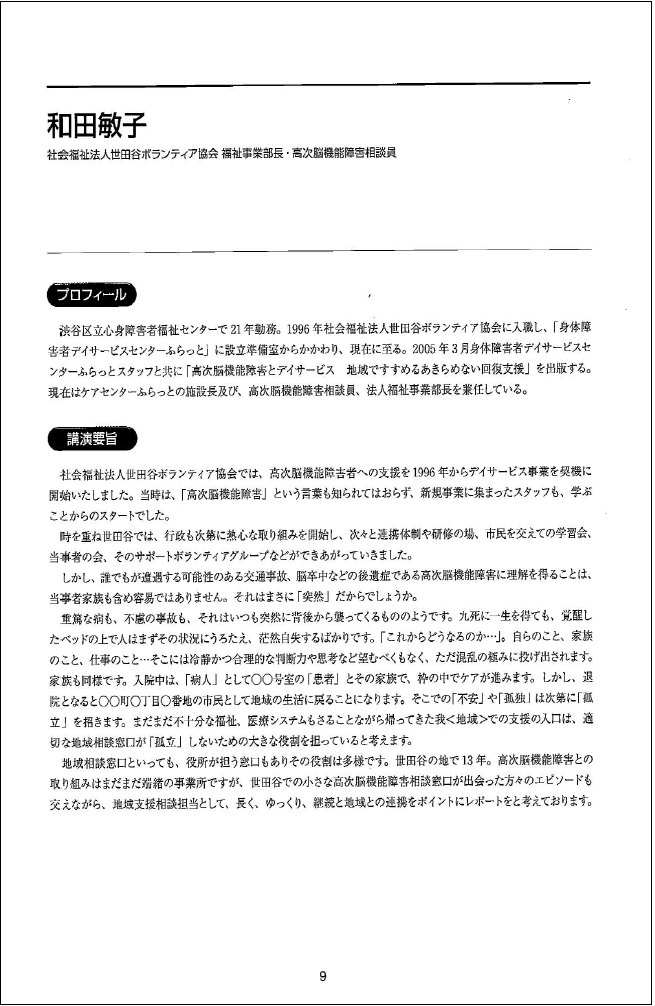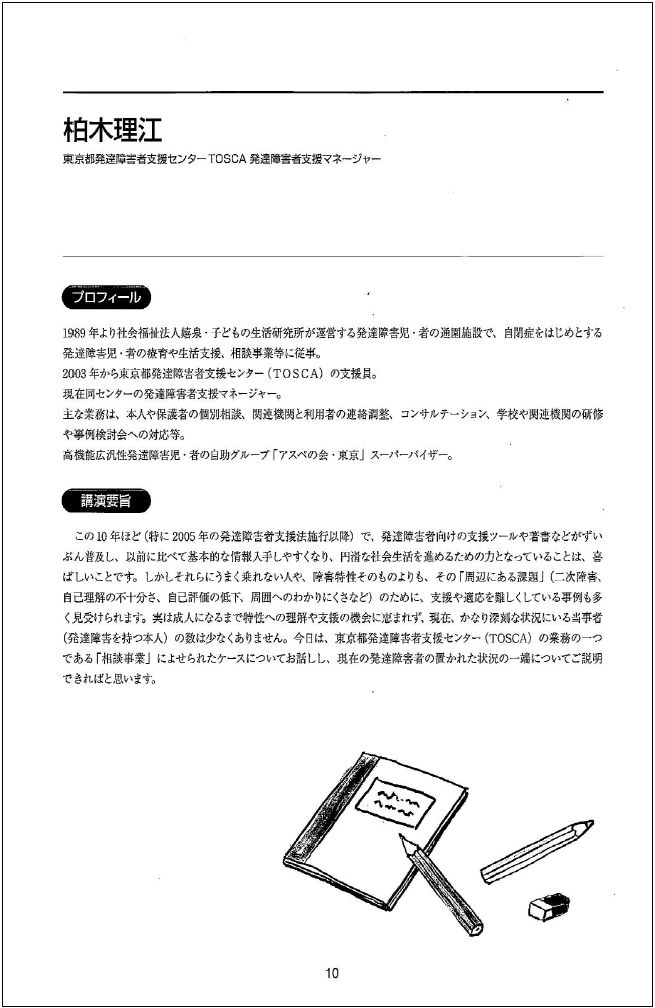5. 資料
5−3 ワーキンググループ名簿
| 氏 名 | 所 属 |
|---|---|
| 荻野 佳代子 | 早稲田大学 女性研究者支援総合研究所 客員准教授 |
| 佐藤 倫子 | 明治学院大学 心理学部 非常勤講師 |
| 山口幸一郎 | 早稲田大学 教職大学院 客員教授 |
| 米倉 康江 | 早稲田大学 教育学部 非常勤講師 |
(五十音順・敬称略)
5−4 ワーキンググループ議事録
⌈発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族を対象としたコールセンター設立に関する調査研究⌋
ワーキンググループ第 1 回ミーティング 議事録
【日時】
平成 20 年 8 月 6 日 ( 水 )
【場所】
財団法人パブリックヘルスリサーチセンター会議室
【出席者】
荻野佳代子、佐藤倫子、米倉康江、浅野昌彦、今津芳恵
【配布資料】
- 実施計画書
- 目的と概要
- スケジュール
- 予備調査質問紙、予備調査結果
- 参考資料( PHRF ストレスチェックリスト・ショートフォーム、地域住民用ソーシャルサポート尺度、心身障害児をもつ母親のストレス尺度、4 QRS 簡易型)
【議題】
1. 本事業の概要の説明
- コールセンターの最終イメージは以下の2つ。
- ① 情報コンシェルジュ ② 相談相手
- 本年度の課題は以下の2つ
- ① 発達障害および高次脳機能障害児(者)の家族に対する支援ニーズの調査
- ② 現存する資源のデータベースの作成
2. ワーキンググループの位置づけの説明
- ワーキンググループは以下の作業を行う。
- ① 上記調査の調査項目を作成する。
- ② 上記調査の調査結果を分析する。
- 調査の実施は事務局が行う。
3. 調査内容の検討
- 調査用紙に加える変数の検討から始める。
- 資源の使用の実態
- ① 公的な資源の実態(既存の資源の存在を知っているか否か、既存の資源を使って いるか否か、使っていないとしたらなぜか。)
- ② 私的な資源の実態(例えば既存のソーシャルサポート尺度を用いる。)
- 支援ニーズ(支援ニーズ尺度を作成する。)
- 現在のストレス
- ① ストレッサー(項目は既存のストレッサー尺度と面接調査の結果をもとに作成する。子どもの発達段階による分析ができるとベター。)
- ② ストレス反応( PHRF ストレスチェックリストを用いる。)
- ライフヒストリー
- (ストレッサーとストレス反応のレベルは、ライフステージの中で様々に変化しそうである。そこで、発達段階ごとにストレスの高低のプロフィールを描いてもらい、めだった変化のあった部分のエピソードを尋ねる。)
4. その他
- 次回のミーティングは 8 月 20 日(水) 1 時半より。財団会議室にて。
- 次回までに事務局で質問紙のフォーマットを作成しておく。
⌈発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族を対象としたコールセンター設立に関する調査研究⌋
ワーキンググループ第 2 回ミーティング 議事録
【日時】
平成 20 年 8 月 20 日 ( 水 )
【場所】
財団法人パブリックヘルスリサーチセンター会議室
【出席者】
山口幸一郎、荻野佳代子、米倉康江、今津芳恵
【配布資料】
- 第 1 回ミーティング議事録
- 調査内容案
- 参考資料(先行研究一覧、⌈発達障害の子を育てる家族への支援⌋、⌈障害児を育てる親の発達に関する文献検討⌋、⌈障害児をもつ親のストレスに関する文献検討⌋)
【議題】
1. 前回の議事の確認
2. 発達障害児(者)用調査票の検討
- 配付資料の⌈調査内容(案)⌋を参考に、調査票の検討を行った。
- ⌈属性⌋
- ① ⌈精神遅滞⌋は⌈知的障害(精神遅滞)⌋に変更する。
- ② ⌈障害名⌋は、複数回答と後の分析を考慮して、⌈主障害に◎、副障害に◯⌋をつけてもらう教示に変更する。
- ③ ⌈家族構成⌋は、複数名の障害児 ( 者 ) をもつ場合を考慮した内容にする。
- ④ ⌈手帳の有無⌋と⌈級⌋を追加する。
- ⑤ ⌈告知を受けた時期⌋と⌈告知された相手⌋を追加する。(告知が遅くなればなる ほど周囲の援助をうけにくくなってしまう可能性あり。)
- ⑥ 告知される前に⌈いつ異常に気づいたか⌋を追加する(異常に気づいてから告知されるまでの間に不安を抱えている可能性あり。)
- ⌈資源の利用の実態⌋
- ① ⌈資源⌋の意味を整理しておく(例えば、医療機関、行政機関、教育・療育機関のように大きな枠組みを作っておく)。
- ② ⌈知っている⌋⌈利用したことがある⌋⌈いつか利用したい⌋という尋ね方にする。
- ⌈支援ニーズ⌋
- ① 過去と現在について発達段階別に尋ねる(告知の前後と現在では異なる可能性がある)
- ② 親自身が意識できているニーズと与えられて初めて気づくニーズがあるので、それを明確化できる尋ね方を工夫する(情緒的サポートは意識できていない可能性がある)
- ⌈ストレス⌋
- ① 健常児(者)と異なるストレスを明確にできる項目をたてる(目の前の小さなストレスは解消可能だが、障害を持っているというストレスは一生涯解消できるものではない)
- 全体として仮説を明確にした上での質問票にするべき。
- ① 仮説Ⅰ:告知の前後が最もストレスが大きい
→告知前後の第一段階としての支援機関が必要。
- ② 仮説Ⅱ:告知の直後に適切な支援を与えられなかった場合、現在のストレスが大きい。
→告知直後の早期支援が必要。
- ③ 仮説Ⅲ:現在、大きなストレスを抱えている人は現在の支援が不足している。
→気軽に相談できる支援機関が必要。
- サンプル数は少なくても確実なデータを得たい。
- ① 積極的に支援を受けていない人達のうずもれた声を反映させたい。
- ② 調査員に、一人ずつ聞き取りで調査を行ってもらう方法もあり。
3. その他
- 次回のミーティングは 9 月 3 日(水) 1 時半より。財団会議室にて。
- 次回までに事務局で質問紙を作成しておく。
⌈発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族を対象としたコールセンター設立に関する調査研究⌋
ワーキンググループ第 3 回ミーティング 議事録
【日時】
平成 20 年 9 月 3 日 ( 水 )
【場所】
財団法人パブリックヘルスリサーチセンター会議室
【出席者】
山口幸一郎、荻野佳代子、米倉康江、佐藤倫子、今津芳恵、浅野昌彦
【配布資料】
- 第2回ミーティング議事録
- 調査票(案)
- 参考資料(検討委員会野口委員提供資料、⌈自閉症児を抱える母親のストレス構造⌋、自閉症児を育てる母親の子育てに対する気持ちとソーシャルサポートとの関連⌋、⌈就学前の自閉症児をもつ母親のストレッサーの構造⌋)
【議題】
1. 前回の議事の確認
2. 発達障害児(者)用調査票の検討
- 配付資料の⌈調査内容(案)⌋を参考に、調査票の検討を行った。
- ⌈属性⌋
- ⑦ 年齢の質問は最初には置かない。
- ⑧ 関係を問う設問では予め選択肢を用意して選択してもらう。
- ⑨ ⌈複数のご家族⌋を⌈複数の障害をお持ちのお子様⌋とする。
- ⑩ 告知についての設問では、⌈異常⌋という語は避け、⌈気になる点⌋等とする。
- ⑪ また、告知前に気になる点がなかった場合の選択肢も設定しておく。
- ⌈資源の利用の実態⌋
- ③ 大学の相談窓口があるので⌈大学などの相談機関⌋を追加。
- ④ 東京都の機関が対象のため、他県在住経験者には当該県の機関に相当する機関を選んでもらうようにする。
- ⑤ リストにない機関の利用の想定し、自由記載項目をつくる。
- ⌈身近な人のサポート⌋
- ① 障害者の親のサポートを知るためには、必ずしも必要とはいえない ( 引っ越しを手伝ってくれる人がいる等 ) 項目があるので修正。
- ② 配偶者、父母、きょうだい、友人だけでは不十分であり、親戚、学校の先生、ヘルパー等についても質問するとよい。
- ③ ⌈期待感⌋について聞いているが、援助の現状について聞くべきである。
- ⌈支援ニーズ⌋
- ③ まず、必要性を問い、必要とされた支援についてはそれを利用した場合、満足のいく形で与えられたか否かを質問する。
- ④ ダウン症は出生直後に診断できるため、出生直後からのニーズを聞く必要があるのではないか。
- ⑤ ⌈コーディネーター⌋等はもう少し分かりやすい語に言い換えられないか。
- ⑥ コールセンターについてもニーズを聞ければよい。
- ⑦ コールセンターのニーズについては、想定される傾聴、資源紹介、課題の整理など様々なコールセンター機能を細分化してそれぞれのニーズを聞けるとよい。
- ⑧ それらのニーズを満たすために利用した人、組織について書いてもらうのもよいのでは。
- ⌈ストレッサー⌋
- ② 頻度を問うものとなっているが、言葉の表現として頻度で回答しづらいものもある。
- ③ 頻度と同時に嫌悪度も測れるとよいのではないか。
- ⌈ストレス反応⌋
- ① デイリーハッスルだけではなくライフステージごとのストレスの推移がわかるとよい。
- ② 告知も含めて、いくつかのストレス要因となると思われるイベントを想定して、最もストレスが高かった出来事を100点としてもらい、それぞれのイベントのストレスを得点で表記してもらう。
3. その他
- 次回のミーティングは 9 月 17 日(水) 10 時より。財団会議室にて。
- 次回までに事務局で本日の議論、及び検討委員会での議論を反映させた質問紙を作成する。
以 上
⌈発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族を対象としたコールセンター設立に関する調査研究⌋
ワーキンググループ第 4 回ミーティング 議事録
【日時】
平成 20 年 9 月 17 日 ( 水 )
【場所】
財団法人パブリックヘルスリサーチセンター会議室
【出席者】
山口幸一郎、米倉康江、今津芳恵、浅野昌彦
【配布資料】
- 第3回ミーティング議事録
- 調査票 ( 案 )20080905
【議題】
1. 9 月 5 日検討委員会の報告
- 調査票の設問3・1のみを実施することとなった。理由は以下の2点。
- ① 実際、自閉症協会等ではアンケートの回収率が非常に低い (20%) 。枚数が多いアンケートは敬遠される。→アンケートは A4 か A3 を 1 枚程度にするべき。
- ② コールセンターの設立が最終目的であるならば、既存の支援機関の長所と短所の 把握を第一に行うべき。→当事者家族の支援機関への評価と同時に、支援機関の 相談員へのヒアリングを行うと、双方の思惑のずれが浮かんできて、既存の支援 機関の問題点が分かる。これだけでも今年度の課題として大きな意義がある。
- アンケートをするよりも、座談会やヒアリングを行って当事者の意見を聞くべきとの意見が多かった。
2. 発達障害児 ( 者 ) 用調査票の検討
- 支援機関を並べて、満足度を◎、◯、△、✕で評価させ、その理由をオープンアンサーにすれば、枚数は少なくて収まる。
- 提言なり分析なりをしていこうとすると、ある程度の数のデータで、数量化した形のものが必要であることを、当事者家族に説明して分かってもらう必要もある。
- 当事者家族はアンケート慣れしている、そしてアンケートの答える人はいつも決まって いるという 2 点で、これまでの数量的なデータへの信頼性は低い。質的なデータも必要。
- コールセンター設立のためには、このようなアンケートが必要であることを、当事者家族によく理解してもらう必要がある。
- アンケートで自分が答えたことが確実に何かの形に反映されていくという確証があるような形で調査を行えば、沈黙している当事者家族も積極的に答えてくれるのではないか。
- 当事者側の意に即した調査とう意味で、幾人か中心になる人を決めて、その人々にアンケートを配布・回収あるいは面接してもらうという方法にすれば、信頼性が高まるのでは。
- 支援機関の満足度と属性(性、年齢、告知の時期、以上に気づいてから告知までのタイムラグ)等に差が出ると興味深いがどうか。
- 支援機関が数多くあるけれど、当事者家族の不満は消えない。その不満がどこから来ているのかを拾える質問紙になるといいのだが。
- 調査をする目的をもう一度明確にしておくべき。この内容でどのような仮説が立てられるかを考えておくべき。
- 9 月 26 日(金)に当事者の家族を 10 名前後集めて座談会を実施する予定なので、それまでに上記のように調査票を作り直して、検討してもらう。
- 座談会では、調査の内容とその方法についても、当事者自身に考えてもらう形にしたい。
- 座談会では、いつもアンケートに答えない、積極的に支援機関を利用しない人からどうやったらデータを得られるかも尋ねる。
- 座談会の前に、作成し直した調査票と会議の趣旨を当事者家族に事前に送っておく。
- 座談会では山口先生に司会をしていただく。坂爪先生も参加していただく。
3. その他
- 特になし
以 上
5−5 シンポジウムリーフレット

5−6 シンポジウムプログラム