みんなが参加しともにあゆむ21世紀をめざして
山口県障害者福祉長期ビジョン
No.1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 立案時期 | 平成6年3月 |
| 計画期間 | 平成6年度~平成14年度(9年間) |
はじめに
昨年は、心身障害者対策基本法が全面的に改正され、名実ともに今後の障害者福祉の推進を図るうえでの基本的な法律である障害者基本法として生まれかわり、まさに歴史的に意義のある年でありました。
これまで本県では、昭和57年に策定した「山口県障害者対策長期計画」に基づき、各般にわたる施策を総合的に展開してきました。その結果、障害者関連施策が大幅に拡充される一方、障害者自身の自立と社会参加の意欲が高まり、県民の障害者への理解も深まるなど、長期計画は全体として着実な成果をあげてきたと考えています。
しかしながら、障害の重度化・重複化や障害者の高齢化及びニーズの多様化など、障害者を取り巻く環境も変化しており、県ではこうした状況に対応するとともに、これまでの成果とエネルギーをさらに発展させるため、障害者福祉長期ビジョン策定懇話会の委員をはじめ、県民各層の御意見をお聞きしながら、このたび、21世紀に向けた障害者福祉推進の指針となる「山口県障害者福祉長期ビジョン」を策定しました。
このビジョンは、障害者基本法の趣旨も踏まえ、「完全参加と平等」の実現に向けて、「障害者の自立への支援と社会参加の促進」「障害の重度化・重複化や障害者の高齢化への対応」「すべての人々の参加によるすべての人々に住みよいまちづくり」の視点に立ち、福祉、医療・保健、教育、雇用、生活環境など広い分野の諸施策を総合的かつ計画的に推進し、障害をもつ方々が地域で安心し、生きがいをもって生活できる“心のかよう福祉社会”を築いていこうとするものです。
このビジョンに基づき、みんなが参加しともにあゆむ21世紀をめざして、国や市町村との密接な連携のもとに、諸施策の積極的な展開に努める所存でありますので、今後とも、県民の皆様をはじめ、関係団体、企業などの一層の御理解と御協力をお願い申し上げますとともに、積極的な行動を期待いたします。
平成6年3月
山口県知事 平井 龍
目次
策定にあたって
1 ビジョン策定の趣旨
2 ビジョンの性格
3 ビジョンの期間
4 ビジョンの内容
5 ビジョンの推進
第1章 「国連・障害者の十年」及び「山口県障害者対策長期計画」の成果と動向
1 これまでの経緯
2 「国連・障害者の十年」の主な成果
3 「山口県障害者対策長期計画」の成果
4 障害者福祉の現状と動向
5 障害者基本法の成立
第2章 山口県の障害者の実態及び動向
1 全体の動向
2 身体障害者の状況
3 精神薄弱者の状況
4 精神障害者の状況
第3章 ビジョンの基本的考え方
1 障害者の自立への支援と社会参加の促進
2 障害の重度化・重複化や障害者の高齢化への対応
3 すべての人々の参加によるすべての人々に住みよいまちづくり
4 施策の連携と総合的推進
第1節 啓発・広報
1 啓発・広報の推進
2 福祉教育の推進
3 交流・ふれあいの促進
第2節 教育・育成
1 就学前教育・療育の充実
2 義務教育段階の教育の充実
3 後期中等教育段階の教育の充実
4 教職員等の指導力の向上
5 社会教育の充実と生涯学習の推進
第3節 雇用・就業
1 雇用の促進と安定
2 職業リハビリテーション対策の推進
3 福祉的就労の場の整備促進
第4節 保健・医療
1 障害の発生予防
2 障害の早期発見と早期療育の推進
3 医療及びリハビリテーション医療の充実
4 精神保健対策の推進
5 専門従事者の確保
第5節 福祉
1 生活安定のための施策の充実
2 在宅生活支援サービスの拡充
3 施設福祉サービスの充実
4 ひとづくりの推進
第6節 生活環境
1 住みよいまちづくりの総合的推進
2 住宅・建築物の改善
3 移動・交通対策の推進
4 情報提供体制の整備・充実
5 防犯・防災対策の推進
第7節 文化・スポーツ・交流
1 文化活動の促進
2 スポーツ・レクリエーションの推進
3 交流の促進
ビジョンの推進のために
1 適切な役割分担と協働
2 ビジョンの総合的推進
3 マンパワーの確保
4 ビジョンの進行管理
5 国への要請
主要な障害者施策の概要
障害者に対する主要な他制度による福祉措置
障害者基本法
山口県障害者福祉長期ビジョン策定懇話会設置要綱及び委員名簿
策定にあたって
1 ビジョン策定の趣旨
本県の障害者福祉については、ノーマライゼーションの考え方を基本理念として昭和57年(1982年)に策定した「山口県障害者対策長期計画」に基づき、各種の取り組みを進めてきました。しかしながら、住民意識の変革、生活環境の整備などの課題が残されている一方、障害の重度化・重複化や障害者の高齢化及びニーズの多様化など新たな課題も生じています。
そこで、障害者が地域で安心し、生きがいをもって生活できる福祉社会の実現を図るために、その指針として、「山口県障害者福祉長期ビジョン」を策定しました。
2 ビジョンの性格
このビジョンは、「山口県福祉マンパワー対策指針」との連携のもと、「山口県社会福祉基本構想」の障害者福祉に関する分野別計画として位置付けられ、次のような性格をもちます。- (1) 県における障害者(身体障害者・精神薄弱者・精神障害者)福祉を推進するための基本指針とします。
- (2) 障害者をはじめ、一般県民、団体、市町村などがそれぞれ行動を展開するための指針とします。
3 ビジョンの期間
平成6年度から平成14年度(1994~2002年)までの9年間とします。(主要事業のうち、数字で示すものは、平成12年度(2000年)とします。)
4 ビジョンの内容
「啓発・広報」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」、「福祉」、「生活環境」、「文化・スポーツ・交流」といった分野の総合的な内容とします。
5 ビジョンの推進
- (1) 国、市町村、関係団体、企業などと連携を図り、県民各層の理解を得ながら、総合的に推進することとします。
- (2) 組織的、継続的な進行管理を行います。
総論
第1章 「国連・障害者の十年」及び「山口県障害者対策長期計画』の成果と動向
1 これまでの経緯
障害者福祉については、国連が決議した「国際障害者年」(1981年)や「国連・障害者の十年」(1983~1992年)を通して、大きな進展がみられました。
さらに、1993年から2002年までを「アジア太平洋障害者の十年」とする国連の決議もなされました。
国においても、国連の動きに呼応し、昭和57年(1982年)に、「障害者対策に関する長期計画」を策定し、各種施策を進めてきました。
また、平成5年(1993年)には、新たに、今後10年間の取り組みの方向を示す「障害者対策に関する新長期計画」も策定されました。
一方、本県においては、「国際障害者年」及び「国連・障害者の十年」の趣旨、さらに、国の「障害者対策に関する長期計画」などを踏まえて、昭和57年(1982年)に、「山口県障害者対策長期計画」を策定し、各般にわたる施策を総合的に推進してきました。
特に、社会福祉の分野においては、「自立と社会参加の促進」、「在宅福祉の充実」、「障害者福祉施設の整備充実」の観点から、諸施策を推進してきました。
| 年 | 国際連合 | 国 | 山口県 |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1981年を「国際障害者年」とすることを 決議 | - | - |
| 1981 | - | 1112月9日を「障害者の日」と決定 | 「山口県国際障害者年推進 本部」の設置 |
| 1982 | 1983~1992年を「国連・障害者の十年」 とすることを宣言 | ・「障害者対策に関する長期 計画」の策定 ・総理府に「障害者対策推進 本部」設置 | 「山口県障害者対策長期 計画」の策定 |
| 1992 | 1993~2002年を「アジア太平洋障害者の 十年」とすることを決議 | 各種最終年記念事業の実施 | 各種最終年記念事業の実施 |
| 1993 | - | ・「障害者対策に関する新長期 計画」の策定 ・「障害者基本法」の成立 | - |
2 「国連・障害者の十年」の主な成果
「完全参加と平等」をめざして展開された「国連・障害者の十年」を通して、障害者福祉についての諸施策の着実な推進が図られてきました。昭和59年には、「身体障害者福祉法」が改正され、「完全参加と平等」という理念が法律に盛り込まれるとともに、法の対象となる障害者の範囲が拡大されました。
昭和61年には、年金制度の改正により、障害基礎年金制度が創設され、年金額の大幅な改善が行われました。
昭和62年には、従来、身体障害者のみを対象としていた「身体障害者雇用促進法」が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正され、対象範囲が精神薄弱者、精神障害者を含むすべての障害者に拡大されるとともに、精神薄弱者についても「雇用率制度」、「納付金制度」の対象とされることとなりました。
なお、平成4年には、さらに法改正が行われ、精神障害者が助成金の支給対象とされるとともに、雇用率制度及び給付金制度においては、重度精神薄弱者をダブルカウント(2倍して計算)することとされました。
精神障害者については、昭和62年に「精神衛生法」が「精神保健法」に改正され、精神障害者社会復帰施設が法律上位置づけられるなど、精神障害者の社会復帰の促進が図られました。
さらに、平成2年には、社会福祉関係八法が改正され、身体障害者関係施設への入所決定の事務や更生医療、補装具の交付事務などが町村に移譲され、市町村における在宅福祉サービスと施設福祉サービスの一元的な提供体制づくりが行われました。
| 年度 | 主な成果 | |
| S58 | ・第三セクター方式による重度障害者雇用企業の育成-民間企業と地方自治体の共同出資による重度障害者雇用のための企業への助成 | |
| S59 | ・身体障害者福祉法の改正-障害者の範囲の拡大(ぼうこう・直腸機能)や「完全参加と平等」の理念の盛り込み | |
| S60 | ・国民年金法等の改正-障害基礎年金制度の創設による年金額の大幅アップ | |
| S62 |
・障害者の雇用の促進等に関する法律への改正-障害者の範囲の拡大(実雇用率の対象に精神薄弱者を加えるなど)。平成4年には、重度障害者や精神障害回復者等に配慮した同法の改正が行われている。
・精神保健法への改正-精神障害者の人権の擁護と適正な医療の確保及び社会復帰の促進 | |
| H2 |
・国立筑波技術短期大学の開設-平成2年から聴覚障害者、平成3年から視覚障害者の受け入れを開始
・身体障害者福祉法等の改正-在宅福祉・施設福祉サービスを一元的かつ計画的に提供する市町村の体制の整備 | |
| H3 | ・障害者職業総合センターの開設 | |
| H4 |
・社会福祉事業法等の改正-福祉の人材確保のための基本指針の策定、福祉人材センター、福利厚生センターの設置
・ILO第159号条約(障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約)の批准-すべての障害者が適当な雇用の場に就くことができるようにし、障害者の社会への参加を促進するため、職業的リハビリテーションや雇用に関する措置を規定 |
3 「山口県障害者対策長期計画」の成果
本県においても、国際障害者年の趣旨をふまえて策定した「山口県障害者対策長期計画」に基づき、社会福祉施策の充実をはじめ、養護学校の整備充実、障害者の雇用・就労の促進、スポーツ、文化活動の促進など、各般にわたる諸施策を総合的に推進してきました。その結果、障害者自身の自立と社会参加の意欲が高まり、県民の障害者への理解も進んでおり、長期計画は全体として着実な成果を挙げてきたと言えます。
特に、社会福祉の分野では、身体障害者や精神薄弱者の福祉施設の整備充実などによる施設福祉の推進、福祉作業所・デイケアハウスやグループホームの整備促進、障害児の総合療育システムの整備充実などによる在宅福祉の推進、各種スポーツ大会の開催や全国スポーツ大会への参加、希望芸術文化展の開催、民間の公共的施設の改善を進める「人にやさしいまちづくり事業」や「視覚障害者情報提供事業」の実施などにより、障害者の自立と社会参加の促進に取り組んできました。
| 年度 | 主要施策 |
|---|---|
| S38 | ・山口県身体障害者体育大会の開始 |
| S40 | ・山口県精神保健大会の開始 |
| S48 | ・心身障害児(者)デイ・ケア推進事業の開始 |
| S50 | ・心身障害者福祉作業所の開始 ・保健所社会復帰相談事業の開始 |
| S53 | ・精神障害者共同作業所の開始 |
| S56 | ・総合療育機能推進事業の開始(山口市でモデル実施) ・ミニ障害者福祉都市推進事業の開始 |
| S57 | ・鹿野グリーンハイツ開設 ・精神保健社会適応訓練委託事業の開始 |
| S58 | ・山口県障害者希望芸術文化展開催 ・川上すぎのこ村開設 |
| S59 | ・総合療育機能推進事業の本格実施開始 |
| S60 | ・精神薄弱者ミニ福祉ホーム事業の開始 |
| S61 | ・心身障害児(者)デイ・ケア推進事業の拡大 |
| S62 | ・精神薄弱者社会自立促進事業の開始 ・施設機能強化推進事業の開始 ・地域リハビリテーション推進事業の開始 ・乳幼児発達クリニック事業開始 |
| S63 | ・身障者ガイドヘルパー派遣事業の開始 ・精神薄弱者地域生活援助事業の開始 ・精神障害者社会復帰施設の設置開始 |
| H元 | ・ショートステイ居室整備事業の開始 ・精神薄弱者グループホーム事業の開始 |
| H2 | ・西日本車いすロードレース大会の開始 ・心身障害児(者)施設機能オープン化促進事業の開始 |
| H3 | ・身体障害者社会参加促進センターの設置 ・障害者の住みよい福祉のまちづくり事業の開始 ・障害者の創作・生産活動支援事業の開始 ・総合療育機能推進事業の実施地区拡大の完了 |
| H4 | ・「国連・障害者の十年」記念事業の実施 ・精神薄弱者スポーツ振興事業の開始 ・心身障害児母子通園訓練事業の開始 ・身体障害者健康診査事業の開始 ・人にやさしいまちづくり事業の開始 |
| H5 | ・視覚障害者情報提供事業の開始 ・精神薄弱者社会活動総合推進事業の開始 |
《障害福祉関係施設の設置箇所数等の推移》(国連・障害者の十年 - 1983~1992年)
- 心身障害者関係施設 -
| 施設種別等 | 1983年(S58) | 1992年(H4) | 期間中の事業量 | |||
| 箇所数 | 定員 | 箇所数 | 定員 | 箇所数 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者更生援護施設 | 11 | 494 | 14 | 680 | 3 | 186 |
| 精神薄弱者援護施設 | 23 | 1,060 | 36 | 1,780 | 13 | 720 |
| 心身障害者福祉作業所 | 21 | 210 | 27 | 300 | 6 | 90 |
| 心身障害児デイ・ケアハウス | 12 | 20 | 17 | 160 | 5 | 40 |
| グループホーム | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 28 |
| 公共施設等改善関係事業 | 12市7町で実施済 | 14市30町村で実施済 | 2市23町村で実施 | |||
| 総合療育機能推進事業 | 1市(山口市) | 全市町村 | 13市42町村 | |||
- 精神障害者関係施設 -
| 施設種別等 | 1983年(S58) | 1992年(H4) | 期間中の事業量 | ||||
| 箇所数 | 定員 | 箇所数 | 定員 | 箇所数 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会復帰 施設 | 援護寮 | - | - | 3 | 60 | 3 | 60 |
| 福祉ホーム | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| グループホーム | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神障害者共同作業所 | 5 | 67 | 17 | 284 | 12 | 117 | |
《県内障害者の雇用状況》
| 業種区別/法定雇用率 | 1983年(S58) | 1992年(H4) | 期間中の増加 | ||||
| 障害者数 | 雇用率 | 障害者数 | 雇用率 | 障害者数 | 雇用率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般企業 | 1.6% | 1,388 | 1.60% | 1,841 | 1.75% | 453 | 0.15% |
| 市町村 | 2.0% | 312 | 2.39% | 294 | 2.35% | △ 18 | △0.04% |
4 障害者福祉の現状と動向
国の中央心身障害者対策協議会の意見具申(「国連・障害者の十年」の最終年に当たって取り組むべき重点施策について(1991年)及び「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方について(1993年))では、障害者福祉は全般的に各部門において着実な進展をみていると評価されています。本県においても、すでに述べているように「山口県障害者対策長期計画」に基づき、障害者福祉に関する諸施策が積極的に推進される一方、障害者自身の自立と社会参加の意欲が高まり、県民の障害者への理解も進んでおり、長期計画は全体として着実な成果を挙げてきたといえます。
「国連・障害者の十年」や「山口県障害者対策長期計画」を通して達成されたこれらの成果をさらに進展させるとともに、これまで積み上げられてきた障害者福祉についての関心とエネルギーを継承しつつ、今後さらに障害者福祉を充実させていくことが期待されています。
ところで、現在、障害者福祉の大きな流れとして、身体障害者中心から全障害者へ、軽度障害者から重度(重複)障害者へ、施設中心の福祉から在宅サービスを重視した地域のネットワークに依拠した福祉へ、職業的自立中心からより広く精神的自立(自己決定の保障)なども含む自立や社会参加へと、対象、施策分野が拡大し、施策の重点に変化がみられます。
こうした流れは今後さらに進めていく必要があり、施策内容の拡大や充実がより一層高いレベルで求められているといえます。
5 障害者基本法の成立
平成5年11月、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、「心身障害者対策基本法」が改正され、「障害者基本法」が成立しました。(本文は巻末資料)《改正の主な内容》
| (1) 法律の対象となる者の名称を「障害者」に改め、身体障害、精神薄弱又は精神障害が法律の 対象であることを明らかにした。 (2) 障害者の自立と社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動への参加促進を法律の目的とした。 (3) 12月9日を「障害者の日」とした。 (4) 政府は障害者基本計画を策定するとともに、都道府県・市町村も同様の計画を策定するように 努めることとされた。 (5) 雇用の促進・公共的施設の利用、情報の利用などについて、国及び地方公共団体が講ずべき 施策に関する規定を整備するとともに、事業主に対しても所要の努力義務規定を設けた。 |
第2章 山口県の障害者の実態及び動向
1 全体の動向
本県における障害者の全体的な状況は、次の3点にまとめられます。| 障害者全体は年々増加している。 |
| 障害児に比べ、障害者の増加が著しく、高齢化が進んでいる。 |
| 障害の重度化や重複化の傾向がみられる。 |
2 身体障害者の状況
【身体障害児の減少と身体障害者の増加】| ○ | 本県の身体障害者は、昭和61年3月末が47,254人、人口千人当たり29.5人、平成5年3月末が57,503人、人口千人当たり36.9人となっており、実数、総人口に占める割合とも増加しています。 |
身体障害者手帳所持者数の推移
| 年度 | 所持者数(人) |
|---|---|
| S60 | 47,254 |
| S61 | 49,893 |
| S62 | 51,606 |
| S63 | 51,743 |
| H元 | 53,337 |
| H2 | 54,443 |
| H3 | 55,509 |
| H4 | 57,503 |
| ○ | 昭和61年3月末で、身体障害児(18歳未満)は1,335人、身体障害者(18歳以上)は45,919人、平成5年3月末で、身体障害児は1,308人、身体障害者は56,195人となっており、昭和61年3月末と平成5年3月末を比較すると、身体障害児は2.0%減少し、身体障害者は22.4%増加しています。出生率の低下と高齢化の傾向が大きく影響しているようです。 |
身体障害者手帳所持者数(児・者別)の推移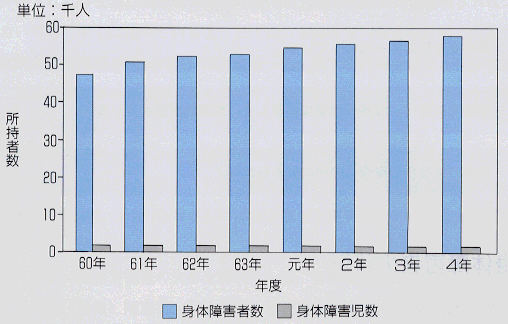
資料:障害福祉課
【高齢化の傾向】
| ○ | 60歳以上の占める割合が、昭和60年7月現在52.0%を占めていましたが、平成5年3月末では66.9%に増加しており、高齢化の傾向が著しくなっています。 |
| ○ | 高齢化の理由として、(1)人口の高齢化に伴い、高齢期に身体障害者となる人が増加したこと、(2)一般の高齢化と同様に、身体障害者についても高齢化が進んでいることなどが考えられます。 |
【重度化の傾向】
| ○ | 障害程度等級1・2級の重度の身体障害児・者が、昭和61年3月末では全体の35.9%を占めていましたが、平成5年3月末では、39.4%に増加しており、障害の重度化が進んでいます。 |
昭和61年3月
| 級 | (%) |
|---|---|
| 重度(1,2級) | 35.9 |
| 中度(3,4級) | 37.7 |
| 軽度(5,6級) | 26.4 |
平成5年3月
| 級 | (%) |
|---|---|
| 重度(1,2級) | 39.4 |
| 中度(3,4級) | 38.2 |
| 軽度(5,6級) | 22.4 |
【肢体不自由が全体の55%】
| ○ | 身体障害児・者を障害の種類別にみると、最も多いのは「肢体不自由」で全体の55.0%を占めています。次いで、「内部障害」が全体の17.6%を占めています。増加率が最も高いのが「内部障害」で、昭和61年3月末と比較すると87.3%ほど増加しています。 「内部障害」の増加が著しいのは、「心臓疾患」や「じん臓疾患」が増加していることや「ぼうこう・直腸機能障害」などが身体障害者手帳の交付対象に加わったことによると思われます。 |
障害種類別身体障害者手帳所持者数(単位:人)
| 障害の種類 | 昭和61年3月 所持者数 | 平成5年3月 所持者数 |
|---|---|---|
| 視覚 | 6,840 | 7,365 |
| 聴覚・平衡 | 7,433 | 8,409 |
| 肢体不自由 | 27,574 | 31,603 |
| 内部 | 5,407 | 10,126 |
【障害原因は疾病が4割】
| ○ | 平成2年度に実施した心身障害者実態調査によると、在宅の身体障害児・者の障害の原因は、「疾病」によるものが41.6%、「事故」によるものが21.3%となっています。 なお、「疾病」の内容としては、「脳血管障害」が最も多く、「疾病」全体の3割近くを占めています。 |
障害を受けた原因
(心身障害者(児)実態調査(平成2年度))
| 障害を受けた原因 | (%) |
|---|---|
| 10.8 | |
| 30.8 | |
| 11.9 | |
| 9.2 | |
| 4.9 | |
| 7.2 | |
| 3.9 | |
| 21.3 |
3 精神薄弱者の状況
【精神薄弱者の増加】※1 ○| 県内の療育手帳所持者は、昭和61年3月末が4,443人、人口千人当たり2.7人、平成5年3月末が6,166人、人口千人当たり3.9人となっており、実数、総人口に占める割合とも増加しています。 |
養育手帳所持者数の推移
| 年度 | 所持者数(人) |
|---|---|
| S60 | 4,443 |
| S61 | 4,687 |
| S62 | 4,987 |
| S63 | 5,281 |
| H元 | 5,490 |
| H2 | 5,695 |
| H3 | 5,939 |
| H4 | 6,166 |
| 療育手帳所持者数の児・者別の推移を見ると、18歳未満の手帳所持者(精神薄弱児)数に比べ、18歳以上の手帳所持者(精神薄弱者)数が増加しています。 出生率の低下や各種制度の周知などによるものと思われます。 |
療育手帳所持者数(児・者別)の推移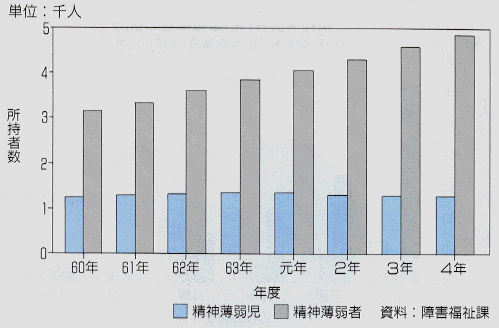
| ※1 | 精神薄弱者 | |
| この用語の問題については、現在、国において検討中である。 |
【身体との重複障害者は4人に1人】
| ○ | 身体との重複障害者は26.7%と4人に1人の割合です。 重複する障害の内容は、「非進行性脳病変による運動機能障害(脳性まひ等)」との重複が23.4%と最も多く、次いで、「上下肢」が19.4%、「音声・言語」が12.8%、「下肢」が7.8%となっています。 なお、昭和60年度の調査時点では、身体との重複障害者が21.7%であり、増加傾向にあります。 |
精神薄弱者(児)の重複障害の状況
(心身障害者(児)実態調査(平成2年度))
| 重複障害の状況 | (%) |
|---|---|
| 運動機能 | 23.4 |
| 上肢・下肢 | 19.4 |
| 音声・言語 | 12.8 |
| 下肢 | 7.8 |
| 聴覚・平衡 | 7.2 |
| 視覚 | 6.6 |
| 体幹機能 | 6.2 |
| 内部障害 | 5.1 |
| 上肢 | 3.8 |
| 不明 | 7.7 |
| ○ | 重度の身体障害(身体障害者手帳1~2級)と重度の精神薄弱(療育手帳A)をあわせもつ重複障害者が多い状況がうかがわれます。 |
精神薄弱者(児)重複障害の状況
(心身障害者(児)実態調査(平成2年度))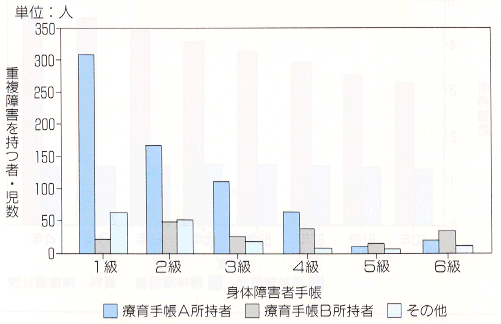
資料:障害福祉課
4 精神障害者の状況
| ○ | 本県の精神障害者の数は、実態の把握が困難ですが、平成5年3月末で、約21,000人(推計)となっています。 |
| ○ | 昭和57年3月末の数は約14,000人(推計)となっており、増加傾向にあります。 特に、入院患者では、専門病棟も整備されはじめ、脳器質性精神障害(老人性痴呆等)が増加傾向にあります。 |
入院患者の状況(病名別)
昭和57年3月
| 病名 | (%) |
|---|---|
| 分裂病 | 59.9 |
| 脳器質性精神障害 | 14.7 |
| 中毒性精神障害 | 8.4 |
| 躁うつ病 | 3.5 |
| てんかん | 2.8 |
| その他 | 10.5 |
平成5年3月
資料:健康増進課| 病名 | (%) |
|---|---|
| 分裂病 | 59.7 |
| 脳器質性精神障害 | 19.1 |
| 中毒性精神障害 | 6.4 |
| 躁うつ病 | 4.6 |
| てんかん | 2.1 |
| その他 | 8.2 |
第3章 ビジョンの基本的考え方
障害者一人ひとりの尊厳を大切にするという「人間尊重」を基本とし、ライフステージのすべての段階での全人間的復権をめざす「リハビリテーション」の理念と障害者が障害をもたない者と同等に生活し、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念のもと、「完全参加と平等」の実現をめざし、障害者福祉を推進します。リハビリテーションの理念とは
| 障害者の人間性回復という立場から、単に身体の機能回復のみでなく、障害者が人間としての尊厳を回復し、その能力を最大限に発揮できるよう、自立と社会参加を促進する考え方 |
※リハビリテーションには、医学的・教育的・職業的・社会的リハビリテーションの4つの分野があります。
ノーマライゼーションの理念とは
| すべての人々が共に生活し、互いに助け合う社会を実現するために、若者も高齢者も、障害をもつ人ももたない人も、共に平等に社会の一員として生活し、活動する地域社会づくりをすすめる考え方 |
「障害」の概念について
| WHO(世界保健機構)の「国際障害分類試案」(1980年)によれば、障害は次の3つに分類されます。 ○個人の特質である「機能障害」 ○そのために生ずる機能面の制約である「能力低下」 ○「能力低下」の社会的結果である「社会的不利」 |
1 障害者の自立への支援と社会参加の促進
| ○ | 障害をもつ人も、障害をもたない人と同様、自立した主体的存在であるという意識を今後さらにひろめ、社会全体で、障害者の自立を支援し、社会参加といきがいづくりを進めていきます。 |
| ○ | 「自立」は、単に職業的自立のみでなく、生活の自立や精神的自立(自己決定の保障)なども含んでおり、そうした広い意味での「自立」を支援します。 |
| ○ | 今後特に進めていく必要があるのは、障害者の自立と社会参加にとってハンディキャップとなる物理的な障壁、制度的な障壁、文化・情報における障壁、意識上の障壁を除いていくことであり、そのための取り組みを積極的に進めていきます。 |
| ○ | 関係機関の連携により、障害児の早期発見、早期療育を進める総合療育システムの拡充、養護学校や特殊学級などでの教育体制の充実、職業リハビリテーションの推進、脳卒中後遺症患者や精神障害者等の病院退院後のリハビリテーションシステムの確立など、ライフステージのすべての段階で、障害者のニーズに応じて、いつでもどこでも適切なリハビリテーションが一貫した形で提供されるシステムづくりを進めていきます。 |
2 障害の重度化・重複化や障害者の高齢化への対応
| ○ | 重度・重複障害者が地域で生きがいのある安心した生活を送ることができるよう、各種サービスを充実させるとともに、その利用を促進します。 |
| ○ | 専門機関や家族、地域住民などにより、援護を必要とする対象者を中心にネットワークを形成し、対象者のニーズに応じた適切なサービスを提供していきます。 |
| ○ | 重度・重複障害者や高齢障害者に対する雇用の促進や施設福祉の充実に努めます。 特に、施設に対しては、生活や就労の場としてのみならず、在宅で生活する障害者のための地域サービスの拠点となるよう、施設機能の拡充に努めます。 |
| ○ | 障害者の多くが高齢者であることから、高齢者施策との一体的推進が必要であり、各種サービスの一体的実施やサービス実施施設の相互利用などを進めます。 |
| ○ | 在宅の重度・重複障害者の世話をする介護者も高齢化が進んでいる実態を考慮しながら、在宅介護者を支援する施策を推進します。 |
3 すべての人々の参加によるすべての人々に住みよいまちづくり
| ○ | ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者にとって住みよいまちづくりを進めることが、高齢者、児童、妊産婦などすべての人々にとって住みよいまちづくりにつながるという認識をひろげていきます。 |
| ○ | 住民の声、とりわけ、障害をもつ人々の声を十分聞きながら、関係機関・団体・事業主などすべての人々の参加と連携によりまちづくりを進めていきます。 |
| ○ | 住宅、公共建築物、交通ターミナル、道路、バス、電車などハード面の整備改善だけでなく、移動サービスシステム、情報提供サービスなど、ソフト面でのサービスの充実にあわせ、障害者をとりまく人々の意識の啓発に努めます。 |
| ○ | 障害者や高齢者などに配慮した施設や設備などの整備については、障害者や高齢者の立場に立ち、これまでの点的整備から、連続的で面的な整備へ向けた取り組みを進めます。 |
| ○ | 施設の整備については、障害者専用の施設ではなく、障害者をはじめ、だれもが利用できるような施設の整備に努めます。 |
4 施策の連携と総合的推進
| ○ | 福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境など広い分野の関連施策の連携に努め、障害者の立場に立って、各種サービスを総合的かつ有機的に提供することに努めます。 |
| ○ | 情報提供機能の充実や総合相談体制の整備を図り、障害者が利用できる各種のサービスが総合的かつ一元的に提供されるよう努めます。 |
各論
第4章
施策の現状、課題及び今後の方向
主要施策の体系
第1節 啓発・広報
第2節 教育・育成
第3節 雇用・就業
第4節 保健・医療
第5節 福祉
第6節 生活環境
第7節 文化・スポーツ・交流
| 大項目 (分野) | 中項目 (重点目標) | 小項目 (施策の方向) |
|---|---|---|
| 啓 発 ・ 広 報 | 啓発・広報の推進 | マスメディアの有効活用 「障害者の日」等の有効利用 住民参加による住みよい福祉のまちづくりの推進 |
| 福祉教育の推進 | 小中学校等の学校教育における福祉教育 一般社会人を対象とした啓発・広報 | |
| 交流・ふれあいの促進 | ボランティア活動への支援 相互交流の充実 | |
| 教 育 ・ 育 成 | 就学前教育・療育の充実 | 盲・聾学校幼稚部の充実 幼稚園や保育所での障害児の受け入れの促進 教育、医療、福祉等関係機関による指導・相談 体制の整備 |
| 義務教育段階の教育の充実 | 教育方法・内容の改善、研究による質的充実 学校教育全体における特殊教育への認識の向上 就学指導体制における連携の強化 | |
| 後期中等教育段階の教育の充実 | 特殊教育諸学校高等部の整備・充実 職業教育、進路指導の充実 | |
| 教職員等の指導力の向上 | 教職員等の指導力の向上 | |
| 社会教育の充実と生涯学習の 推進 | 地域における学習の場の充実・確保 生涯学習ボランティア活動の推進 | |
| 雇 用 ・ 就 業 | 雇用の促進と安定 | 総合的な雇用対策の推進 重度障害者雇用の推進 精神薄弱者、精神障害者の雇用対策の推進 |
| 職業リハビリテーション対策の 推進 | 職業能力開発機能の充実 実践的研究の成果及び就労支援機器の普及 職業リハビリテーションネットワーク体制の 整備 | |
| 福祉的就労の場の整備促進 | 職業能力開発機能の充実 授産施設の拡充 福祉工場の整備 | |
| 保 健 ・ 医 療 | 障害の発生予防 | 障害の発生予防 |
| 障害の早期発見と早期療育の 推進 | 早期発見から早期治療に結びつける体制の強化 早期発見から早期療育にいたる一貫した相談指導 体制の確立 | |
| 医療及びリハビリテーション 医療の充実 | 医療体制の充実 医療給付制度の充実 リハビリテーション医療実施体制の整備 | |
| 精神保健対策の推進 | 適正な医療の普及 地域精神保健対策の推進 社会復帰対策の推進 | |
| 専門従事者の確保 | 専門従事者の確保 | |
| 福 祉 | 生活安定のための施策の充実 | 年金・手当や資金貸付の充実及び制度の周知 経済的負担の軽減 |
| 在宅生活支援サービスの拡充 | 相談・情報提供機能の充実 障害の重度化・重複化や障害者の高齢化に応じた在宅 福祉サービスの充実 福祉機器サービスの充実 地域福祉活動の推進 | |
| 施設福祉サービスの充実 | 施設の整備・充実 施設におけるリハビリテーション機能の充実 障害の重度化・複数化や障害者の高齢化に応じた 処遇の確保と向上 施設機能の強化及び地域開放 | |
| ひとづくりの推進 | 福祉マンパワーの養成・確保 ボランティア活動への参加の促進 | |
| 生 活 環 境 | 住みよいまちづくりの総合的 推進 | 各種指針の策定・普及 推進体制の整備 関連事業の推進 |
| 住宅・建築物の改善 | 障害者のニーズに対応した住宅整備の推進 公共的建築物等の構造の改善 | |
| 移動・交通対策の推進 | 道路交通安全の確保 交通ターミナルの整備 移動・交通手段サービスの普及・充実 ガイドマップの作成 | |
| 情報提供体制の整備・充実 | 障害者に対する情報提供体制の充実 視聴覚障害者に対する情報提供体制の整備・充実 | |
| 防犯・防災対策の推進 | 地域における防犯・防災体制の充実強化 住宅・施設の防災対策の強化 | |
| 文 化 ・ ス ポ | ツ ・ 交 流 | 文化活動の促進 | 文化活動への参加促進 文化活動への支援 |
| スポーツ・レクリエーションの 推進 | 生涯スポーツやレクリエーションの推進 障害者の参加が可能な運営方法やルールの普及 競技スポーツの振興と競技スポーツ団体の育成 | |
| 交流の促進 | 交流・ふれあい活動の推進 国際交流の促進 |
| 第1節 啓発・広報 ~ノーマライゼーション理念の浸透~ |
|---|
障害をもつ人々も障害をもたない人々も、ともに等しく人間として普通に暮らせる社会を実現するためには、障害や障害者に対する偏見や差別の意識など「心の壁」を取り除くことが必要です。
「心の壁」を取り除き、ノーマライゼーションの理念の浸透を図るうえで、啓発・広報活動は、基本的で重要な要素です。
テレビなどのマスメディアの活用による啓発・広報や福祉教育の推進、さらには、障害をもつ人々と障害をもたない人々との交流を進める必要があります。
特に、幼児期からの障害者との自然なふれあいが、「心の壁」を取り除くのに大きな効果をもたらします。
| 重点目標 |
|---|
| 1 啓発・広報の推進 |
| 2 福祉教育の推進 |
| 3 交流・ふれあいの促進 |
1 啓発・広報の推進
| 現状と課題 |
|---|
- 12月9日の「障害者の日」を中心に、テレビなど各種のマスメディアを活用した広報活動が行われてきており、人々の障害や障害者への関心は高くなってきています。
しかしながら、心身障害者(児)実態調査(平成2年度)の結果によると、「障害及び障害者について社会の理解がある。」と回答した障害者は3割あまりに過ぎません。 - 障害者の福祉は特定の人の問題であるという誤った認識があることや、啓発・広報の多くが行政を中心にした送り手側の一方通行になりがちであることなどから、今後、障害に関する正しい理解と認識を深めるための効果的な啓発・広報を工夫する必要があります。
- 【障害者問題への関心度】全国20歳以上の者2,271人対象
- 「機会があれば、障害をもつ人ともたない人相互の交流活動や、共に活動する催しや機会、ボランティア活動に参加したいと思うか。」
| 回答 | (%) |
|---|---|
| 是非参加したい | 4.3 |
| 機会があれば参加したい | 54.4 |
| わからない | 11.7 |
| 参加したくない | 29.6 |
- 【障害・障害者への理解度】県内身体障害者・精神薄弱者41,644人対象
- 「社会の人は障害者問題に対して理解を示していると思いますか。」
| 回答 | (%) |
|---|---|
| 非常に理解 | 8.9 |
| どちらかといえば理解 | 26.8 |
| わからない | 37.5 |
| どちらかといえば無理解 | 19.9 |
| 無理解 | 6.8 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | マスメディアの有効活用 | ● 障害者団体、住民団体、行政機関、報道機関の連携により、広報誌、テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアを通じて、障害や障害者に関する各種の情報を提供し、県民の正しい理解と認識の普及を図ります。 |
| 2 | 「障害者の日」等の有効利用 | ● 「障害者の日」※1、「人権週間」※2、「障害者雇用促進月間」※3、「精神保健普及運動」※4、「身体障害者福祉週間」※5、「精神薄弱福祉月間」※6 などの機会を利用し、各種行事等を開催しながら、重点的な啓発・広報に努めます。特に、幅広い参加が得られるように工夫します。 |
| 3 | 住民参加による住みよい福祉のまちづくりの推進 | ● 住みよい福祉のまちづくりのための各種事業を住民参加により、地域ぐるみで進めていくことを通して、人々の「心の壁」を取り除くことに努めます。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉啓発事業 | 身体障害者についての正しい理解を得るための各種の広報誌の発行、福祉展・講演会・映画会等の開催、施設見学などの実施 | 全市町村での実施 | 障害福祉課 | 市町村 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| マスメディアを利用した啓発・広報 | テレビや新聞を広告媒体とした障害や障害者についての正しい理解と認識の促進 |
| 障害者の日を利用した啓発・広報 | 障害者の日を中心とした行事の開催による障害者の人権の尊重など「障害者の日」の趣旨についての県民理解の促進 |
| ※1 | 障害者の日 | |
| 12月9日をいう。1981年(昭和56年)の国際障害者年に、国民の障害者問題についての理解と認識を深め、福祉の増進を図ることを目的として制定された。国際連合で「障害者の権利宣言」が採択された日で、障害者基本法に規定されている。 | ||
| ※2 | 人権週間 | |
| 12月4日から同月10日までの1週間をいう。 | ||
| ※3 | 障害者雇用促進月間 | |
| 9月1日から同月30日までの1月間をいう。 | ||
| ※4 | 精神保健普及運動 | |
| 期間は特に定められていないが、おおむね10月又は11月の1週間を定め、各種の行事等を行う。 | ||
| ※5 | 身体障害者福祉週間 | |
| 12月9日から同月15日までの1週間をいう。 | ||
| ※6 | 精神薄弱福祉月間 | |
| 9月1日から同月30日までの1月間をいう。 |
2 福祉教育の推進
| 現状と課題 |
|---|
- 障害や障害者についての正しい理解と認識を深めるためには、体系的、長期的な福祉教育が重要です。これまで、「福祉のこころ」を育てるため、小・中・高等学校の児童・生徒に対して、ボランティア協力校※1や福祉教育研究校※2の指定による福祉教育が進められてきました。
- 学校での福祉教育はある程度進められてきましたが、今後は、幼児期からのふれあい教育や学校での成果を地域で実践していくことが課題です。
- 地域の人々を対象として、「福祉講座」や「福祉体験学習」※3等が社会福祉協議会などにより行われていますが、今後もその拡大が必要です。
| ※1 | ボランティア協力校 | |
| 県下の小学校、中学校、高等学校を毎年数十校ずつ指定し、3年間、体験学習を目的とした実践的活動などを行う。 | ||
| ※2 | 福祉教育研究校 | |
| 県下の小学校、中学校を毎年数校ずつ指定し、2年間、児童・生徒の福祉教育の推進に必要な研究を行う。 | ||
| ※3 | 福祉講座 福祉体験学習 | |
| 地域の社会福祉協議会が中心になって、地域住民を対象に随時開催している。市民手話講習会、介護セミナー、施設見学ツアー、交流キャンプなど多種多様なものがある。 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 小中学校等の学校教育における福祉教育 |
● 障害及び障害者についての正しい理解と認識を深めるとともに、お互いの立場や心情を思いやり、相互に協力し合う精神や態度を養うため、保育園・幼稚園、小・中・高等学校などにおいて、教職員等の理解を深めるとともに、ふれあい教育、福祉教育や交流教育の充実を図ります。
● 学校での福祉教育の成果を生かすため、社会福祉協議会やボランティア団体などとの連携を図り、地域でのボランティア活動に結びつけます。 |
| 2 | 一般社会人を対象とした啓発・広報 | ● 地域社会の人々の障害や障害者についての正しい理解と認識を深めるため、社会福祉協議会が行う関連事業や社会教育、生涯学習を通じて啓発・広報活動の充実を図ります。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉教育研究指定校事業 | 小学校、中学校の指定による児童・生徒の発達段階に応じた福祉教育の推進 | 社協やボランティア団体などとの連携強化28校→42校 | 社会課 | 市町村 |
| 福祉講座等開催事業 | 一般市民を対象とした福祉講座や介護教室の開設 | 参加者の拡大 | 社会課 | 社会福祉協議会等 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 一般県民を対象とした福祉講座の開催 | 広く県民を対象とした福祉講座の開設による障害や障害者についての正しい理解と認識の普及促進 |
| 行政関係者を対象とした福祉研修会の開催 | 民生部門に限らず、県職員ほか広く行政関係者を対象とした福祉研修会の開催による障害や障害者についての正しい理解と認識の促進 |
3 交流・ふれあいの促進
| 現状と課題 |
|---|
- 障害者に対する偏見や差別意識の多くは、「障害」を知らないことに起因しています。障害や障害者を正しく理解し、認識するためには、知識を増やすことはもちろん、地域の人々が各種のボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参加するなど日常生活のなかで、障害をもつ人々との交流・ふれあいを深めることが重要です。
- 学校における交流教育や地域交流キャンプとともに、地域の人々の福祉施設行事への参加や福祉施設入所者の地域行事への参加など、交流・ふれあいの機会や場は着実にひろがってきていますが、今後さらに交流・ふれあいのための条件整備を図っていく必要があります。
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | ボランティア活動への支援 | ● 学校教育、社会教育をはじめ、生涯学習の幅広い分野において、地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するように努めます。 |
| 2 | 相互交流の充実 | ● 障害をもつ人々も障害をもたない人々も、ともに参加できる文化・スポーツ大会などの開催により、交流・ふれあいの場をひろげ、相互の交流を促進するとともに、自治会、こども会など身近な場における自然な交流が行われるよう啓発に努めます。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| ボランティア活動への支援 | ボランティア基金の果実などによるボランティアの育成、活動に対する支援体制の強化やボランティア団体の先駆的活動への支援など | ボランティア活動の振興・促進 | 社会課 | 県 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 地域交流の推進 | 交流会や交流キャンプを通じての地域の障害児(者)と健常児の日常的な交流の促進によるノーマライゼーションの理念の自然な浸透 |
| 自治会、子供会などの啓発 | 関係機関の連携による自治会やこども会への障害に関する情報提供や障害者の自治会活動への積極的な参加へ向けた啓発活動 |
| 第2節 教育・育成 ~健やかな成長を願って~ |
|---|
どのような障害をもつ人々も大きな可能性をもっているという認識に立ち、それぞれに応じた教育・育成が保障される必要があります。
特に、障害をもつ子どもの場合、年齢や障害に応じた特別の配慮が必要とされており、教育や育成が一貫した形で行われることが大切です。
また、障害者が生涯学習を進めるためには、社会教育の場においても学習の機会を整備し、充実していくことが大切です。
| 重点目標 |
|---|
| 1 就学前教育・療育の充実 |
| 2 義務教育段階の教育の充実 |
| 3 後期中等教育段階の教育の充実 |
| 4 教職員等の指導力の向上 |
| 5 社会教育の充実と生涯学習の推進 |
1 就学前教育・療育の充実
| 現状と課題 |
|---|
- 障害児の早期発見、早期療育を推進するため、医療・福祉・教育の関係機関が連携し、相談、治療、療育などの一貫した体制をとる「総合療育機能推進事業」※1を県下8地区で実施しており、年々充実を図っています。
また、盲学校と聾学校に設置されている幼稚部、県内12校の特殊教育諸学校※2に設置されている「障害幼児教育相談室」※3、市町村が開設している「ことばの教室」※4などが早期教育・療育の対応を行っています。
これら関係機関や制度の連携を深めていくことが今後の課題です。 - 障害児を地域の保育所や幼稚園で受け入れ、保育や就園機会の確保を図っており、今後も受け入れ体制を強化していく必要があります。
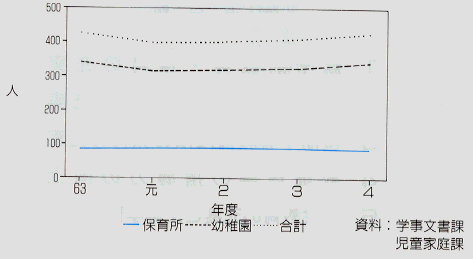
| ※1 | 総合療育機能推進事業 | |
| 第4節「保健・医療」を参照のこと。 | ||
| ※2 | 特殊教育諸学校 | |
| 盲学校、聾学校、養護学校(精神薄弱、肢体不自由、病弱)の総称 | ||
| ※3 | 障害幼児教育相談室 | |
| 就学に関する相談、生活や運動の指導、保護者に対する助言を随時又は継続的に行う。 | ||
| ※4 | ことばの教室 | |
| 言語に障害のある幼児に対する指導・訓練、保護者に対する助言・指導を月に数回行う。 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 盲・聾学校幼稚部の充実 | ● 教育担当者の資質向上のため、研修会や講習会をより充実します。 |
| 2 | 幼稚園や保育所での障害児の受け入れの促進 | ● 教育・保育担当者の資質向上のため、研修会や講習会をより充実します。 ● 保護者に対する就学前教育の啓発を行うとともに、運営費の支援措置を充実し、障害児に対する一層の受け入れの促進と手厚い処遇を確保します。 |
| 3 | 教育、医療、福祉等関係機関による指導・相談体制の整備 | ● 平成7年度にセミナーパーク※1に開設される新しい教育研修所の特殊教育部門※2が「障害幼児教育相談室」、「ことばの教室」などの教育部門の核となり、専門的な相談や指導を行います。 また、総合療育システムの一翼を担い、医療・福祉など、関係機関との連携により一貫した総合的な指導を行います。 ● 保護者を対象とした研修や情報交換の場を設定し、障害児に対する理解と保護者との連携を図ります。 |
盲・聾学校幼稚部の在籍数の推移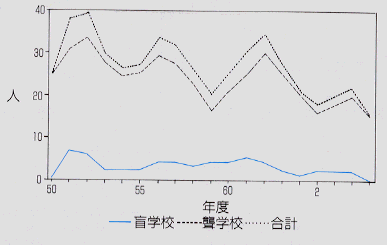
資料:山口県統計年鑑
| ※1 | セミナーパーク | |
| 平成7年度に山口市に開設予定の、自治研修、社会福祉研修、教育研修を核とする研修施設。民間団体や一般県民も利用できる。 | ||
| ※2 | 新しい教育研修所の特殊教育部門 | |
| 関係職員に対する研修、教員に関する調査研究、障害児と保護者に対する相談・指導・援助を行う機関 |
2 義務教育段階の教育の充実
| 現状と課題 |
|---|
- 昭和54年度に養護学校教育の義務制が実施されて以来、本県においても養護学校の整備を進めており、現在12校の特殊教育諸学校が地域の特殊教育※1の核としての役割を担っています。
- 平成5年度から小・中学校における通級における指導※2が制度化され、軽度障害児に対するきめ細かな指導の充実が図られていますが、学習障害(LD)※3などの新たな課題への対応が必要になっています。
- 教職員全体に対して、特殊教育についての研修会・講習会を開催しており、学校教育全体におけるなお一層の理解と認識の向上を進めています。
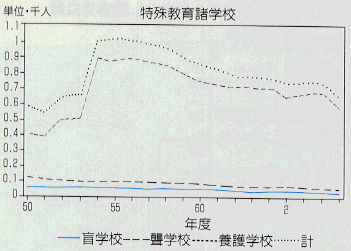
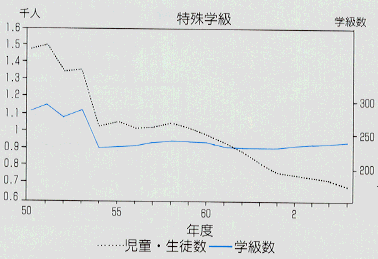
資料:山口県統計年鑑
| ※1 | 特殊教育 | |
| 障害を有する児童・生徒を対象として、特別な配慮のもとに特殊教育諸学校や小・中学校で行われる教育 | ||
| ※2 | 通級による指導 | |
| 小・中学校の通常の学級に在席している軽度の障害児に対し、障害に応じた養護・訓練などの特別の指導を通級指導教室で行うという特殊教育の形態 | ||
| ※3 | 学習障害(LD=Learning Disabilities) | |
| 軽度障害の一種として近年注目されるようになったもの。全般的な知的発達の遅れはないのに、特定の能力(聞く、話す、読む、書く、計算する等)の習得と使用に著しい困難を示すさまざまな障害群の総称 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 教育方法・内容の改善、研究による質的充実 | ● 障害の重度化・重複化や学習障害など、課題の多様化に対応できるよう、教育内容等の改善及び研究に努めます。 |
| 2 | 学校教育全体における特殊教育への認識の向上 | ● 一般校を含めた教職員全体に対する研修をより充実します。 ● 学校教育全体で障害児を受け止めるという観点から、小・中学校と特殊教育諸学校の児童・生徒の交流教育を推進します。 |
| 3 | 就学指導体制における連携の強化 | ● 就学指導※1にあたっては、関係機関が早期の相談・支援を行うよう、連携の強化を図ります。また、就学後も各学校と引き続き連携をとり、適切な指導を行います。 |
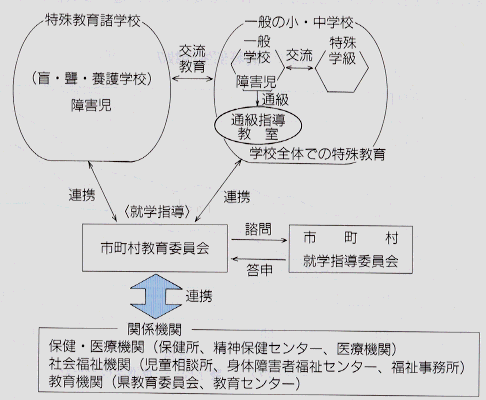
| ※1 | 就学指導 | |
| 障害に応じた適切な教育を行うため、市町村教育委員会は各障害児ごとに教育措置(一般の小・中学校か特殊教育諸学校かなど)を決定する。 決定にあたっては、専門家で組織される市町村就学指導委員会の意見を聴くこととされている。 |
3 後期中等教育段階の教育の充実
| 現状と課題 |
|---|
- 身体障害児に対する後期中等教育※1は早くから整備されていましたが、精神薄弱児についても養護学校に順次高等部を新設し、定員を大幅に拡大してきました。
- 養護学校高等部の入学選抜基準を見直し、平成3年度以降はすべての高等部に重複障害学級※2を設置しましたが、今後も進学希望者の増加が見込まれます。
- 一般の高等学校で教育を受けることが可能な生徒については、施設の改善などにより受け入れを行ってきましたが、今後も必要に応じ、適切な改善を図る必要があります。
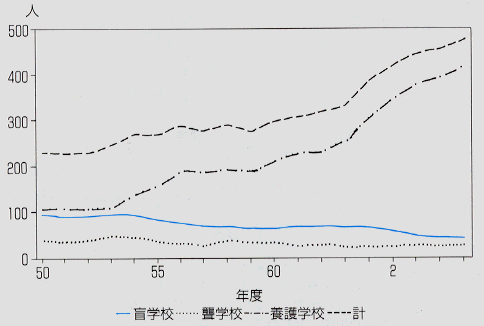
資料:山口県統計年鑑
| ※1 | 後期中等教育 | |
| 一般の高校、特殊教育諸学校の高等部で行われる教育 | ||
| ※2 | 重複障害学級 | |
| 心身の障害を2つ以上併せ持つ生徒で編成される学級で、教職員の配置が手厚い。 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 特殊教育諸学校高等部の整備・充実 | ● 養護学校高等部については、教育機会の一層の確保と教育環境の充実を図るため、引き続き、施設や設備の整備・充実に努めます。 ● 高等学校においても、障害のある生徒の受け入れのための施設や設備の改善に努めます。 |
| 2 | 職業教育、進路指導の充実 | ● 生徒のニーズの多様化に対応した進路指導を行うため、職業教育や進路指導のあり方の調査・研究を進めるとともに、教育・福祉・労働などの関係機関との一層の連携を図ります。 |
特殊教育諸学校の高等部の整備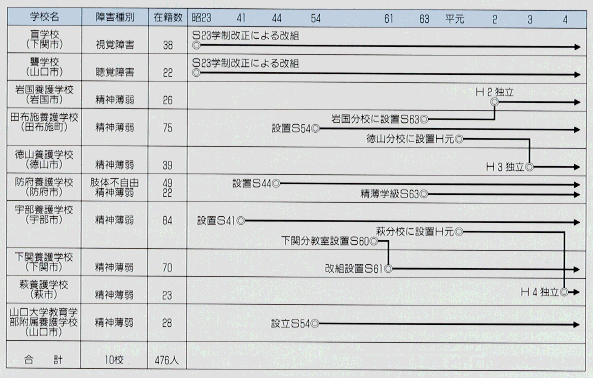
4 教職員等の指導力の向上
| 現状と課題 |
|---|
- これまで、特殊教育の向上を図るため、専門的な研修会や講習会を開催するとともに、国の実施する長期、短期研修へ教員を派遣してきました。
- 今後は、さらに障害別の研修会などを充実させることにより、指導の専門性をより高める必要があります。
| 施策の方向 | 具体的取り組み |
|---|---|
| 教職員等の指導力の向上 |
● 平成7年度に開設される新しい教育研修所が本県の特殊教育の研究や研修の中核となり、教職員の資質の向上に努めます。
● 特殊教育長期研修教員の派遣制度や、教育職員免許法に係る認定講習※1の充実に努めます。 |
| ※1 | 教育職員免許法に係る認定講習 | |
| 特殊教育諸学校の教員は、原則として普通免許状に加え、特殊教育諸学校の免許状が必要である。これは、大学の教員養成課程のほか、県教育委員会が行う現職の教員に対する認定講習の受講などによっても取得できる。 |
5 社会教育の充実と生涯学習の推進
| 現状と課題 |
|---|
- 生涯学習※1を推進するため、山口県生涯教育センター※2や各市町村の関係機関は、さまざまな学習機会の提供を行ってきました。
- 行政機関が関係団体に委託して、障害種別に応じた家庭生活や社会生活に関する教養教室などを開催しています。しかし、近年組織離れの傾向が見られるため、幅広い参加を得るための方策が必要です。
- 美術館や博物館など生涯学習の場となる施設の料金割り引きなどの優遇措置が、公立施設を中心に図られてきました。
- 公民館などの施設・設備のハード面の整備や手話通訳の派遣などのソフト面の充実が進みつつあるものの、今後、障害者が参加できる学習の場の一層の確保が必要です。
- 生涯学習の成果を生かしたボランティア活動(生涯学習ボランティア)※3の重要性が注目されています。今後は、ボランティア活動を日常生活の一部として、障害者自身が活動に参加することが望まれます。
| ※1 | 生涯学習 | |
| 自己の充実・啓発や生活の向上のため、自発的意思に基づき自己に適した手段・方法を選んで生涯を通じて行う学習活動 | ||
| ※2 | 山口県生涯教育センター | |
| 学習情報の提供、相談、啓発、指導者の養成等を行う機関で、山口市に設置 | ||
| ※3 | 生涯学習ボランティア | |
| 生涯学習とボランティア活動の関連は次の3つの視点からとらえられる。 1.自己実現の手段としてのボランティア活動(ボランティア活動そのものが生涯学習である。) 2.学習の成果を生かし深める実践としてのボランティア活動 3.人々の生涯学習に協力・支援するボランティア活動 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 地域における学習の場の充実・確保 | ● 障害者団体など関係団体の組織力の強化とともに、教養教室などの内容の充実と参加者の拡大を図ります。 ● 障害者が参加できる学習の場を確保するため、公的施設や設備の改善を進めるとともに、民間の公共的施設の改善に対して助成制度などにより支援します。 ● 障害者が参加できる学習の場が設定されるよう広く啓発活動を行うとともに、手話通訳派遣制度など関係制度の周知に努めます。 ● 美術館や博物館など学習活動の場となる施設の利用を進めるため、優遇措置の拡大と普及を図ります。 |
| 2 | 生涯学習ボランティア活動の推進 | ● 広く生涯学習ボランティア活動を推進するため、生涯学習ボランティアセンター※1が中心となり、学習情報の提供体制の整備充実に努めます。 ● 障害者自身のボランティア活動への積極的な参加を進めるため、啓発活動や障害者団体などへの働きかけを行います。 |
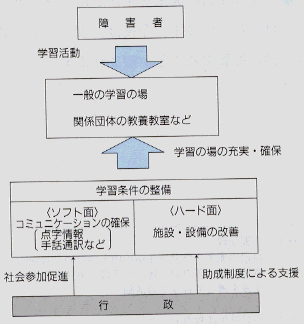
| ※1 | 生涯学習ボランティアセンター | |
| 県内7教育事務所にコーディネーターを配置し、ボランティア活動や学習情報の収集・提供、ボランティアグループに対する交流促進を行う。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 心身障害児理解推進事業 | ○小・中学校の児童・生徒と特殊教育諸学校の児童・生徒の交流教育の実施 ○特殊教育諸学校の児童・生徒と地域の人々との交流活動の実施 | 福祉教育の推進とノーマライゼーションの実現 | 指導課 | 県 |
| 心身障害児職業自立推進事業 | 障害児の職業自立を進めるために、職業教育、進路指導のあり方の調査・研究や労働・福祉など関係機関との連携強化を図る協議を実施 | 障害児の職業自立 | 指導課 | 県 |
| 障害幼児教育相談事業 | 障害の早期発見、早期教育の観点から、各特殊教育諸学校に相談室を置き、各種の相談に対応 | 適切な相談・支援の充実 | 指導課 | 県 |
| 各種研修会・講習会 | 小・中学校の一般教員の特殊教育担当者を対象とする研修会や講習会の開催 | 特殊教育への理解と指導力の向上 | 指導課 | 県 |
| 心身障害児就学指導地方研究協議会 | 各市町村の就学指導担当者及び就学指導委員会の委員などを対象とする障害児の適正就学についての研究協議会の開催 | 担当者の資質の向上 | 指導課 | 県 |
| 山口県心身障害児就学指導委員会活動事業 | 依頼のあった児童・生徒の障害の状況を調査・判定し、適正就学を指導 | 適切な就学先の保障 | 指導課 | 県 |
| 生涯学習ボランティア活動総合推進事業 | 生涯学習の成果を地域社会における諸活動で生かすことができるよう、各種のボランティア活動を総合的に促進 | 障害者を含めたうるおいのある地域づくり | 社会教育課 | 県 |
| 障害者の明るいくらし促進事業 | 障害種別に応じた家庭生活・教養・社会生活などの研修の実施や手話通訳の派遣などコミュニケーションの確保への支援 | 障害者の地域社会での自立と参加 | 障害福祉課 | 県 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 保護者を対象とした研修等の場の設定 | 障害児と保護者がいっしょに参加する療育キャンプを開催し、日常生活、機能回復、言語訓練などの方法を研修 |
| 学習障害など軽度の障害児への対応 | 障害の特性に応じた教育方法の工夫・改善の研究 |
| 第3節 雇用・就業 ~社会の一員として~ |
|---|
働くことは、生活していくうえでの経済的な基盤であるとともに、社会の一員として社会に参加し、貢献しているというよろこびを与えてくれます。
障害者の多くが就労を望んでおり、それぞれの適性と能力に応じた就労の機会を確保していくことが必要です。
障害者の一般雇用の促進と安定を図るとともに、雇用、福祉等の密接な連携による有機的な職業リハビリテーションを充実していくことが必要です。
雇用されることが困難な障害者の福祉的就労の場の整備についても、推進することが必要です。
| 重点目標 |
|---|
| 1 雇用の促進と安定 |
| 2 職業リハビリテーション対策の推進 |
| 3 福祉的就労の場の整備促進 |
1 雇用の促進と安定
| 現状と課題 |
|---|
- 障害者の雇用に対する事業主の理解と関心が高まりつつあり、雇用される障害者の数は着実に増加しています。平成5年6月1日現在、県内の民間企業における実雇用率は、1.81%となっており、法定雇用率1.6%を大きく上回っています。
- しかしながら、法定雇用率未達成の企業もあり、一部の業種・企業規模において、障害者の雇用に立ち遅れが見られます。
障害の重度化・重複化や障害者の高齢化が進んでおり、障害者をとりまく環境は依然として厳しいものとなっています。
今後は、特に重度障害者の雇用対策に重点を置き、障害者の雇用に関する社会環境の整備を図りながら、障害者が可能な限り一般雇用の場に就くことができるように、障害の特性に応じたきめ細かな障害種類別対策を進める必要があります。
(各年6月1日現在)
| 年次 | 対象企業数(企業) | 雇用障害者数(人) | 雇用率(%) | 未達成割合(%) | 法定雇用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S60年 | 434 | 1,379 | 1.57 | 27.6 | 1.5 |
| S61年 | 427 | 1,358 | 1.55 | 28.8 | |
| S62年 | 423 | 1,298 | 1.53 | 32.4 | |
| S63年 | 509 | 1,456 | 1.60 | 36.9 | 1.6 |
| H元年 | 520 | 1,511 | 1.63 | 37.5 | |
| H2年 | 534 | 1,575 | 1.64 | 35.2 | |
| H3年 | 557 | 1,700 | 1.67 | 34.3 | |
| H4年 | 590 | 1,841 | 1.75 | 32.7 | |
| H5年 | 591 | 1,917 | 1.81 | 30.1 |
| (1) | 対象企業は、昭和62年以前については常用労働者数67人以上、昭和63年以降につい |
| ては63人以上のものである。 | |
| (2) | 「雇用障害者」とは、昭和62年以前は身体障害者のみ、昭和63年以降については精 |
| 神薄弱者を含む。 | |
| (3) | 「雇用障害者数」の計上にあたっては、重度障害者については、ダブルカウント |
| (1人を2人として計算)してある。 | |
| 資料:職業安定課 |
身体障害者の就労の状況(障害程度別)
(心身障害者(児)実態調査)
| 障害程度別 | 就労比率(%) | |
|---|---|---|
| 昭和60年度 | 平成2年度 | |
| 1級 | 24.1 | 28.0 |
| 2級 | 25.9 | 28.8 |
| 3級 | 33.0 | 34.4 |
| 4級 | 45.9 | 47.2 |
| 5級 | 53.4 | 54.8 |
| 6級 | 47.2 | 50.3 |
| 合計 | 37.7 | 39.5 |
精神薄弱者の就労の状況
(心身障害者(児)実態調査)
| 障害程度別 | 就労比率(%) | |
|---|---|---|
| 昭和60年度 | 平成2年度 | |
| 療育手帳A | 29.7 | 30.6 |
| 療育手帳B | 54.9 | 52.8 |
| もっていない | 34.8 | 36.6 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 総合的な雇用対策の推進 | ● 法定雇用率達成のための指導を強化するとともに、障害者が可能な限り一般雇用の場に就けるように努めます。 ● 市町村等の公的機関に対しては、民間企業に率先した障害者雇用の重要性について理解を促すとともに、全ての公的機関が法定雇用率を達成できるよう努めます。 ● 県民、事業主に対して、啓発・広報を積極的に行い、障害者が職業を通じて社会参加することの重要性についての理解を促進します。 ● 就職が可能な障害者の把握に努め、障害者の就職を促進します。 |
| 2 | 重度障害者雇用の推進 | ● 重度障害者の雇用機会の確保に努めます。 なお、第三セクター方式などによる企業の設置の可能性についても調査・研究を行います。 |
| 3 | 精神薄弱者、精神障害者の雇用対策の推進 | ● 職域の開発、職業能力開発、職場定着の推進等を図るため、人的援助体制などの条件整備を推進します。 ● 精神薄弱者援護施設からの就労自立を推進します。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 雇用率達成指導の強化 |
《民間企業に対する指導》 ○身体障害者雇用率制度の厳正な運用の促進 ○障害者雇用促進法の改正内容の周知 ○特定求職者雇用開発援助金等各種助成金制度の活用による就職の促進 ○公共職業安定所における特別求人開拓の実施 《市町村等公的機関に対する指導》 | 企業及び市町村機関等への指導強化 | 職業安定課 | 県 公共職業安定所 |
| 雇用の啓発、広報の強化 | 毎年9月の障害者雇用促進月間を中心として、雇用主をはじめとする県民一般に対し、障害者雇用の重要性に関する啓発活動を積極的に展開 | 県民の理解の促進 | 職業安定課 | 県 公共職業安定所 |
| 求職登録の促進と自立の援助 | ○障害者の求職にあたっては、一般求職者より、さらに手厚い取扱いを実施 ○ケースワーク方式による入念な職業指導、職業紹介、就職後の指導を行うとともに、その状況を詳細に記録し、職場定着、再就職に活用 | 事業の指導強化 | 職業安定課 | 公共職業安定所 |
| 精神薄弱者・精神障害者の就労体制の整備 | 精神薄弱者・精神障害者の雇用を促進するために、適職の開発、職場適応指導等の職業リハビリテーションの充実、企業の受け入れ体制の整備、職業相談及び指導を実施 | 事業内容の充実 | 職業安定課 | 県 公共職業安定所 地域障害者職業センター |
| 精神薄弱者社会自立再訓練事業 | 職場に定着できなかった精神薄弱者を精神薄弱者援護施設(入所施設)に一時的に入所させ、再就労のために必要な指導・訓練を実施 | 実施施設数の増 | 障害福祉課 | 県 |
| 精神薄弱者就労訓練事業 | 精神薄弱者援護施設及び精神薄弱児施設の入所者(児)の自立を図るため、社会自立の可能性がある人に対し、一定期間民間事業所において就労訓練を実施 | 実施人員の増員 | 障害福祉課 | 県 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 第三セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設置 | 重度障害者の雇用機会の確保を目的とした第三セクター方式による重度障害者多数雇用企業の設立の可能性についての調査・研究 |
2 職業リハビリテーション対策の推進
| 現状と課題 |
|---|
- 近年、障害の重度化・重複化が進んでおり、職場への適応がより困難な障害者が増加しています。
しかし、多くの障害者が就業を望んでおり、これらの人々が個々の能力や障害の程度に応じて職業的な自立が図られるようにしなければなりません。
このため、地域障害者職業センター※1、公共職業安定所、公共職業能力開発施設※2などと福祉部門との間で密接な連携・協力のもとに、職業能力の開発及び職業指導等のきめ細かな職業リハビリテーションを実施する必要があります。
また、障害者のもてる能力を最大限に発揮できるように、職業能力の開発・向上を図るとともに、企業が取り組む職業能力開発等への支援も必要です。
| 年度 | 県内校(人) | 県外校(人) |
|---|---|---|
| 60年 | 6 | 20 |
| 61年 | 10 | 11 |
| 62年 | 2 | 20 |
| 63年 | 4 | 22 |
| 元年 | 4 | 16 |
| 2年 | 5 | 4 |
| 3年 | 5 | 6 |
| 4年 | 7 | 10 |
| 5年 | 4 | 11 |
| (1) | 県内校とは、東部高等産業技術学校、西部高等産業技術学校、山口職業能力開 |
| 発促進センター、小野田職業能力開発促進センターのことです。 | |
| (2) | 県外校とは、広島及び福岡の障害者職業能力開発校のことです。 |
| 資料:職業能力開発課 |
| ※1 | 地域障害者職業センター | |
| 就職を希望している人の相談・職業能力評価を行うとともに、職業生活に必要な労働慣習を身につけるための訓練を行い、障害者の就職の促進と職場への適応を援助するための施設で、県内には防府市に山口障害者職業センターが設置されている。 | ||
| ※2 | 公共職業能力開発施設 | |
| 技能の向上や資格の取得などの職業能力開発を進める施設で、県内には障害者だけを対象にした障害者職業能力開発校はないが、高等産業技術学校、職業能力開発促進センターが設置されている。 |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 職業能力開発機能の充実 | ● 公共職業能力開発施設などにおける障害者の職業能力開発の機会の拡大に努めます。 ● 全国身体障害者技能競技大会※1を通じ、障害者の職業能力開発を推進します。 |
| 2 | 実践的研究の成果及び就労支援機器の普及 | ● 障害の重度化・重複化に対応して、事業主が取り組む職務開発及び就労支援機器の利用等による職場環境の改善などを支援し、重度障害者や精神薄弱者の雇用機会の拡大と職場定着を図ります。 |
| 3 | 職業リハビリテーションネットワーク体制の整備 | ● 教育、福祉及び医療機関との連携によって、就職を希望する障害者の把握に努めるとともに、職業的自立に向けた一貫した職業リハビリテーションのネットワークづくりに努めます。 |
| ※1 | 全国身体障害者技能競技大会 | |
| 身体障害者の職業能力の開発を促進し、技能を通じて身体障害者に対する社会的理解と認識を高めるための全国大全で、平成5年度、山口県からは2人が参加した。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 公共職業能力開発施設等の充実 | ○障害者の職業能力開発ニーズに応え、健常者とともに訓練可能な者について入校を促進するとともに、必要な訓練を実施 ○障害の種別・程度に応じ、国等が設置している障害者職業能力開発施設への入校の相談・指導を実施 | 障害者のニーズにあった職業能力開発体制の充実 | 職業能力開発課 | 県 雇用促進事業団 |
| 技能競技大会への参加 | 《全国身体障害者技能競技大会への選手派遣》 ○職業能力の開発促進 ○技能労働者として社会に参加する自信と誇りと意欲の高揚 | 障害者の職業能力の開発・向上の推進 | 職業能力開発課 | 県 |
| 職域の拡大及び職場環境改善指導 | 障害者がもつ能力を最大限に発揮できるような職場作りが重要なことから、障害者が作業を容易に行えるように開発された就労支援機器や効果的な職場改善手法の普及促進 | 事業の普及 | 職業安定課 | 公共職業安定所 |
| 職業リハビリテーション体制の整備 | 障害者の職業的自立を促進するため、地域障害者職業センター、公共職業安定所などが中心となり、教育、福祉及び医療部門との密接な連携と協力のもとに、情報交換などを実施 | ○関係機関の連携強化 ○事業内容の充実 | 職業安定課 | 県 |
3 福祉的就労の場の整備促進
| 現状と課題 |
|---|
- 多くの障害者が働くことを通じて社会へ参加することを望んでいます。
しかし、障害者の中には一般の企業で働くことが困難な人もいます。
そのため、県内には授産施設や福祉工場、福祉作業所などが設置されています。 - 現在、養護学校等の卒業生や脳卒中の後遺症などによる中途障害者等で、障害が重く、一般企業で雇用されることが困難な人たちが増えています。
また、在宅志向が高まるなか、地域における障害者のいきがいの拠点としての役割が重要になってきています。 - 今後は、地域に密着し、障害者にとって身近で利用しやすい、福祉的就労の場の整備をさらに進める必要があります。
| 施設種別 | 箇所数(箇所) | 定員(人) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者授産施設 | 7 | 296 | 入所・通所・分場 |
| 身体障害者福祉工場 | 1 | 50 | - |
| 精神薄弱者授産施設 | 13 | 640 | 入所・通所 |
| 心身障害者福祉作業所 | 30 | 340 | 通所 |
| 計 | 51 | 1,326 | - |
| 施策の方向 | 具体的取り組み | |
|---|---|---|
| 1 | 福祉作業所の拡充 | ● 身体障害者と精神薄弱者をともに受け入れることができ、かつ、身近な所に設置できる福祉作業所の整備を促進します。 ● 利用者及び職員の処遇の向上を図るため、助成制度の充実に努めます。 ● 既存の福祉作業所のなかで、可能なものについては法人化により、国制度の施設への転換を推進します。また、既存の授産施設を母体とした分場方式への移行も促進します。 |
| 2 | 授産施設の拡充 | ● 在宅福祉を推進する観点から、通所型を中心にした授産施設の整備を促進します。 ● 対象者の少ない地域においては、既存の授産施設を母体とした分場方式の活用により就労の場の確保に努めます。 |
| 3 | 福祉工場の整備 | ● 相当の作業能力はあるが、一般就労の困難な障害者の職業的自立を図るため、関係機関と連携して精神薄弱者等の福祉工場の整備を促進します。 ● 既存の福祉工場については、経営の効率化、運営の安定化を図るため、設備の近代化などにより運営充実を図ります。 |
《主要事業》
| 事業名 | 事業内容 | 目標 | 所管課 | 事業主体 |
|---|---|---|---|---|
| 心身障害者福祉作業所設置運営事業 | 在宅の心身障害者で雇用されることが困難な者を通所させて、その能力に応じた授産指導を行い、自立を促進する施設 | ○運営費の充実 ○整備の促進30→34箇所 | 障害福祉課 | 市町村 |
| 身体障害者授産施設 | 身体障害者で雇用されることが困難な者を通・入所させて自立を促進する施設 | ○分場型の拡大 ○整備の促進7→9箇所 | 障害福祉課 | 社会福祉法人 |
| 精神薄弱者授産施設 | 精神薄弱者で雇用されることが困難な者を通・入所させて自立を促進する施設 | ○通所型施設の整備 ○分場型の導入促進 ○整備の促進13→16箇所 | 障害福祉課 | 市 社会福祉法人 |
| 身体障害者福祉工場 | 作業能力はあるものの一般企業で就労できない身体障害者を雇用し、生活指導と健康管理のもとに社会自立を促進する施設 | ○整備の近代化 ○事業内容の拡大 ○運営の安定 | 障害福祉課 | 社会福祉法人 |
《今後の研究・検討事項》
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 精神薄弱者福祉工場の整備の促進 | 作業能力はあるものの一般企業で就労できない精神薄弱者を雇用し、生活指導と健康管理のもとに社会自立を図ることを目的とした「精神薄弱者福祉工場」の整備の促進 |
主題:
山口県障害者福祉長期ビジョン 1頁~58頁
みんなが参加しともにあゆむ21世紀をめざして
発行者:
山口県
発行年月:
1994年3月発行
文献に関するお問い合わせ:
山口県
