「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2010年8月号
(第30巻 通巻349号)毎月1回1日発行 800円
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
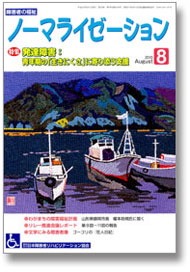
【8月号の特集】
発達障害:青年期の「生きにくさ」に寄り添う支援
発達障害のある人たちへの支援は、発達障害者支援法が成立したことで広く障害が知られるようになり、特別支援教育の対象に発達障害児が含まれるなかで、支援のあり方が議論されてきている。そのような中で青年期を迎え、自分らしさを見つめる時期になると、社会生活上の困難や対人関係のトラブルなどで、「生きにくさ」を感じたり、自己否定をしたり、また二次的な問題が発生する場合もある。
今回の特集では、発達障害の特性を理解し、青年期の「生きにくさ」に寄り添い、本人の社会参加や自分らしい生き方を実現するために、周囲はどのように関わるべきか、それぞれの分野で実践されている方々および本人の最も身近にいる家族の立場からご自身の経験を通してご提案いただく。
- 【グラビア】
- 夢を大きな宙(そら)に駆け巡らせて
自立生活夢宙センター 平下泰幸さん、平下耕三さん兄弟
写真・文:タケノウチシュウヘイ
- 夢を大きな宙(そら)に駆け巡らせて
- 【時代を読む】
- 宇都宮病院事件から精神保健法の誕生
伊東秀幸
- 宇都宮病院事件から精神保健法の誕生
- 【お知らせ】
- 【特集】 発達障害:青年期の「生きにくさ」に寄り添う支援
- 発達障害:青年期の「生きにくさ」に寄り添う支援
―「人権」の視点から考える―
石渡和実 - 発達障害者の生きにくさについて
―医療の立場から―
市川宏伸 - 作業療法士の立場から
―感覚統合理論の視点で発達障害を理解する―
石井孝弘 - 発達障害―青年期の支援を考える―
金子健 - 家族の立場から
田中晶子 - 生きにくさに寄り添う支援
―本人とその周囲をよく見ることの大切さ(浅草事件を通して)―
大石剛一郎
- 発達障害:青年期の「生きにくさ」に寄り添う支援
- 【1000字提言】
- レクリエーション
小山内美智子 - 「社会」がアタマにつく言葉の違い、ちょっと整理してみました。
栗原久
- レクリエーション
- 【わがまちの障害福祉計画】
- 山形県鶴岡市長 榎本政規氏に聞く
致道館の精神(こころ)と障害福祉
聞き手:宮崎昭
- 山形県鶴岡市長 榎本政規氏に聞く
- 【リレー推進会議レポート】
- 第8回~11回の報告
新谷友良
- 第8回~11回の報告
- 【ワールドナウ】
- 【文学にみる障害者像】
- ゴーゴリの『狂人日記』
高橋正雄
- ゴーゴリの『狂人日記』
- 【ほんの森】
- NPO法人日本脳外傷友の会編
『Q&A脳外傷 第3版 高次脳機能障害を生きる人と家族のために』
評者:細田満和子
- NPO法人日本脳外傷友の会編
- 【知り隊おしえ隊】
- 【列島縦断ネットワーキング】
- 〈山形〉「鶴高養現場実習支援の会」の歩みとこれから
佐藤公力 - 〈愛知〉まちづくりを通してつながる輪
―楽笑におけるまちづくりプロジェクトの取り組み―
小田泰久
- 〈山形〉「鶴高養現場実習支援の会」の歩みとこれから
- 【工夫いろいろエンジョイライフ】
- 実用編●小さな力で座席シートも簡単移動!、他●
提案者:藤田博文 イラスト:はんだみちこ
- 実用編●小さな力で座席シートも簡単移動!、他●
- 【インフォメーション】
- 【編集後記】
